2005年05月02日
■『仮面ライダー青春譜』プロローグ
※註:
この文章は、以前『ぼくのマンガ青春期』のタイトルで、すがやみつるのWebサイトに掲載していた作品です。出版を前提に書き直していましたが、読んだ人の好みによって、「マンガ史も含めてほしい」「特撮関連の部分だけでいい」などと、あれこれ異なる意見が続出したため、執筆の手も止まった状態になっています。
内容については、以前の原稿を全面改稿に近い状態で書き直していますが、筆者としては「1960年代から70年代前半にかけたマンガ史に、どのように関わってきたか」という記録にしたいと考えているのですが、お読みになったうえで、ご意見などいただけたら幸いです。
なお、まだドラフト段階のため、表記や敬称の統一ができていません。その点、ご了承のうえ、お読みください。
プロローグ
一九九八年二月三日の午後、西武池袋線桜台駅南口駅前の喫茶店に、八人のマンガ家が集合した。
集まったのは、永井豪、桜多吾作、ひおあきら、細井ゆうじ、山田ゴロ、成井紀郎、津原義明、そして、ぼく――すがやみつるの八名である。全員が、石ノ森章太郎先生のアシスタント経験者か、石ノ森作品の著作権管理をしていた石森プロの出身者だった。
ひさしぶりに顔を合わせた人も多かったのだが、簡単に挨拶しただけで、みんな口が重かった。
「そろそろ行こうか……」
最年長の永井さんにうながされ、ぼくたちはソファから腰をあげた。
喫茶店を出ると、西武池袋線のガードに沿って練馬の方角に歩きだす。
目的地は、桜台駅から徒歩十五分ほどのところにある石ノ森章太郎先生の自宅である。
石ノ森先生は、六日前の一月二十八日、長い闘病生活の末に、御茶の水の病院で永い眠りについていた。
先生の死去のニュースが報道されたのは、二日後の三十日になってからだった。家族だけの密葬にしてほしいという先生の遺志で、葬儀がすむまで亡くなったことが伏せられていたらしい。
しかし、せめて線香くらい手向けさせていただきたい――と、元アシスタントと弟子筋のマンガ家がそろって交渉した結果、ようやく、ご遺族の許しが得られ、この日の訪問となったのだった。
ガードに沿った細い道を進むと、すぐにバス通りに出る。西武池袋線がまだ高架ではなかった頃、ここには踏切があった。
踏切の際には一軒のパチンコ店があり、二階は広い喫茶店になっていた。
喫茶店の名は「ラタン」。店内の一角には石ノ森先生の専用席があった。先生は、毎日のようにこの席に坐り、ダンヒルの紫煙をくゆらせながらマンガのネームを入れていた。
専用席の近くのテーブルには担当編集者がすわり、先生のネームが入るのを待っていた。ネームが一ページ入るたびに、受け取った原稿用紙にトレーシングペーパーを載せ、吹き出しのなかのセリフを写し取っていく。これが編集者の仕事だった。
踏切の北側には交番があった。たくさんのファンやマンガ家志望者が、石ノ森先生の自宅への道をたずねた交番だ。あまりにも多くの若者が道をたずねるため、石ノ森先生が用意した専用地図まで置かれていた。
そんなことを思い出しながらバス通りに沿った歩道を歩き、途中で脇の路地に入る。住宅街を縫うように走る曲がりくねった細い道は、石ノ森先生宅までの抜け道にもなっていた。
「このあたりの景色、あまり変わってないなあ……」
住宅街の中に、ところどころ高くそびえる木々を見ながら永井さんがいった。
この道は、三十年以上も前、石ノ森先生のところでアシスタントをしていた永井さんも、よく通った道なのだ。
ぼくが初めて石ノ森先生のお宅に伺ったときに通ったのも、やはり、この道だった。
あのとき一緒に歩いていたのは、いまも横を歩いているひおあきらだった。
永井さんと初めて会い、細井ゆうじと知り合ったのも、同じ日――昭和四十二(一九六七)年三月二十五日のことだった……。
投稿者 msugaya : 03:40 | コメント (0) | トラックバック
■『仮面ライダー青春譜』 第1章 巨匠との遭遇(1)
●ニセ石森章太郎の正体
「きみが菅谷クン……?」
改札口を出たとたん、学生服姿の男子高校生が声をかけてきた。
学生服の襟元からは、派手なオレンジ色のタートルネックの襟がのぞき、整髪料でテカテカと光り固められた髪には、しっかりと櫛目がとおっている。いかにも都会の高校生――といったキザな姿で、静岡の田舎から出てきたばかりのぼくは、一瞬たじろいだ。
「は、はい……」
うろたえながらもなんとか返事をすると、前に立つ高校生が、笑顔になって自己紹介した。
「ミュータント・プロの菅野です」
「ど、どうも。菅谷です」
ペコリとお辞儀したぼくも、やはり学生服に身を包んでいた。
昭和四十二(一九六七)年三月二十五日の正午前。高校一年の三学期が終わり、春休みに入ったばかりのときである。
場所は、東京都練馬区の西武池袋線桜台駅。
この駅の北口改札口前で、ぼくが待ち合わせをしていた男子高校生は、〈ミュータント・プロ〉というマンガ研究会の会長だった。
名前は、菅野誠。年齢は、ぼくと同じ十六歳のはずなのに、いくぶん大人びて見えるのは、隙のない服装とヘアスタイルのせいにちがいない。同人誌では、本名のほかに、「ひおあきら」というキザなペンネームも使っていた。
ぼくの学生服は従兄弟のおさがりで、情けないほどヨレヨレにくたびれていた。中学生のときまで長髪禁止だった関係で、髪も高校一年の終わりになって伸ばしはじめたばかり。どこから見ても、田舎の高校生であることが一目瞭然だった。
東京に来るのは、小学六年生の修学旅行以来だった。つまり四年ぶりになる。前日のうちに上京したぼくは、亀戸の叔父の家で一泊させてもらったあと、国鉄総武線(当時)と地下鉄丸の内線、そして西武池袋線を乗り継いで、桜台駅までやってきたところだった。
この日ぼくは、初対面となるマンガ研究会の仲間に、会の名誉会長である石森章太郎先生と、名誉副会長の松本零士、久松文雄両先生のお宅に案内してもらうことになっていた。持参した原稿を先生方に見てもらうためである。脇に抱えたスケッチブックには、原稿のほかに、サインをもらうための色紙も挟んでいた。
石森先生のお宅は、住宅街の隙間をうねるように走る狭い道をたどった先にあった。桜台駅からは十五分くらいの距離である。
途中、ところどころに畑がひろがり、雑木林のような木立も見える。
――これが武蔵野の面影なのかなあ?
ぼくは、変なことを考えながら、菅野誠のあとをついていった。
菅野もぼくも、スケッチブックを小脇に抱えていた。スケッチブックには、マンガの原稿が挟まっている。この頃の典型的なマンガ少年のスタイルだった。もう少し寒い季節で、首に長いマフラーでも巻いていたら、もっと完全だったろう。気分だけは『ジュン』(石森章太郎)や『漫画家残酷物語』(永島慎二)の主人公のつもりだったのだ。
石森章太郎先生のお宅は、音楽大学の付属幼稚園の脇を抜け、少し坂を下った途中にあった。
青々とした芝生が茂る庭には、小さいながらもプールまである。建てられて間もない石森邸は、台風が来るたびに窓を釘で打ちつけるようなボロ家に住んでいたぼくにとっては、まさに白亜の豪邸で、ハリウッドスターの住まいのように、ピカピカと光り輝いて見えた。
先生は、まだおやすみで、庭先で奥さんが、長男の丈君をあやしていた。現在、俳優として活躍する丈君は、まだ一歳だった。
そこに遅れて〈ミュータント・プロ〉のメンバー三人が到着した。副会長の細井雄二、田村仁、近藤雅人の三人である。
菅野誠も含めた四人は、三鷹市内の中学の同級生だった。ぼくも影響を受けた石森章太郎先生の『マンガ家入門』に感化され、マンガ研究会「ミュータント・プロ」を結成したのが一年前のこと。肉筆回覧誌「墨汁三滴」も、すでに三号まで発行しているという。
「墨汁三滴」という会誌の名前は、石森章太郎先生が高校生のときに結成した〈東日本漫画研究会〉の肉筆回覧誌「墨汁一滴」の名前を受け継いだものだった。
石森先生たちの〈東日本漫画研究会〉には、赤塚不二夫、高井研一郎、横田とくお氏などが参加し、「墨汁一滴」にも原稿を寄せていた。「墨汁一滴」の題名は、もちろん正岡子規の随筆集にあやかったものだ。
〈ミュータント・プロ〉の会誌が「墨汁二滴」にならなかったのは、〈東日本漫画研究会・女子部〉が、先に「墨汁二滴」の名前をつけた肉筆回覧誌を発行していたからである。
「墨汁二滴」は、西谷祥子、志賀公江、神奈幸子といった人気少女マンガ家を輩出した同人誌としても知られていた。また、志賀、神奈の両氏は、「墨汁三滴」の名誉会員として、会誌の会員一覧ページにも名前をつらねていた。
庭先にいた奥さんの話によると、石森先生は、三時間ほど前にベッドに入ったばかりで、あと一時間ほど経たないと起きてこないという。それまでのあいだ、庭の草むしりをしてくれないかと奥さんに頼まれた。菅野をはじめとする〈ミュータント・プロ〉のメンバーは、全員が奥さんとも顔なじみで、気軽にOKした。とりわけ菅野は、奥さんにも「菅{かん}ちゃん」と呼ばれるほどで、もう長いあいだ通い詰めていることが窺われた。
ぼくもすることがないので、菅野たちと一緒に芝生のあいだから顔を出している雑草をむしり取った。小さい頃から母と一緒に近所のお寺の草取りを手伝っていたので、これくらいの作業は苦にもならなかった。
三十分ほどで草取りを終えると、奥さんがお礼にと、昼食をご馳走してくれることになった。そば屋のメニューを手渡され、なんでも好きなものを頼んでいいというのだ。
ところが東京のそば屋のメニューときたら、カツ丼や天丼、親子丼といったドンブリものから、天ぷらにカレー、キツネにタヌキ、盛りに、かけに、ざる……と実に多彩。よく考えたら、ぼくは、そば屋に入った経験がなかった。
豊富なメニューに目がくらんでしまい、何を頼んでいいのか迷い、うろたえた。
ドンブリもののほかに、そばとうどんがある。天ぷらやカレー、キツネにタヌキあたりは、どんなものか知識があったが、どう考えてもわからないメニューがひとつだけあった。おかめうどん――である。ぼくの田舎では、こんなメニューを見たことがない。そこでぼくは好奇心を発揮し、おかめうどんを注文した。
先生の奥さんは、
「若いんだらから、もっとボリュームのあるカツ丼か親子丼にでもすれば?」
とおっしゃってくれたのだが、どうしても、おかめうどんの正体を確かめてみたかったのだ。
そば屋から届いたおかめうどんは、カマボコや伊達巻き玉子が載っているだけで、どこがおかめなのか、さっぱりわからなかった。かまぼこや玉子焼き、しっぽくで、おかめの顔が形づくられていることを知ったのは、ずっとあとになってからのことだ。
庭に面した居間で食事をご馳走になったあと、ぼくたちは先生の仕事部屋に向かった。菅野が勝手知ったる様子で案内してくれたのだ。
仕事部屋の隅に置かれたソファに座って先生の起きてくるのを待っていると、先に三人ほどのアシスタントが仕事部屋に入ってきた。菅野の小声の説明によると、アシスタントたちは、奥にある仮眠室でやすんでいたらしい。
アシスタントたちは、生あくびを噛み殺しながら、すぐに机の上に置かれていた原稿を手にとった。原稿には、人物にだけペンが入っている。人物のペンは、石森先生が入れたものだ。
アシスタントたちは、鉛筆で背景の下絵を描いてはペンを入れ、吸い取り紙がわりのトイレットペーパーを原稿の上に転がしていく。墨汁が乾く時間を短縮させるためらしい。アシスタントたちが、わずかの時間を惜しんでいる様子が、見学しているぼくにもビンビンと伝わってきた。
いつのまにか全身が熱くなっていた。生まれて初めてプロのマンガ家の仕事場を訪問し、アシスタントの仕事ぶりを目の当たりにしているのだ。その興奮と緊張に、身体が対応しきれていなかったらしい。
――もしかすると将来、ぼくもここで仕事することになるのかもしれない……。
そんな夢想に酔いながらアシスタントの手元を見つめていると、突然、玄関のチャイムが鳴った。
先生の机に一番ちかい席にいたアシスタントが、玄関に立っていくと、すぐに、
「サインください」
という元気な男の子の声が聞こえきた。近所の小学生がサインをもらいにきたのだ。
「ちょっと待ってね」
子供から色紙を預かってきたアシスタントは、自分の席にもどると、マジックインキを手にとった。
――え……?
ぼくは目を丸くした。それも当然だろう。アシスタントは、ぼくたちの見ている前で、下絵もなしにサラサラと『サイボーグ009』の絵を描きあげると、石森章太郎というサインまで入れてしまったのだ。
アシスタントは、その色紙を持って玄関に立っていった。
「はい」
アシスタントの声が聞こえ、男の子の嬉しそうな感謝の言葉が聞こえてきた。
子供が帰るとアシスタントは自分の席にもどり、何ごともなかったかのように仕事を再開した。
――これがプロのマンガ家の現実なのか……!
唖然としているぼくに、横から菅野が声をかけてきた。
「いまのがチーフの永井さんだよ」
いま『サイボーグ009』の色紙を描いて子供に渡したチーフアシスタントは、ほかのアシスタントよりも若そうに見えた。しかし、仕事の手は速く、さっさ、さっさと原稿を仕上げていく。しかも楽しげに背景のペン入れを進めていた。
チーフアシスタントのフルネームは、永井清。この一年ほど後に、『目明かしポリ吉』というギャグマンガでデビューするが、そのときのペンネームは、永井豪――となっていた。
投稿者 msugaya : 03:45 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月03日
■『仮面ライダー青春譜』 第1章 巨匠との遭遇(2)
●ペンの線がちがう!
「おっ、来てたのか」
石森章太郎先生が仕事場に姿を見せたのは、正午を少しまわった時刻だった。
「おはようございます」
菅野や細井たちは、すっかり顔なじみになっているようで、気軽に挨拶をかわしている。緊張しているのはぼくだけだった。
石森先生は、後年、パーマをかけた長髪がトレードマークになったが、この頃は、スポーツ刈りにちかい短髪だった。
「新しい会員の菅谷君です」
菅野に紹介され、あわててお辞儀したぼくは、スケッチブックに挟んできた色紙を差し出した。しかも二枚もだ。
「サ、サインしてください」
口のなかがカラカラに乾いているために、声がうまく出てこない。
「ちょっと待ってな」
石森先生は、色紙を受け取ると、仕事机に座り、墨汁をつけた筆でサラサラと『ジュン』を描き、『気ンなるあいつ★』のヒロインの絵を描いてくれた。
さらに持参した原稿を出しかけると、これからネームを入れに桜台駅ちかくまで出かけるので、そこで見てくれるという。ぼくたちは、石森先生のあとについて桜台駅までもどることになった。
石森先生が案内してくれたのは、桜台駅北口そばの小さな喫茶店だった。
ぼくたち五人は、先生とは別のテーブルについた。なんでも好きなものを注文するようにという先生の言葉に甘え、ぼくはオレンジジュースを注文した。緊張で喉が渇ききっていたからだ。
「じゃ、原稿を見せてごらん」
先生が、ぼくを向かいの席に呼んでくれた。
「お願いします」
ぼくは、カチンカチンに硬くなりながら、スケッチブックのあいだから取り出したマンガの原稿を取り出した。
マンガのタイトルは「シークレット・エィジェントマン」。題名どおりのスパイものだった。直前の冬休みに、〈ミュータント・プロ〉の新しい会誌用に描いたものだったが、その会誌は発行されずじまいとなり、宙に浮いてしまった原稿だった。
「ペンの線が汚いなあ……」
石森先生は、パラリと原稿を見るなり、眉間にシワを寄せていった。
自作マンガのペンの線が汚いことには、すでに気づいていた。といっても、その事実に気づいたのは、つい先ほど、石森先生の仕事部屋で、アシスタントが背景を描いている原稿を見たときのことだ。
生まれて初めてマンガのナマ原稿を見たぼくは、まさに度肝を抜かれていた。
ナマ原稿に引かれた線は、拡大サイズで描かれているにもかかわらず、細くきれいで、そして繊細だった。少年雑誌のザラ紙に印刷された線ばかり見ていたせいで、マンガの原稿が、こんなにもきれいな線で描かれているとは、想像さえもしていなかったのだ。
「ペンは少し使い古したくらいの方が使いやすい」
そんなことが書かれたマンガ入門書も多かった。ぼくは、それを真に受け、わざわざ使い古しのペンをもらってきては、マンガを描くのに使っていたのだ。
古いペンの仕入れ先は市役所だった。近所に住む市役所勤めの人に、使い古しのペンが欲しいと頼んでみると、山のように持ってきてくれたのだ。ボールペンもまだ普及していなかった頃で、役所の申請書類は、すべて、つけペンと青インクで書かれていた。
市役所でも、使い古しのペン先が大量に出るため、捨て場所に困っていたという。そんなときに、ぼくの申し出があったため、喜んで持ってきてくれたものらしい。
とはいえ使い古しのペン先は、先端がすり減り、変なクセがついていた。
貸本劇画誌で得た情報によれば、平田弘史氏は、市販のペン先の先端をペンチで切断し、グラインダーと砥石で整形したオリジナルのペン先を使っているという。そこでぼくも平田氏のマネをして、古いペン先を砥石で研いでは使っていたのだ。
もともとすり減ったペン先だから、引かれる線も当然のごとく太くなる。ザラ紙に印刷され、線が滲んだ状態のマンガしか見たことのないぼくは、ナマ原稿も同じような汚い線で描かれているものと思い込んでいたのである。
「菅野。お前の原稿を見せてやったら?」
石森先生が、菅野のスケッチブックに視線を向けながらいった。そこに原稿が挟まっていることをお見とおしだったらしい。
「はい」
菅野がニヤニヤと笑いながら、スケッチブックのあいだに挟まれていた原稿を取り出した。
菅野の原稿を見て、ぼくはショックを受けた。模造紙の原稿用紙に描かれていたのは、空母から発艦するジェット機の絵だった。ぼくもメカ好きだったので、その機体がグラマンA6「イントルーダー」だということは、すぐにわかった。当時、泥沼状態になっていたベトナム戦争でも使われていた二人乗りのジェット攻撃機だった。
攻撃機の機体のカーブは、まるで製図器具を使って引かれたかのようにシャープで、しかも背景の空気の流れまでもが、微細な線で描かれていた(菅野が工業専門学校の生徒で、マンガを描くのにドラフターという製図器具や、雲形定規まで活用していたことは後になって知った)。
昨年(一九六六年)の夏、「ボーイズライフ」(小学館)という男子向けティーン雑誌の読者欄で、マンガ研究会〈ミュータント・プロ〉の会員募集告知を見つけたぼくは、「名誉会長・石森章太郎」の文字に惹かれ、入会審査用のカットを二点描いて会長の菅野誠のところに送付した。
一点は旧海軍の局地戦闘機「雷電」、もう一点は、藤子不二雄タッチを真似たギャグマンガのキャラクターを描いたものだった。
一ヶ月もたたないうちに、送ったカットがもどってきた。同封された手紙には、「テクニックがなっていない。レタリングがヘタ」という酷評が書かれていた。会長の菅野が書いた文章だった。
小学生六年生のときに『マンガのかきかた』(手塚治虫・監修/秋田書店)を読んだのがきっかけで、ペンと墨汁を使ってマンガを描きはじめ、中学三年生のときに遭遇した『マンガ家入門』(石森章太郎/秋田書店)で、マンガ家になろうと決意して以来、ほとんど独学でマンガを描きつづけてきた。
同じ趣味を持つ友人もいたが、高校生になってまでマンガを描いているのは、ぼくだけになっていた。
ぼくのマンガを見た友人や近所の人たちは、誰もが「うまいなあ」と感心してくれた。おかげで自作マンガのレベルは、かなり高いところにあるのではないかと思い込むようになっていたのだ。
その自信が、菅野からの手紙で打ち砕かれてしまったのだ。いや、正直に告白すると、この段階では、酷評の手紙を送ってきた菅野のことを「ちょっとナマイキな奴」と考えていたところもあった。それは菅野の絵を見ていなかったし、プロのナマ原稿も目にしていなかったからである。
〈ミュータント・プロ〉には、いちど入会を断られたが、その後、補欠のようなかたちで入会を許され、この日の上京となったのだ。
ところが石森先生の仕事場でプロのナマ原稿を見て、またここで菅野の緻密な絵を見せられたことで、それまでの自信はガラガラと音を立てて崩れ落ちていた。いくらマンガがうまいつもりでいても、やはり井の中の蛙にすぎなかったのだ。
「描けば描くだけうまくなるから、あきらめずに頑張ンな」
ぼくの落ち込む様子を察したのか、石森先生は、そういって激励してくれた。
石森先生からは、五年後にも同じ言葉をかけられることになるのだが、このとき、そんなことがわかろうはずがない。ぼくたちは、先生のネーム入れの邪魔をしないよう、早々に喫茶店をあとにした。
投稿者 msugaya : 14:44 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月04日
■『仮面ライダー青春譜』 第1章 巨匠との遭遇(3)
●松本零士氏の不遇時代
喫茶店を出たぼくたちは、桜台駅で西武池袋線の電車に乗った。行き先は石神井公園。「しゃくじいこうえん」と読むらしい。桜台からは四つ先の駅だった。
石神井公園駅でバスに乗り、東映撮影所前で下車すると、撮影所の脇の細い道をまっすぐに北に向かって歩く。
次に訪問する松本零士先生のお宅は、あちこちに畑が広がる練馬区大泉学園町の一角に建っていた。
やはり新築の大きな家で、案内された応接間には暖炉まであった。
ソファに座って待っていると、上品でにこやかな笑みを浮かべた女性が、紅茶を運んできてくれた。エプロンをつけているが、お手伝いさんではなさそうだ。
紅茶の受け皿には、スプーンと一緒に、輪切りになったレモンが載っていた。このレモンが何をするものなのか、ぼくには見当がつかなかった。わが家でも紅茶を飲むことはあったが、入れるのは砂糖だけだったからだ。
「冷めないうちにどうぞ」
紅茶を出し終えた女性が、そう言い置いて応接間から出ていくと、ぼくの耳元で菅野がささやいた。
「牧先生だよ」
「え? もしかして松本先生の奥さんの牧美也子先生……?」
「そう」
菅野は、当然といった顔でうなずくと、紅茶が入ったカップのなかに、受け皿に添えられていた輪切りのレモンをスプーンに載せて入れた。
ぼくも見よう見まねでスプーンを使ってレモンをすくいあげた。この瞬間は、あの『マキの口笛』の作者でもある牧先生に会えた感激よりも、輪切りになったレモンを落とさないようにカップに入れることに必死になっていた。
紅茶にレモンを入れて飲む習慣があることを知ったのは、恥ずかしながら、このときが初めてだった。田舎育ちのぼくは、喫茶店というものに入ったこともなく、そのためレモンティーの存在も知らなかったのだ。
数分後、
「やあ、待たせてごめん」
といいながら松本先生が入ってきた。
正面のソファに腰をおろした先生は、ぼくの前のティーカップに目をとめた。
「早くレモンを出したほうがいいよ。紅茶の色が薄くなってしまうから」
その言葉に驚いて、両隣に座る菅野や細井たちのカップを見ると、いつのまにかレモンが出され、受け皿の上に置かれたスプーンの上に載っている。レモンを入れっぱなしにしていたのは、ぼくだけだった。ぼくは、あわててスプーンでレモンのサルベージ作業に取りかかった。
レモンを引きあげるのももどかしく、松本先生にもサインをお願いした。しかも、またも図々しく二枚の色紙を差し出したのだ。
「何がいいの?」
ぼくが出した色紙を手にして松本先生が訊いた。ぼくは、すかさず答えた。
「零戦をお願いします!」
「え?」
松本先生が、一瞬、目を丸くしたが、その顔は、すぐに微笑みに変った。どうやらこちらが年季の入った松本ファンであることに気づいてくださったらしい。
「長いあいだマンガ家をしてるけど、零戦を描いてほしいといわれたのは初めてだなあ……」
松本先生は、照れ笑いしながら青の硬質色鉛筆で色紙に当たりをとると、黒のマジックインクで下絵をなぞりはじめた。
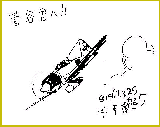 「最近、こういうマンガの注文が少なくなっちゃってねえ……」
「最近、こういうマンガの注文が少なくなっちゃってねえ……」
突然、松本先生の口調が寂しげなものに変わった。「注文が来るのは犬っころのマンガばかりなんだよなあ……」
当時の松本先生は、少年マンガは松本あきらのペンネームで執筆し、奥さまの牧美也子先生と少女マンガを合作するときのみ、松本零士の名前をつかっていた。少年マンガでは、『電光オズマ』『潜水艦スーパー99』『ララミー牧場』といったSFマンガやアクションマンガを描いていたが、ぼくが惹かれたのは、誰よりも精細なメカニズムの描写だった。
松本先生のメカは、潜水艦から拳銃に至るまで、どれもこれもがリアルで、しかもカッコよくデフォルメされていた。小学生のときに、そんな松本マンガのメカ描写にしびれたのが、自分でマンガを描きはじめるきっかけでもあったのだ。
とりわけ航空戦記マンガに描かれた零戦やグラマンの絵の精緻さは、他のマンガ家の追随を許さなかった。旧日本陸海軍の航空機については、元陸軍航空隊整備兵出身の、わちさんぺい氏の絵も素晴らしかったが、松本先生の絵は、それにスマートさが加わっていた。わちマンガのメカが、リアルではあっても、どこかのんびりとしているのに対し、松本マンガに登場するメカは、どこまでもスマートでクールだった。そこに新しさがあったのだ。
小学生のとき、松本先生の戦記マンガに遭遇したのがきっかけでマンガを描くようになったぼくにとって、色紙に零戦の絵を描いてもらうのは、悲願のひとつでもでもあった。
しかし、「冒険王」に連載されていた『潜水艦スーパー99』(一九六四~六五年)あたりを最後に、少年マンガからは遠ざかっていた。「犬っころのマンガ」と自嘲気味にいわれたのは、『その名はテス』などの松本零士名義で描かれた少女向けの動物マンガが仕事の中心になっていたからだろう。奥さまの牧美也子先生と合作した動物マンガも多かった。
「またメカの出てくるマンガを描けたらいいんだけどねえ……」
松本先生は、ブツブツとつぶやきながら二枚目の色紙には、犬っころならぬ子猫の絵を描いてくれた。少女雑誌では、子犬や子猫の登場する哀しいマンガが人気を集めていた頃で、松本先生も、その人気に便乗するような作品を描いていた。松本先生にとっては不遇の時代だったのだ。

松本先生が色紙を描き終わるのを待って、ぼくは自作マンガの原稿を取り出した。先ほど石森章太郎先生にも見てもらった原稿だ。石森先生には、時間がないこともあってペンタッチの批評しかしてもらえなかったが、松本先生は、鉛筆を取り出して、具体的なチェックをしてくれた。
最初に見たのは当然ながらトビラだった。そこには「シークレット・エィジエントマン」という恥ずかしいタイトルが描かれている。
「ほお、自分でタイトルまで書いているのか。でも、プロになると雑誌の編集部に詰めている版下屋さんが、タイトル文字をレタリングしてくれるから、自分で描く必要はなくなってしまうんだよ」
その言葉を聞いて、ぼくは隣にいる菅野の顔を盗み見た。去年、〈ミュータント・プロ〉に入会申し込みをしたとき、送ったカットの絵に「レタリングがなっていない」という酷評をしていたのが菅野だったからだ。
――プロになれば、レタリングの技術なんて必要なくなるんじゃないか……。
そんなことを考えながら菅野の顔を横目で見たのだが、松本先生は、まるでぼくの心中を見透かしたかのように、次のような言葉を発したのだった。
「でも、手塚先生も、タイトルは自分で描いてるだろ? 石森さんもそうだね。タイトルを版下屋さんにまかせるようになったのは、つい最近のことで、本来はマンガ家が描くべきものなんだよ。タイトルだって作品の一部なんだからね」
「は、はい……」
ぼくは背中に冷や汗が流れるのを感じながら小声で答えた。
松本先生は、その間も、ぼくのマンガを読み進めていた。
「飛行機は、もっとパースを極端にしたほうがカッコよくなるよ」
こんな構図の取り方まで、具体的に原稿に描き込んでくれるのだ。あまりにも感激したせいか、ぼくの記憶は、このあたりで途絶えてしまっている。どうやって辞去したのかも、まるで憶えていないのだ。
記憶がよみがえるのは、松本先生のお宅から徒歩で向かった久松文雄先生のお宅の玄関先だった。
※画像をポイントすると説明が表示されます。画像をクリックすると拡大画像が表示されます。
投稿者 msugaya : 21:34 | コメント (1) | トラックバック
2005年05月07日
■『仮面ライダー青春譜』 第1章 巨匠との遭遇(4)
●『スーパージェッター』の作者は、さわやか若大将
久松文雄先生のお宅は、松本先生のお宅から石神井公園駅方向にもどる途中にあった。
「少年サンデー」の一九六五年一月一日号で『スーパージェッター』の連載がはじまったときか、その前後の号で、作者の久松文雄先生の横顔が記事のページに掲載されていたことがある。新築されたばかりの自宅の庭で、鉄棒をしている久松先生の写真が載っていたが、年齢は二十一歳と紹介されていた。
玄関のチャイムを鳴らして待つと、すぐに久松先生がドアを開いてくれた。
久松先生は、二年前に二十一歳だったのだから、そのときは二十三歳だったはずだ。ともに昭和十三(一九三八)年一月二十五日生まれで、二十九歳の石森章太郎、松本零士両先生よりも、六歳ほど若いことになる。背も高く、鉄棒で鍛えているせいなのか、身体もがっちりしていて、さわやかなスポーツマンといった雰囲気だった。
「ぼくら」連載の『風のフジ丸』や「少年サンデー」連載の『スーパージェッター』で人気を博した久松先生は、いまは『冒険ガボテン島』を「少年サンデー」に連載しているところだった。
「やあ、ちょうどいいところに来てくれた。いま大ピンチなんだ。ちょっと仕上げを手伝ってよ」
これが久松先生の第一声だった。やはり菅野たちとは顔なじみのようで、声にも親しみがこもっている。
仕事部屋に案内されたぼくたちは、アシスタントの席らしい空いている机に向かうことになった。アシスタントは休みだったらしい。
「ごくろうさま」
仕事場の隅のソファに座っていたスーツ姿の男性が、声をかけてくれた。どうやら原稿待ちしている編集者のようだ。
先生から手渡されたのは、「たのしい幼稚園」(講談社)に連載中の幼年マンガ『キングコング』の原稿だった。二色のカラー原稿で、すでに背景のペン入れも終わり、先生が、絵の具で色を塗っている最中だった。
二色原稿なので、使う絵の具は朱色と茶色だけ。朱色を水で薄めて塗れば肌色になる。茶色はキングコングの毛むくじゃらの身体を塗るのに使われていた。
ぼくたちは手分けして、渡された原稿のベタを塗りはじめた。水彩絵の具で色を塗るため、原稿用紙には画用紙が使われていた。
キングコングが大海原を進む客船で暴れる話で、ぼくたちは、船の胴体や海の波にベタを塗っていった。ベタ塗りとは、ベッタリと濃い色で塗りつぶすことをいう。通常、ベタといえばスミベタのことで、ベタ塗りには墨汁が使われる。カラー原稿の場合は、アカ(赤)ベタ、アイ(藍)ベタ、キ(黄)ベタなどもある。
ぼくは緊張しながら机の上に載っていた筆を借り、墨汁をつけてベタを塗りはじめた。自作マンガの批評をしてもらうつもりだったのに、いきなりプロの原稿を手伝わされることになったのだ。
――ベタがはみ出したらどうしよう……?
そんなことを考えるだけで身体が硬くなり、腕が震えた。
それでも数ページの短いマンガだったせいで、五人で手分けするとベタ塗りは、すぐに終わった。
久松先生は、原稿をぼくたちに回すと、すでに別の仕事に取りかかっていた。『冒険ガボテン島』のキャラクター設定の仕事らしい。アニメの動画用紙に鉛筆でキャラクターを描いていく。まだ『キングコング』の原稿が終わらないうちに、アニメの製作会社の人がきて、キャラクターを描いた紙を受け取っていった。
すぐに久松先生は、ベタ塗りの終わった『キングコング』の原稿をチェックを開始した。右手にはホワイト用の小筆が握られている。
ホワイトとは、ペンの線やベタがはみ出したところを修正するための白のポスターカラーのことだ。ペン入れの段階から、はみ出しなどない状態で描かれていたため、ホワイトを入れる箇所も少なく、仕上げも五分ほどで完了した。
原稿を受け取った編集者が去ると、ようやく原稿を見てもらえることになった。いや、その前に色紙にサインをしてもらわなければ。とはいえ、仕事でお疲れの様子なので、ここでは色紙を一枚にとどめておいた。
リクエストは、もちろん『スーパージェッター』だ。「ぼくら」の『風のフジ丸』のときから久松文雄というマンガ家の名前は知っていたが、「少年サンデー」で連載がはじまったSFマンガの『スーパージェッター』は、絵がきれいなだけでなく、実に精緻で、すぐにファンになった。手塚治虫系の絵柄ではあったが、手塚マンガよりもキャラクターがスマートでカッコよかったのだ。
色紙にサインをもらうと、こんどは原稿を見てもらった。石森、松本両先生に見てもらった原稿だ。
「これじゃ構図に奥行きが感じられないね」
ぼくのマンガを見た久松先生は、松本先生と同じように鉛筆を持つと、ジャングルの木々を描き加えた。それも下からあおったアングルで、梢の部分が極端に小さくなっている。これだけで空間の奥行きと空の高さが感じられるようになった。
コマの枠線で登場人物の脚が切れているところは、人物の位置を上にずらすか、コマを下に伸ばして、足先まできっちりと描くようアドバイスされた。地面に立っていないと不安定になるからだという。いわれてみれば、確かにそのとおりだった。
ベタ塗りを手伝っていたおかげで、とうに窓の外は暗くなっていた。そろそろ夕食の時刻でもあるので、ぼくたちは先生のお宅を辞去することにした。
色紙と原稿へのアドバイスのお礼をいって、玄関から出ようとしたときである。
「ちょっと待って」
といって久松先生が、仕事部屋に引き返した。
すぐにもどってきた先生は、マンガの原稿と、それを入れるための大型封筒を手にしていた。
「わざわざ静岡から訪ねてくれたうえに、仕事の手伝いまでしてもらって悪かったね。お礼がわりに、この原稿を持っていって」
ぼくは目を丸くした。久松先生が手渡してくれたのは、『スーパージェッター』と『冒険ガボテン島』のあいだに「少年サンデー」に連載された『サンダーキッド』というマンガのナマ原稿だったからだ。ギリシア神話を下敷きにしたようなストーリーで、けっこう面白い作品だったが、『ガボテン島』の関係もあったのだろうか、連載は短期で終わっていた。
薄手の模造紙に描かれた原稿には、吹き出しの部分に写植まで貼られている。まぎれもなく正真正銘の雑誌用に描かれた原稿だった。
少年向けのストーリーマンガが新書判コミックスとして売られるようになったのは、この一年半ほど前からだった。少年週刊誌が六十円くらいだった時代に、新書判コミックスは二百円前後。小中学生には、おいそれとは手が出ない高額商品だった。当然、購買層は、小遣いにゆとりのある高校生以上になる。その分、著名なマンガ家の作品、あるいは名作と呼ばれるようなセレクトされた作品しかコミックスにはならない時代でもあった。マンガ雑誌に連載されたマンガが、なんでもかんでもコミックスになるのは一九七〇年代後半になってからのことだ。
「少年サンデー」に連載されたマンガも、自社ではコミックスにならず、秋田書店から刊行されることが多かった。といっても、それは『伊賀の影丸』や『サブマリン707』のような長期連載作品が中心で、短期連載作品がコミックスになることは皆無に近い状態だった。
つまり、大半の雑誌連載マンガは、いちど雑誌に掲載された時点で、その役割を終えたことになる。だから久松先生も気楽に原稿をプレゼントしてくれたのだろう。『サンダーキッド』は、平成に入ってから復刻されているが、雑誌かゲラ刷りから版を起こしたものにちがいない。少なくとも三ページの原稿は、ぼくがもらってしまったのだから。
すっかり暮れた大泉の住宅街を抜けて石神井公園駅まで歩くと、そこで菅野や細井たちと別れ、ひとりで東京駅に向かった。
西武池袋線の電車に乗り、座席についたぼくは、マンガ家の先生方にいただいた色紙と原稿を挟んだスケッチブックを抱え、ニンマリと微笑んでいた。
中学三年生の夏休みに石森章太郎先生の『マンガ家入門』を読んで以来、マンガ家になることを夢見てきたが、この日、マンガ家への距離が一挙に縮まったような気になった。
東京までは、鈍行電車でも片道三時間。いちど出かけてしまうと、東京も、もう、そんなに遠いところではなくなっていた。
投稿者 msugaya : 01:22 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月09日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(1)
●少年月刊誌の全盛時代
ぼくが生まれ育った静岡県富士市は、北に富士山、南に駿河湾を望む温暖な土地で、豊かな地下水を利用した製紙業が盛んな工業地帯でもあった。
昭和二十五(一九五〇)年生まれのぼくは、幼い頃から絵を描くのが好きで、幼稚園に入る前からマンガ雑誌を見ては、マンガの主人公たちの似顔絵などを描いていたらしい。
「うちの息子は、マンガで字を憶えた」と母がよく言っていたが、幼稚園の頃に読んでいたマンガの記憶は皆無にちかい。かろうじて『あんみつ姫』を読んだことだけを断片的に憶えている。
マンガそのものに興味を抱きはじめたのは、小学校に入ってからだった。
ぼくが小学校に入学した昭和三十一(一九五六)年頃は、月刊少年マンガ誌が子供たちの娯楽の王様で、本誌の厚さや別冊フロクの数を競う過激な競争がはじまっていた。
「少年」(光文社)、「少年クラブ」「ぼくら」(ともに講談社)、「幼年ブック」「おもしろブック」(ともに集英社)、「冒険王」「漫画王」(ともに秋田書店)、「少年画報」(少年画報社)、「痛快ブック」(芳文社)などが、太平洋戦争終結直後に生まれたベビーブーマー――いわゆる団塊の世代を読者として獲得するために、鎬{しのぎ}を削り合っていた頃だ。
この前年に連載がスタートした『鉄人28号』(横山光輝/「少年」連載)が、子供たちのあいだで人気になっていた。富士山麓の工業都市に住むぼくたちのあいだでは、同じ「少年」に連載中の『鉄腕アトム』よりも、圧倒的に人気が高かった。おそらく破壊性、暴力性が、『アトム』に勝っていたからだろう。小学一年生のとき、クラスメイトと一緒に、教室のうしろにある黒板に「鉄人27号」や「鉄人28号」の絵を描いては遊んだものだった。このとき一緒に「鉄人」の絵を描いていた金森俊昭は、のちに、ぼくがマンガ家を志望するきっかけをつくることになる。
「少年」には、『ナガシマくん』(わちさんぺい)、『ポテト大将』(板井レンタロー)、『ストップ兄ちゃん』(関谷ひさし)といった人気マンガがひしめいていた。
「少年画報」の人気マンガは、『赤胴鈴之助』(武内つなよし)、『まぼろし探偵』(桑田次郎)、『ビリーパック』(河島光広)など。
「冒険王」では、『イガグリくん』(福井英一/ありかわ旭一)や『ジャジャ馬くん』(関谷ひさし)に人気が集まっていた。
マンガを読むのは大好きだったが、小学五年生の頃までは、ぼくは、ただの読者であり、マンガを描くようなこともしなかった。
●テレビはなくても映画があった
ぼくが小学生だった昭和三十年代の大きなできごとといえば、やはりテレビの隆盛だろう。
しかし、昭和三十年代の前半は、テレビはまだまだ高価な電化製品で、近所の子供たちは、自動車修理工場の従業員休憩所に集まっては、『月光仮面』や『七色仮面』を見せてもらっていた。
小学校も学年が進むにつれて、テレビは加速度的な普及を遂げていくが、わが家にはテレビが入る気配もない。そんな経済的ゆとりは、どこを探してもなかったからだ。
父が自分で経営していた水道工事の会社を倒産させたのは、ぼくが三歳のときだった。父はどこかに姿を消したままで、ぼくは母と二人で暮らしていた。
父は、たまに帰ってくることもあったが、そのときは必ず泥酔状態だった。玄関に鍵がかかっているとガラス戸を蹴破って入ってくるため、鍵もかけられなかった。深夜、遠くから酔っぱらった父の怒鳴り声が聞こえてくると、ぼくは毛布を持って、近所の家に避難した。
母は、昼間は保険や化粧品の外交、夜は映画館で切符のもぎりと、働きづめに働いていた。それでも生活は苦しかった。
ぼくにとって運がよかったのは、母が映画館で働いていたことだった。顔パスで映画が見られたからである。日活作品が三本立てで上映される中央劇場という名の映画館で、ぼくは、毎週、土曜日になると、観客席に潜り込んではスクリーンを見つめていた。
石原裕次郎、小林旭、赤木圭一郎、宍戸錠たちが活躍した日活の黄金時代である。ぼくは、気にいった映画があると、平日でもかまわずに、学校の帰りにカバンを持ったまま、映画館に飛び込んだ。
小林旭と赤木圭一郎の映画がかかったときは、平日の学校帰りにも、ランドセルを背負ったまま映画館に寄り、客席の隅でスクリーンに見入っていた。
同年代の子供たちがテレビの『月光仮面』や『怪傑ハリマオ』や『七色仮面』に熱中していた頃、ぼくは映画館の闇の中で、石原裕次郎や小林旭が映画の中で唄う主題歌を一緒になって口ずさんでいた。
テレビも一家に一台の時代になりつつあった時代だが、ぼくの家にはテレビがなかった。テレビなど買える経済状況ではなかったのだ。わが家に中古のモノクロテレビが入るのは、東京オリンピックの翌年になってからだ。カラーテレビを買った親戚が、不要になったからとゆずってくれたものだった。
赤木圭一郎がゴーカートの事故で重体になったときは、ローカル紙に掲載された容態を伝える記事を食い入るように読んでは一喜一憂した。赤木圭一郎の死を知ったときは、まるで身内が死んでしまったかようなショックと悲しみに襲われたものだ。
赤木圭一郎が事故に遭ったときに撮影していたのは『激流に生きる男』という題名の映画だった。
女優のなかで好きだったのが石原裕次郎主演の文芸作品でヒロインを演じた芦川いずみだった。清楚で可憐で愛くるしくて、こんな人が姉さんにいたらなあ……なんてことを考えながらスクリーンを見つめていた。
母が勤める映画館の経営者は、隣の富士宮市にも映画館を持っていた。二軒の映画館は、上映時間をずらしただけの同じプログラムを組んでいた。こちらの映画館で上映が終わったフィルムをバイクで隣町の映画館に運び、あちらで上映の終わったフィルムをこちらの映画館に運んできて上映するのだ。おそらくフィルム代を節約するためだったのだろう。
ぼくも何度かフィルム運びを手伝ったことがあった。バイクの後部座席でフィルムケースを抱えては、隣町の映画館との間を一日に何度も往復するのだ。小学生のぼくにとっては、ちょっとした冒険旅行だった。
一九八九年公開の『ニューシネマ・パラダイス』というイタリア映画をテレビで見たとき、ふいに涙が込みあげて止まらなくなった。隣町の映画館との間でフィルム運びをするシーンが出てきたときのことだ。小学生のときに体験したフィルム運びの体験が、つい、画面のシーンに重なってしまったらしい。
映写室が遊び場になっていたのも、『ニューシネマ・パラダイス』と同じだった。映写技師のお兄さんとも顔なじみになり、成人映画を映写室の小窓から覗き見させてもらったこともある。もちろん母には内緒だったが、小学生には、そこで展開されているシーンの意味など理解できなかった。
市内で大映と松竹の作品を上映していた映画館が廃業すると、母が勤めていた映画館が、その代替上映をするようになった。日活作品に加え、大映と松竹の作品までもが見られるようになったのだ。勝新太郎の『座頭市』や『悪名』、そして市川雷蔵の『忍びの者』や『陸軍中野学校』のシリーズが好きで、同じ映画を何度も繰り返し見にいったものだ。とりわけ『忍びの者』は、学校帰りに劇場に飛び込んでは、七日間連続、計九回も見た。数が合わないのは土曜日と日曜日に二回ずつ見たせいだ。藤村志保の入浴シーンにドギマギしたのも懐かしい。
土曜日の夜は、ナイトショーという遅い時間の上映があった。終了時刻は午後十一時過ぎ。それから客席の掃除を手伝うのが週末の夜の日課になっていた。
まだ封が切られていないキャラメルやチョコレートも、よく落ちていた。暗がりで落としてあきらめたのだろう。ときどき小銭も落ちていて、これらは掃除を手伝うぼくの余録となった。
ぼくにはテレビはなくても映画があった。毎週三本ずつの映画が、顔パスで見られるのだ。家は貧しくても、あまり苦にせずにすんでいたのは、こんな貴重な体験をしていたからだろう。
父が戸板に載せられた状態で、あわただしく家に担ぎ込まれてきたのは、ぼくが小学5年生の真冬の朝のことだった。運び込んできた男性たちの話によると、凍てついた深いドブ川の中で倒れているのが、朝になって発見されたらしい。前夜のうちに酔っぱらってドブ川に落ち、頭のどこかを打って動けなくなっていたようだ。冷たいドブ川の水に浸かったまま一夜を明かした父は、この日以来、寝たきりの生活になった。
父がいなかった頃のほうが、家の中は平和だった。なんとかトイレには立てるようになった父は、身体が自由にならない苛立ちで、母やぼくに当たり散らす。身体が動かないのに酒を呑んでは暴れることもたびたびだった。
「あのまま死んでしまえばよかったのにねえ……」
「あのオヤジが死んだら町内で提灯行列を出してやるのに……」
近所の人たちが、息子のぼくに、面と向かってこんなことをいうほどに、酒乱で有名な父親だった。少し歩けるようになると、また外に酒を呑みに出ては大騒ぎを繰り返していた。近所の人たちもうんざりしていたのにちがいない。
父の面倒まで見なくてはならなくなった母は、ぼくが小学校を卒業した年に、調理師学校に入学した。手に職をつけないと、高収入が得られないからといって、母の実家の支援を受け、学校に入ったのだ。この頃には、せめてぼくを高校までは出してやりたい……というのが母の悲願になっていたらしい。
母は、昼は調理師学校に通い、夜は近所の割烹旅館で働くようになった。その旅館では、市内にある三軒の映画館すべてに、スライド広告を出していた。その関係で、毎週、映画館から招待状が届くのだが、旅館で働く人たちは、忙しくて映画など見にいっている暇がない。そこで招待券は、映画好きということになっていたぼくが、すべて独占させてもらえることになった。
おかげで母が映画館をやめても、映画館通いがつづけられることになった。それも毎週、三軒の映画館に行けるのだ。どの映画館も三本立てが基本である。毎週九本、年間四百本以上もの映画を見る生活が、高校を卒業するまでつづいたのだ。
上映される映画の大半は、プログラム・ピクチャーとも呼ばれた大衆向けの娯楽映画だった。
一九六〇年代後半、日活と大映は凋落の一途をたどっていたが、東映はヤクザ映画が好調で、東宝には特撮とクレージーキャッツと若大将のシリーズがあった。洋画では「007」をはじめとするスパイものや戦争映画、そしてフランスの暗黒街映画{フイルム・ノワール}に夢中になった。
映画に熱中した理由は別にもあった。母が割烹旅館で働きはじめたこともあって、学校から家に帰った後は、深夜まで父とふたりだけになってしまうのだ。
六畳二間だけの家で、父が寝ている奥の部屋とは障子で仕切られているだけだった。寝ているだけならいいのだが、始終、誰かをののしったり叫んだりしつづけているのだ。
父の声を聞いているのが耐えられず、夜になると、すぐに映画館に足を向けた。映画館に行ってスクリーンを見つめていれば、嫌なことを忘れることができたからである。
それでも映画館は三軒しかない。週のうち三日は映画館で時間をつぶせたが、残りの日は、別のことで気をまぎらわせる必要があった。
ぼくは、新しい気晴らしを見つけていた。
新しい気晴らし――それはマンガを描くことだった。小学六年生の終わりに描きはじめたマンガに、さらに熱を入れるようになったのだ。マンガを描いていれば、自分の作った物語の世界に没入できる。父の声も遠くで聞こえるだけになった。ぼくにとってマンガを描くことは、映画を見るのと同様に、現実逃避の行動でもあったのだ。
投稿者 msugaya : 22:02 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月19日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(2)
●「燃えろ南十字星」ショック
ぼくは小学五年生くらいから戦記画を描くことに夢中になっていた。ノートの落書きは、零戦やグラマンF6Fといった太平洋戦争時代の戦闘機ばかり。少年雑誌の戦記記事や戦記マンガと、プラモデルのブームに影響された結果だった。
戦記雑誌の「丸」から航空雑誌の「航空ファン」「航空情報」まで読みあさり、零戦や「隼」のスペックを頭のなかに叩き込んでいった。「丸」の通信販売で、零戦のナマ写真を買ったこともある。もちろん零戦を描くときの参考資料にするためだ。
憧れは、小松崎茂であり、その弟子の高荷義之だった。
高荷義之の絵は、師匠でもある小松崎茂の絵よりも精緻でスマートだった。とりわけドイツ陸軍の戦車がカッコよく、必死に真似したものだった。もっとも絵の具を使うまでには至らず、せいぜい色鉛筆を使ったくらいのものだったが。
マンガ雑誌「少年ブック」の表紙が高荷義之の絵に変わったのは、ぼくが小学五年生の終わりくらいだったろうか。ぼくは、乏しい小遣いを貯めては、毎月一冊か二冊のマンガ雑誌を買っていたが、高荷義之が表紙絵を描くようになってからは、「少年ブック」だけを買いつづけるようになった。
「おもしろブック」から誌名を変えた「少年ブック」には、『新選組』(手塚治虫)、『大平原児』(川崎のぼる)、『ゼロゼロ指令』(石森章太郎)といったマンガが連載されていた。
しかしぼくには、マンガよりも高荷義之の表紙の絵や、小松崎茂が講師をつとめる「戦記画教室」の方が重要だった。「戦記画教室」には、戦闘機の絵を描いては何度か応募したこともある。もっとも、入選したことはなかったが。
そのぼくが、マンガを描きはじめたのは、学校で配布されたPTA向け雑誌のページを開いたのがきっかけだった。
「母と生活」という保護者向け雑誌が、戦記マンガの特集を組んでいた。もちろん反戦の立場から、戦記マンガを批判する内容の記事だった。
その記事に、戦記マンガの一ページがカットとして添えられていた。題名は『燃えろ南十字星』というらしいが、作者の名前はわからない。
記事のカットに使われていたのは、霧のなかから戦艦「大和」が浮かびあがってくるシーンだった。そしてジャングルのなかを飛ぶ九六式艦上戦闘機が描かれたコマ。どちらもあまりにもリアルに描かれていて、ぼくは絶句した。
『ゼロ戦レッド』や『ゼロ戦太郎』など、戦記マンガの数は多かったが、兵器のリアルさ、精緻さは、PTA雑誌のカットに使われているマンガのほうが数倍も上だった。
PTA雑誌の記事によると、『燃えろ南十字星』は「日の丸」に連載されているらしい。そこに掲載されたカットにショックを受けたぼくは、このマンガが掲載された「日の丸」を求めて友人たちのあいだを駆けずりまわり、ようやく現物に対面した。
カットに使われていたのは、その年(一九六三年)の新年号に掲載された連載第一回の冒頭シーンだった。真珠湾攻撃に連合艦隊が出撃するシーンのあと、占領されたばかりのラバウルから、ストーリーの本編がはじまっていた。
『燃えろ南十字星』の作者は、松本あきらだった。現在の松本零士氏である。
それ以前から松本あきらのメカ描写には定評があった。『電光オズマ』や『ララミー牧場』でも、メカや拳銃の描写がカッコよくて、ビリビリとしびれたものだった。
テレビ映画が原作になった『ララミー牧場』でも、年代別に拳銃を描き分けていたし、シングルアクションとダブルアクションのちがいも描き分けられていた。シングルアクションの回転式拳銃{リボルバー}は、きちんと撃鉄を起こしてから引金が引かれていたのだ。
この当時、貸本劇画がリアルさを売りものにしていたが、ことメカ描写に関しては、松本あきらのマンガのほうが、五倍も十倍もリアルだった。
もっとすごいのは、その拳銃の発射音の描写だった。貸本劇画では「ガーン、ガーーン」という擬音がリアルだとされていたが、松本あきらの西部劇では、拳銃の発射音が「ドギュム、ドギュム」になるのだ。「ガーン」よりも「ドギュム」のほうが、どこかリアルに感じられたものだった。
『燃えろ南十字星』に描かれた零戦や紫電、グラマンといった航空機の描写も、これまでの戦記マンガにはないリアルさで、しかもカッコよく見えるデフォルメがなされていた。
『燃えろ南十字星』のメカ描写にショックを受けたぼくは、購読雑誌を「少年ブック」から「日の丸」に変更しようかと考えた。高荷義之が表紙を描く「少年ブック」をとるか、それとも『燃えろ南十字星』の「日の丸」をとるかで、ウーンと悩んでしまったのだ。高荷義之と松本あきらは、ぼくにとって甲乙つけがたい存在になっていた。
だが、その悩みは、あっというまに解消されることになる。『燃えろ南十字星』が連載されていた「日の丸」が突然休刊になり、連載マンガの何本かが、「少年ブック」で継続連載されることになったのだ。『燃えろ南十字星』も、移籍組のなかに入っていた。ぼくにとっては、まさにラッキー以外の何物でもない状態となった。
そして、ついにぼくは、『燃えろ南十字星』の影響で、戦記マンガを描くようになった。マンガなら、一枚絵とはちがって、コマ割りができる。零戦やグラマンの動きに連続性をもたせることができるのだ。この体験は新鮮で、たちまち数十ページのマンガを描き進めることになった。
といっても、この時点では、まだペンでマンガを描いていたわけではない。罫線の入ったノートにコマを割ってセリフを書き、絵を入れていたが、使っていたのは鉛筆だけ。実際のマンガがペンと墨汁で描かれていることも、まだ知らずにいた。
投稿者 msugaya : 22:31 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月24日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(3)
●「マンガのかきかた」
クラスメイトの大熊クンが、突然、自作のマンガを学校に持ってきたのは、小学六年生の終わり頃だった。
少年雑誌のフロクと同じB6サイズの紙に、数十ページのSFロボットマンガを描いたものだ。しかも墨汁をつけたペンで描かれ、色鉛筆で彩色された表紙までついていた。
「菅谷クンも絵が好きなんだから、マンガを描いてみたら?」
おっとりした性格の大熊クンは、そういって、秋田書店から発売されていた『マンガのかきかた』という手塚治虫監修のマンガ入門書を貸してくれた。
その本には、マンガはペンと墨汁で描くこと、失敗したところはホワイトという白のポスターカラーで修正すること、マンガを描くのは模造紙がいいこと。そして、実際に印刷されたものよりも二割拡大のサイズで描くことなどが、ていねいに説明されていた。
こんなにも本格的で実践的なマンガの入門書を読むのは初めてだった。なぜか、ぼくの家には、終戦直後に発行になったらしいボロボロの『漫画自習手本』というマンガ教本があったが、載っていたのは「ポパイ」や「ベティちゃん」の描き方ばかり。ストーリーマンガの描き方は解説されていなかった。
ところが秋田書店の『マンガのかきかた』には、ストーリーの作りの方法から、時間経過の描写法まで、マンガ製作の実際が、実に詳しく説明されていた。
ぼくは、『まんがのかきかた』を借りては返し、また借りてを繰り返しながら、ペン先を買い、墨汁やホワイトをそろえていった。さらに全紙大の模造紙を八等分したものに千枚通しで穴を開けて、B5判を二割拡大した原稿用紙を作りあげ、ついにマンガを描きはじめたのだ。
参考書となった『マンガのかきかた』は、何度、借りたかわからない。大熊クンもついにあきれはて、「そんなに熱心に読むんなら、その本、菅谷くんにあげるよ」ということになってしまったのだ。
こうして小学六年生の終わりから描きはじめたマンガの第一作目は、もちろん、零戦やグラマンが活躍する航空戦記マンガだった。
松本あきらの『燃えろ南十字星』に多大なる影響を受けたストーリーで、被弾して片脚が出なくなった一機の零戦が、ラバウル基地の滑走路に不時着するところからストーリーがはじまっていた。
不時着しようとした主人公の零戦の背後には、すでに危機が迫っていた。ロッキードP‐38「ライトニング」戦闘機が、ぴったりと後ろにつけていたのである。
一ページ描いては、次のページのストーリーを考えてコマ割りをし、鉛筆で下絵を入れては、ペンを入れてベタを塗る。その繰り返しでマンガを描きつづけていったが、いきあたりばったりだったせいで、八〇ページを過ぎてもストーリーが完結しなかった。撃墜王を競う仲間とともに敵に撃墜され、無人島に不時着した主人公が、戦争で人を殺してもいいのかどうかで論争をはじめたせいで、収拾がつかなくなってしまったのだ。
小学生の頭では、整理できない大きな命題に取り組んだのが敗因だった。ぼくは完結を断念した。
その結果、記念すべき処女作は、未完の大作のまま終わることになる。処女作の原稿を放り出したときには、もう中学生になっていた。
【生まれてはじめて描いたマンガ(12歳)】
(※画像をクリックすると大きな絵が別ウィンドウで表示されます)
投稿者 msugaya : 04:01 | コメント (0) | トラックバック
2005年05月25日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(4)
●週刊少年誌の時代--
ぼくが中学校に入学したのは、昭和三十八(一九六三)年の春だった。
中学生になるとクラブ活動がある。必ず何かのクラブ活動に参加しないといけないことになっていた。
最初、剣道部に入ったが、すぐに物理部に鞍替えした。アマチュア無線というものに興味を持ってしまったからである。
もともと機械いじりが好きで、ラジオでも時計でも、すぐに分解するクセのあったぼくは、近所でアマチュア無線をやっていた人の家に遊びにいくと、たちまち影響を受けた。ラジオ雑誌を借りてくると、そこに載っていた回路図をもとに、真空管を使ったワイヤレスマイクの組み立てに取りかかったのだ。部品は壊れたラジオをバラして取りはずしたものだった。
剣道部をやめて物理部に入りなおしたのは、実験室にある工具や計器を借りることができたからである。テスターのような計器は、中学生の小遣いでは買えなかった。
クズ屋さんからタダ同然で払い下げてもらった中古ラジオから部品をはずしては、アルミのシャシーの上に組み付けていく。マイクも高価で買えなかったため、明治製菓のマーブルチョコを代用にした。筒状のケースの底にクリスタルイヤホーンを入れ、口の部分をガーゼで覆ってマイクの代わりにしたのだ。マーブルチョコには、『鉄腕アトム』のシールがオマケについていたので、マンガ好きでもあったぼくには、一挙両得だった。こうしてぼくはラジオ少年に変身していった。ラジオをイヤホーンで聴くという習慣ができてからは、父の声も、さほど気にならなくなっていた。
ラジオ作りに熱中する時間が増えてはいたが、だからといってマンガ少年をやめたわけではなかった。
中学生になると学校給食がなくなり、弁当持参になった。しかし、夜、旅館で働いている母は、朝が遅くて弁当を作る時間がとれず、ぼくの昼食は、毎日パンになった。このパン代を節約して、ぼくは毎週「少年サンデー」と「少年マガジン」を購入するようになった。マンガ雑誌も、すでに週刊誌全盛の時代となっていた。
「少年サンデー」には『伊賀の影丸』(横山光輝)、『大空のちかい』(久里一平)があった。
「少年マガジン」では『ちかいの魔球』(原作・福本和也/マンガ・ちばてつや)が終了し、『紫電改のタカ』(ちばてつや)がはじまっていた。
月刊誌では「少年」で『サスケ』(白土三平)が人気を呼び、白土三平は「少年ブック」でも『真田剣流』という忍者マンガを連載し、「少年サンデー」には、『イシミツ』という不老不死の薬をテーマにしたオムニバスの忍者マンガを連載した。
月刊少年誌が最後の残り火を燃やしていた時代でもあった。戦記マンガと忍者マンガ--そして、野球マンガを中心にしたスポーツマンガ。これらが昭和三十八(一九六三)年前後の少年マンガ雑誌の状況だった。
さいわいにしてぼくは、家で勉強をしろといわれた記憶がない。宿題も家でやっていたのは、小学生のときまでだった。中学生になると宿題は、学校にいってから休み時間にやるものと決め、家ではラジオ作りとマンガ描きに明け暮れていた。
読む雑誌も増えていた。マンガ雑誌、戦記雑誌、航空雑誌に加え、ラジオ雑誌まで読むようになったのだ。
この頃の「初歩のラジオ」「子供の科学」(ともに誠文堂新光社)の読書投稿欄には、あきらかにマンガを描いていると思える達者なペンタッチのカットも載っていた。忠津陽子という名前の読者が投稿したマンガは、かわいらしい雪ダルマを描いたもので、年齢は十二歳となっていた。
●ラジオ少年と読書少年の日々--
中学二年生になると、ますますラジオ作りがエスカレートした。実際にハムをやっている教師が物理部の顧問になったのだ。
この教師の自宅に押し掛けて、高価だった水晶発振子を貸してもらったり、足りない部品を分けてもらったりもした。そうして作った送信機で電波を飛ばしては、無免許{アンカバー}の通信をしたのもこの頃だ。
この年――昭和三十九(一九六四)年の最も大きなできごとは、なんといっても東京オリンピックだった。その直前、新幹線も開通し、三波春夫の「東京五輪音頭」のテーマソングに乗って、日本中が沸いていた。
オリンピックのテレビ中継を授業でも見ることになり、電気に詳しいぼくが選抜されて、図書室にテレビを設置した。
クラブ活動とは別に、クラスごとに各種の学級委員が任命されていたが、ぼくは担任の教師から、強制的に図書委員に任命された。理由は、実に簡単だった。図書委員になりたい生徒がいなかったので、担任教師は図書室に出かけて貸し出しカードを抱えてくると、そのなかで一番たくさん本を借り出している生徒を調べはじめたのだ。
結果は、ぼくがダントツの一位だった。
マンガやラジオ雑誌以外の「普通の本」は学校の図書室で借りる。それがぼくの信条で、図書室の本を毎日のように借り出していた。それも小学校のときから愛読していた岩波少年少女文庫から、電気やラジオに関係する本までだ。
化学部の部員と鍵のかかった薬品室の窓をこじ開けては、硝酸、塩酸、硫酸、マグネシウムなどを持ち出し、王水や火薬もどきなどを作っていたが、そんな化学の知識も、すべて図書室の本から得たものだった。
アインシュタインの相対性理論の解説書まで読んでいた。理解できたかどうかは別問題だが、太陽風というものを目視できるのではないかと、スピーカーを鳴らすトランスをバラしてほぐした髪の毛のように細いエナメル線を、学校のグランドの端から端まで二〇〇メートルほども引っ張ったこともある。
そんな本の書名が羅列された図書の貸し出しカードを見て、ぼくを図書委員に任命した担任教師の一言がすごかった。
「おめえ、精神分裂症じゃねえの?」
体育の教師だったせいで、言葉も乱暴だったが、この言葉は、実に的確だったようにも思う。
マンガも描いていたが、戦争マンガだけでなく、ミステリーや冒険ものにも手を出すようになっていた。これも図書室で借りた本の影響だった。
『ツバメ号シリーズ』で知られるアーサー・ランサム、『エーミールと探偵たち』『飛ぶ教室』『ふたりのロッテ』などのエーリヒ・ケストナー、『名探偵カッレ君』のアストリッド・リンドグレーン、そして『怪盗ルパン』のモーリス・ルブランといった作品を集めた岩波少年少女文庫は、いちど小学生のときに読んでいたのに、中学生になっても読み返していた。
投稿者 msugaya : 06:24 | コメント (0) | トラックバック
2005年06月01日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(5)
●「ボーイズライフ」がやってきた
「ボーイズライフ」という革新的な少年雑誌が小学館から創刊されたのは、昭和三十八(一九六三)年のことだった。ぼくが中一のときのことだ。「中学生の友」という雑誌の休刊後、新たに中学生以上の男子向けに創刊された雑誌で、少しマニアックなマンガや記事が掲載されていた。
マンガでいえば『片目猿』(横山光輝)や白土三平の短篇オムニバス。大藪春彦のガンアクション小説やSFもあった。
この雑誌に、ショーン・コネリー主演の映画で人気の出ていた「007シリーズ」の一作『死ぬのは奴らだ』(イアン・フレミング原作/さいとう・たかを劇画)の連載が、突如として開始されたのは、東京オリンピックで明け暮れた一九六四年が終わる頃だった。
すでに貸本劇画の巨匠だったゴリラこと、さいとう・たかをが、本格的にメジャー雑誌に連載で登場した記念すべき作品でもあった(芳文社の大人向け漫画誌に作品を発表していたことはあったが、少年向け作品は、この直前に「少年サンデー」増刊号に掲載された『燃えろ忍びの森』という読み切り時代劇くらいしかなかったはずだ)。
「ボーイズライフ」の『007』は、さいとう・たかをの貸本劇画作品とは、あきらかにちがっていた。冒頭の高層ビル街の夜景が、すでに凝りに凝った精細なペン画になっていた。この絵を見ると、貸本劇画作品は、描き飛ばしていたとしか思えないほどだった。この『007シリーズ』なくしては、『ゴルゴ13』もなかったはずだとぼくは信じている。
「ボーイズライフ」には、長岡秀三というイラストレーターが、口絵のページで大活躍をつづけていた。空母「ミッドウェー」の透視図を描いた大判のポスターが、特別フロクについたこともある。
長岡秀三は、「ボーイズライフ」の仕事と並行して、「少年サンデー」の口絵や挿絵の仕事もこなしていた。戦艦「大和」や零戦の分解図や透視図が多かったが、これらの仕事をしていた頃の長岡秀三は、まだ武蔵野美術大学のデザイン科に在学する学生だったらしい。少年雑誌の口絵や挿絵の仕事は、学費を稼ぐためのアルバイトだったのだ。
このとき武蔵野美大で席を並べていたのが、後にマンガ家となって『同棲時代』などでヒットを飛ばす上村一夫だった。上村は、授業中に「少年サンデー」の口絵を描いている長岡に驚嘆していたという。
「少年ブック」の表紙を描いていた高荷義之のファンでもあったぼくは、同じように精緻な絵を描く長岡秀三のファンでもあった。
長岡秀三は、後にアメリカに渡り、カーペンターズやジェファーソン・スターシップのレコード・ジャケットを手がけて名をあげる。渡米後の名前は長岡秀星になっていた。
ここでは意識して「口絵」「挿絵」という言葉を使っているが、「イラスト」という言葉がポピュラーになるのは、もう少し後になる。「平凡パンチ」で大橋歩や柳生弦一郎などが人気者になってからだ。すでに、その兆しはあったのかもしれないが、少年雑誌の世界では、まだまだ「口絵」であり「挿絵」であった。
「ボーイズライフ」は、このようなビジュアル面だけでなく、読物にも力を入れていた。それまで、どこか日陰の作家のイメージがあり、「週刊アサヒ芸能」(徳間書店)の専属作家のような感さえあった大薮春彦が、ガンアクション小説の連載をつづけていた。また、いまをときめくSF作家たちが、外国人の名前でSF読物を書いていた。
ぼくは小学生の頃から、大薮春彦の隠れ愛読者でもあった。近所の友人の家に遊びにいくと、いつも「アサヒ芸能」が置かれていた。どうやら父親が購読していたものらしい。当時の田舎では「アサヒ芸能」は、完全なエロ本扱いだった(いまでも似た状態かもしれない)。子供が読んでいたら必ず怒られる雑誌でもあったが、ぼくは、毎週、この友人の家に遊びにいっては、こっそりと「アサヒ芸能」を開いていた。
目的は大薮春彦のガンアクション小説だった。性的な描写があったかどうかは記憶にない。拳銃やライフルの出てくるシーンばかりを拾い読みしていたからだろう。ルガーP‐08、ワルサーP‐38といった拳銃のスペックは、大藪小説を通じて憶えていった。
のちに小学館の編集者に聞くと、この「ボーイズライフ」の社内での位置づけは、〈早すぎた雑誌〉であったらしい。一部の好き者少年には評判のよかった「ボーイズライフ」も、一九六八年には休刊となったが、高校生以上にまで成長していたマンガ好きの読者のためには「ビッグコミック」を生み出し、記事とグラビア部門は、「GORO」を生み出す母胎となった。一九六八年の休刊直前に連載されていた大藪春彦の『血まみれの野獣』は、この年の暮れに東京府中で発生した三億円事件とストーリーがそっくりで、犯人が参考にしたのではないかともいわれていた。
「ボーイズライフ」を読んでいなかったら、ぼくもマンガ家にならなかったかもしれない。この雑誌の読書欄で見つけたマンガ同人誌の会員募集に応募したことが、マンガ家への足がかりとなったからである。
投稿者 msugaya : 00:14 | コメント (7) | トラックバック
2005年06月04日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(6)
●忍者マンガ
ぼくが小学生から中学生だった時代、少年ジャーナリズムの世界においては、忍者マンガと戦記マンガが二大ブームとなっていた。
忍者マンガといえば、第一人者は誰がなんといおうと白土三平だった。
「少年」の『サスケ』、「少年ブック」の『真田剣流』(第二部は『風魔』と改題)、そして「少年サンデー」にオムニバスで掲載された『イシミツ』などが、この時期の白土三平の代表作といっていいだろう。
なかでも人気の高かったのが、のちにアニメにもなる『サスケ』であった。このマンガに登場する「微塵がくれの術」の科学的(?)な解説は、ちょっぴり理科系少年でもあったぼくの胸をときめかせたものである。
白土マンガの忍術の解説は、その後の野球マンガにおける魔球の解説などと一脈通じるものがあった。
だが、魔球の解説は非科学的なものが多く、どう見てもこじつけとしか思えないものが大半だった。それに対し、『サスケ』の忍術解説は、まるで理科の教科書を読んでいるような錯覚を起こさせた。
なかでもよく憶えているのは、サスケが老婆とともに岩穴に閉じ込められたとき、老婆の着ていた綿入れの綿に、岩のあいだからにじみ出ていた天然の硝酸をかけて、火薬を作り出すシーンだった。サスケは、その方法で作った火薬を使って岩を砕き、洞窟からの脱出に成功するというストーリーだった。
ぼくは、中学二年生のとき、この火薬作りを試してみたことがある。
まず、化学部の部員だった同級生とふたりで、化学実験室に隣接した薬品保管室に忍び込み、硝酸をいただいてきた。この硝酸を綿の上にかけてみて、火薬ができるかどうかを実験したのだ。
「サスケ」のマンガでは、綿に硝酸をかけると黒い火薬の粉ができあがったのだが、ぼくたちの実験では、綿が硝酸を吸い込んだだけでおしまいだった。ほかに何の反応もない。
とにかく乾くのを待って、マッチで火をつけてみたが、ボッと少し勢いよく燃えただけだった。
「あのマンガは、インチキだ」
ということになったのだが、念のため、図書室にいって、化学の本をかたっぱしから開いてみた。
すると、硝酸をしみこませた綿は、「硝化綿」とか「硝化セルロース」と呼ばれ、無煙火薬の原料に使われるものであることが判明した。ノーベルのダイナマイトも、ここからはじまっていたのだ(実際の硝化綿は、硝酸と硫酸の混合物を綿に染み込ませて作る)。
しかも、そのまま火薬として使えるわけではないらしい。金槌で硝化綿を叩くと、音を立てて爆発するという。ぼくは、校舎の裏庭に硝化面を持ち出すと、石の上に載せてトンカチで叩いてみた。
パチン! と小さな音を立てて、硝化綿が、線香花火のような火花を飛ばしたが、それで終わりだった。
いくらマンガとはいえ、こんなことを実際に試す読者もいるのだ。マンガ家は気をつけなくてはいけない。
自分の体験から得た教訓も、実際にマンガ家になったときには、すっかり忘れていた。『ゲームセンターあらし』というテレビゲーム・マンガを描いたときに、主人公に「炎のコマ」という必殺技を使わせたのだが、その頃のテレビゲームに使われていたマイコンのCPUは、クロックが1メガヘルツくらいの遅いものばかり。ならば、スイッチで一秒間に百万回以上のオン、オフを繰り返せば、CPUがだまされて、ブロック崩しやインベーダーのゲームで大勝をおさめることができるはず――と考えたのだ。むろん、消える魔球と同様のヘリクツである。
一秒間にテレビゲームのレバーを100万回も動かすために、摩擦によってレバーが熱を持ち、炎を吹き出してしまう--という設定になっていたのだが、このバカバカしさが子供たちの人気を呼んだ。
ただ人気になったのだったら問題はない。ところが、たくさんの子供たちが街のゲームセンターで「炎のコマ」を試してしまったのだ。ゲームマシンのレバーを壊したり、勢いあまって手を怪我した子供もいたらしい。そんな投書をたくさんもらったぼくは、あらためて中学生時代の危ない実験のことを思い出したのだった。
●戦記マンガが少年雑誌のハシラだった
忍者マンガと並んで、この頃、人気があったのが戦記マンガである。一応、どんな戦記マンガがあったか、列挙してみよう。
■「少年サンデー」
◎『大空のちかい』(久里一平)
陸軍加藤隼戦闘隊に所属する少年パイロットを主人公にしたマンガ。戦闘機である隼の編隊が飛ぶシーンには、「加藤隼戦闘隊」の歌の歌詞が書かれていた。作者の久里一平は、アニメ・プロダクション「竜の子プロ」の創立者吉田竜夫(個人)の実弟。
◎『あかつき戦闘隊』(相良俊輔・原作/園田光慶・マンガ)
『大空のちかい』の後、しばらくしてからはじまった戦記マンガ。貸本劇画時代は、ありかわ栄一の名前で活躍していた園田光慶が、「少年画報」「少年キング」などの雑誌で活躍した後、「サンデー」に本格進出した記念すべき作品でもある。
海軍の零戦パイロットが、任地である太平洋の孤島に零戦で赴くと、いきなり、ならず者たちの集まりである味方から銃撃を受けるというファーストシーンは、なぜか日活で石原裕次郎が主演した『零戦黒雲一家』の冒頭と同じだった。ぼくは『零戦黒雲一家』を母が勤めていた映画館で、七日間連続で見ていたため、こんなことまで気になったりもした。
■「少年マガジン」
◎『紫電改のタカ』(ちばてつや)
出てくる戦闘機が、みんなブリキ細工みたいに見えて、ちょっと情けなかった。しかし、ストーリーでは、さすがに「笑いと涙」のちばてつや。最終回では、誰もが泣いた。
ぼくが中学二年生頃だっただろうか、ちばてつやが「紫電改のタカ」を描くところがNHKのテレビで放映されたことがある。ちばてつやが実際にペン入れをするのは、顔の中身と輪郭だけで、あとはアシスタントまかせだったのを見てびっくりした。しかも、そこでアシスタントをしていたのは、大阪の日の丸文庫で活躍していたはずの政岡としや(稔也)と梅本さちおだった。
政岡としやは、その後、青年劇画誌「コミックVAN」で戦記マンガを描いたりもしたが、そのときのメカは、実にカッコよく描かれていた。
梅本さちおは、まもなく「少年マガジン」の増刊号などに読み切りマンガを発表し、やがて創刊される「少年ジャンプ」(はじめは隔週だった)に『くじら大吾』という身体のでっかい少年が主人公のマンガを連載する。つづいて「少年キング」に連載した『アパッチ野球軍』(花登筺・原作)がアニメ化されてヒット。その後も『リトルの団ちゃん』(「月刊少年チャンピオン」連載)などで活躍するが、一九九三年、五十歳で死去。ぼくが知り合ったのは一九八〇年前後だが、その頃には、マンガも描かなくなりつつあった。
■「少年キング」
◎『忍者部隊月光』(吉田竜夫)
テレビにもなった、あまりにも有名な忍者+戦記マンガ。マンガでは太平洋戦争が舞台になっていたが、水木譲主演のテレビ版では、現代を舞台にしたスパイ+忍者モノになっていた。
吉田竜夫は、アニメ・プロダクション「竜の子プロ」を設立し、「少年ブック」に連載していた『宇宙エース』をテレビアニメ化する。このアニメは、カネボウハリスがスポンサーになっていたが、その後、カネボウハリスは、同じ吉田竜夫の柔道マンガ『ハリス無段』、ちばてつやの『ハリスの旋風』などのタイアップ作品を次々と手がけるようになる。
■「少年ブック」
◎『燃えろ南十字星』(松本あきら)
この作品については本文で触れたので省略するが、同じ「少年ブック」では、望月三起也が、戦記マンガの読み切りシリーズを、別冊フロクで描いていた。
■その他
◎『虎の子兵曹長』(わちさんぺい)
元、陸軍航空隊整備兵の経歴を持つ『ナガシマくん』のわちさんぺいが描いた航空戦記マンガ。東南アジアを舞台にしていた。絵は、もともとがギャグマンガ家なので、線なども簡単だったが、その省略された線で描く隼などの戦闘機がリアルだった。また、石油タンクの爆発、火薬による爆発などの煙の描きわけをきちんとしており、さすが経験者はちがうと妙に納得したものだ。
「隼」が機体を傾けるときは、必ず「クラッ」という擬音が入っていた。現在、航空戦記小説を書く筆者が、小説中で戦闘機が傾くとき、つい「クラッ」という擬音を使ってしまうのは、このマンガの影響によるものである。
投稿者 msugaya : 01:45 | コメント (2) | トラックバック
2005年06月10日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(7)
●もう一人の「影丸」――貸本劇画の時代
「おい、菅谷。いくらたくさん雑誌のマンガを読んでたって、『影丸』を知らないようじゃマンガ好きとはいえないぞ」
中学二年生のとき、休み時間にKというクラスメイトがぼくに声をかけてきた。
「影丸って、『伊賀の影丸』じゃなくて?」
「ちがう、ちがう。白土三平の『忍者武芸帳』の主人公さ。首を切られても生きてるすごい忍者なんだ」
「白土三平って、そんなマンガも描いてたの? 雑誌では見たことがないけどなあ」
「雑誌じゃなくて貸本屋で借りてくる単行本だってば。初めてのときは、生徒手帳を預けて借りる仕組みになってるんだ」
「へええ……」
ぼくは、その話を聞いて、初めて貸本屋というところに足を向けた。それまでさんざんマンガを読んでいながら、貸本屋には縁がなかった。市内に貸本屋は二、三軒あったが、歩いていけるのは一軒だけ。あとは自転車が必要なほど遠かった。
商店街のあいだに、ひっそりと埋もれていた一軒の貸本屋に出かけると、書棚には、それまで目にしたことのないようなマンガの本がズラリと並んでいた。
焼きソバ店や理容店の待合室にも、業者が定期的に運んでくる貸本店向けのマンガ本が並んでいたが、そこにあるのは手垢にまみれた古い本ばかりだった。掲載されているマンガも、少年雑誌に載っているものに比べると、ずっと泥臭く、また、ヘタクソに見えた。そんなこともあって、貸本店向けのマンガや劇画には、いまひとつ興味が持てずにいたのだ。
貸本屋に入ってはみたが、最初に本を借りるときに生徒手帳を預けなければいけないという。学校では、ときどき抜打ちの持ち物検査があり、生徒手帳を持っていないと、立たされたりもする。しかも、その貸本屋にやってくる客は、チンピラ風の若者や水商売風の男女ばかり。ヤバイところのような気がして、早々に退散してきたのだった。
翌日、Kにそのことを話すと、生徒手帳を預けなくても本を借りられる貸本店を教えてくれた。
その貸本店は、東海道本線の駅を挟んだ反対側にあった。中学校の学区も異なる地域だったため、そんなところに貸本屋があることも知らなかった。
ここでは、店番をしている初老のおばさんが、生徒手帳で住所と名前を確認するだけで、あとは何もいわずに本を貸してくれた。
最初に借りたのは『忍者武芸帳』ではなかった。人気があるせいなのか、店内には見当たらなかったからである。
ぼくは、さいとう・たかをの『台風五郎』シリーズを二冊ほど借りてきた。子供の頃に見ていた日活アクション映画に似た雰囲気に惹かれたからである。
それまでにも、焼きそば店や理容店で、さいとう・たかをの作品を読んではいたが、その大半は、「ゴリラ・マガジン」や「刑事」といった短篇劇画集に掲載された短編ばかりだった。
『台風五郎』を読んだぼくは、少年マンガ雑誌にはない貸本劇画の迫力に打ちのめされ、これがきっかけで、貸本屋に通い詰めることになる。
佐藤まさあきは、絵は好きではなかったが、暗いムードとストーリーに魅せられた。
『忍者武芸帳』は、その後も、なかなか借りるチャンスに恵まれず、まとめて読むのは、小学館で文庫が出てからのことになる。『忍者武芸帳』を熱心に読もうと思わなかったのは、「サスケ」などの少年マンガと比べると、絵が荒々しく、ちょっと見には雑に見えたからだ。さいとう・たかをの絵が、迫力ある荒さで描かれているのは許せるが、雑誌の丁寧な絵を見慣れていた白土三平の方は、その荒さが、手抜きのように思えてしまったのだ。読者というのは、本当に勝手なものである。
投稿者 msugaya : 04:01 | コメント (0) | トラックバック
2005年06月22日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(8)
●「劇画」と「マンガ」
焼きそば店や理容店で貸本店向けの単行本を読んでいたせいで、貸本店向けのマンガが「劇画」と呼ばれていることは、だいぶ前から知っていた。
もっとも、当時(一九六〇年代前半)、この「劇画」という名称を知っていたのは、貸本店のユーザーくらいのものだったろう。
「劇画」という言葉が、雑誌でも一般化してくるのは、その後、相次いで創刊された青年コミックス誌に、貸本屋向け劇画家たちが大挙登場してくるようになってからである。
「ガロ」に連載していたマンガ家の作品をも「劇画」と呼称する評論家もいたが、白土三平、水木しげる、つげ義春といった「ガロ」系のマンガ家が、みずから「劇画家」と称した事実はない。
ぼくは、おそまきながら貸本屋の単行本を読みふけるようになり、そこにあった古い単行本を読みながら、劇画の歴史をさかのぼっていった。
「劇画」という呼称を使いだしたのは、関西を拠点にしていた貸本向けのマンガ作家たちだった。辰巳ヨシヒロ、松本昌彦、山森ススム、さいとう・たかを、佐藤まさあき、といった作家たちが「劇画工房」という組織を作り、それまでのマンガと表現方法において一線を画すという意味合いから、「劇画」という呼称を使いだしたのが最初だったはずだ。
ぼくが読んだ古い劇画短編集のなかに、辰巳ヨシヒロによる「劇画とマンガのちがい」についての解説があったのを憶えている。その内容は、次のようなものだった。
マンガ=パーン、パーン
劇画=ガーン、ガーン
◎自動車の走り方:
マンガ=スピード感を出すために、自動車の車体が宙に浮く。
劇画=リアルさを追求するため車体は宙に浮かない。
◎登場登場人物が何かに気づいたとき:
マンガ=頭のまわりに点々を描く。
劇画=頭のまわりに激しいフラッシュを描く。
ここで辰巳ヨシヒロが説明していたのは、いかに劇画がリアルな表現方法を使っているかだった。
しかし、ぼくは、すでに松本あきらの洗礼を受けていた。マンガにだってリアルなものがあることを知っていたから、辰巳の説明には納得できなかった記憶がある。
後年、ぼくが漫画家としてアシスタントを使うようになってからのことだが、若いアシスタントたちが、マンガ独特の記号的な表現法をまるで知らないという事実を知って、愕然としたことがある。
びっくりしたときに汗が飛んだり、緊張したときに頬を汗が流れ落ちたり、ヒントが浮かぶと頭の上に電球が灯ったり。頭にランプが灯るキャラクターだっていた。
作者と読者のあいだで暗黙のうちに決められていたはずの記号的表現が、すっかり影をひそめ、忘れ去られていたのだ。アニメでスタートし、その後マンガに入ってくるマンガ家志望者が多いことも、マンガ表現に特有の約束ごとに関心をはらわなくなる原因となっていたようだった。
創世期の劇画は、大阪の日の丸文庫という出版社から発行されていた「影」や「魔像」といった短編集に多く掲載されていた。しかし、ぼくは、日の丸文庫の作品や作家は、あまり好きになれなかった。実際に発表されたときよりも、少し遅れて貸本劇画に接したせいか、古さばかりに目がついてしまったからである。
この頃、日の丸文庫で活躍していたのは、影丸譲也、山本まさはる、みやはら啓一、梅本さちお、水島新司など。時代劇では平田弘史、石川フミヤスたちが、「魔像」を中心に、短編を描いていた。
梅本さちお、水島新司、山本まさはるなどは、「オッス」という現代もののホームドラマ的な生活マンガをよく描いていた。水島新司は、テレビ番組の「番頭はんと丁稚どん」をマンガ化してもいたはずだ。
自ら劇画家を名乗った作家たちとちがい、日の丸文庫系のマンガ家の作品には、庶民の生活を描いたものが多かった。
ぼくは、日の丸文庫系のマンガ家の作品が、どうも苦手だったが、それは、藤山寛美の松竹新喜劇や花登筺などの大阪大衆演劇の臭いが感じられたせいかもしれない。ぼくは、もっとスマートでカッコいい劇画やマンガ――そう、日活アクション映画のような作品が好きだったのだ。
投稿者 msugaya : 15:47 | コメント (2) | トラックバック
2005年06月29日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(9)
●新人の登龍門「街」
同じ頃、名古屋ではセントラル出版という出版社が、「街」という短編集を出し、「影」と人気を張り合っていた。ここで活躍していたのは、出崎統、荒木伸吾といった都会派アクションを描くマンガ家たちだった(彼らも、劇画という呼称は使っていなかったはずなので、ここではマンガ家と呼ぶことにする)。
出崎統は、バラリと前髪がたれたハンサムな若者が、グリスガンという進駐軍払い下げのマシンガンをぶっぱなすマンガばかり描いていた。
ムーディーな青春マンガが得意だった荒木伸吾は、キャラクターの瞳の中に少女マンガのような十字の光を描いていた。
出崎も荒木も、貸本劇画、貸本マンガの衰退とともに、いつしか姿を消してしまったが、やがて虫プロ製アニメのクレジットに、その名前を見るようになる。
出崎統は『悟空の大冒険』で演出をつとめ、「COM」の創刊号からは『悟空の大冒険』のマンガを連載した。荒木伸吾も、いくつかのアニメ作品の中で名前を見つけたが、虫プロには、ほかにも「街」出身者がいた。もりまさき――のちの真崎守である。
もりまさきが「街」の新人賞を受賞したのは昭和三十五(一九六〇)年のことだった。
「街」では月例で新人賞を発表していたが、もりは、一度に二作が入選し、その二作が同時掲載されるという破格の扱いでデビューした。
一作は「雨の白い平行線」というタイトルで、薄幸の少女が列車に飛び込み自殺するという暗い話だった。その絵も、斜線が多用された暗いムードで、そのペンの黒い斜線のかけ合わせの上に、さらにホワイトの細い線がかけ合わされた独特の暗いとしかいいようのないムードを持った作品だった。
もう一作は「暗い静かな夜」という題名で、やはり同じようなムードを持った短篇だった。
余談だが、後年、マンガ専門の編集プロで編集の仕事をやったとき、真崎守氏に電話でデビュー作についてのインタビューをする機会があった。
真崎氏は、デビュー作として、六〇年代の終わりに青年コミック誌に掲載した殺し屋を主人公とした作品の名をあげたのだが、ぼくが、『燃えてすっ飛べ!』(一九六五年/東京トップ社)や「雨の白い平行線」の名前を出すと、「なんで、そんな作品まで知ってるの!」と驚いて、しぶしぶながらも「雨の白い平行線」の名前をデビュー作として雑誌に載せることを了承してくれた。
それもこれも中学生のときに焼きそば屋で読んだ「雨の白い平行線」の印象が強かったからである。高校生になってから東京トップ社の短篇劇画集「刑事」で、もりまさきが永島慎二と共著で『燃えてすっ飛べ!』を上梓しているのを知り、あわてて東京トップ社に購入の申し込みをしたこともあった。この本は、いまも残っているが、おまけでついてきたナマ原稿は消息不明のままだ。
「街」では、ほかにも多くのマンガ家が誕生した。宮脇心太郎、吉元正、五十嵐幸吉、のちに「ガロ」でナンセンスマンガを描き出す星川てっぷも、本名で新人賞に入選していたはずだ。
吉元正は、その後、横山まさみちのアシスタントとなり、横山まさみちプロ(通称「よこみちプロ」)から「鉄火野郎シリーズ」などを発表。やがて絵柄をガラリと変えて、青年コミック誌の「漫画ストーリー」や「漫画アクション」(ともに双葉社)に登場する。ペンネームはバロン吉元に変わっていた。
「街」をはじめとする貸本店向け単行本の多くは、さいとう・たかをを中心としたアクション劇画に押され、次第に姿を消していった。
短期で姿を消した「宝島」という短編集があった。永島慎二、石川球太、つげ義春、コンタロー(「一生懸命ハジメくん」のコンタロウではない)、深井ヒローなどが、だるまプロという名前で出していた貸本店向けの短編集だ。だるまプロは、武蔵野マンガプロダクションという若手マンガ家のグループが前身のグループだったはずだ。つげ義春の作品も載っていたが、後の「ガロ」の時代とは、まるで異なる作風だった。
とくに印象に残っているのがコンタローだ。少年雑誌の別冊フロクにも、少年探偵がメッサーシュミットという三輪自動車に乗って、開きかけた開閉式の勝鬨橋を飛び越えるマンガなどを描いていた。
スマートな絵柄で好きだったのだが、すぐに単行本でも雑誌でも見かけなくなった……と思ったら、いつのまにかイラストレーターへの転進をはかっていた。筒井康隆氏の小説の装幀を手がけるなど、幻想的な作風で知られる杉村篤氏がその人だ。
同じ「宝島」にマンガを描いていた深井ヒローも、その後、深井国と名前を変えてイラストレーターとなり、現在も活躍をつづけている。
「宝島」の読者欄には、後に『風のフジ丸』や『スーパージェッター』、『冒険ガボテン島』などで活躍する久松文雄が「マンガ家になりたい」という手紙を寄せていた。年齢は十二歳か十三歳で、住所は新潟になっていた。国鉄の官舎だったような記憶がある。久松文雄が「漫画王」に投稿したマンガでデビューするのは、この直後のこと。たしか十四歳、中学二年生だったはずだ。
投稿者 msugaya : 21:52 | コメント (0) | トラックバック
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(10)
●貸本劇画健在なり
昭和三十年代に隆盛をみた貸本店向けの短編劇画集は、昭和四十年代に入ると、「少年サンデー」「少年マガジン」「少年キング」といった少年週刊誌の台頭やテレビの普及によって、ドミノ倒しのようにバタバタと倒れ、次々に休刊していった。
大阪を中心に活動していた劇画家の多くは、活動拠点を東京に移し、しばらくのあいだは貸本屋向けの単行本でがんばっていた。
さいとう・たかをは、さいとうプロを設立し、佐藤まさあきも同じく佐藤プロを設立する。それぞれが、自分のプロダクションから劇画の単行本を出版するようになっていた。おそらく、このあたりが、「みずから自分たちの描く作品を劇画と読んだ」作家たちの貸本劇画時代における黄金期ではなかっただろうか。
同じ頃、さいとうプロや佐藤プロの躍進ぶりに刺激されてか、ほかの貸本劇画作家たちも、自身のプロダクションを設立し、単行本を出版するようになっていた。横山まさみちの横みちプロも、そんな劇画家が出版も手がけるプロダクションのひとつだった。
これら劇画家プロダクションからは、新しい勢力として、アシスタント出身の劇画家が登場しはじめていた。
さいとうプロの短編集「ゴリラマガジン」では、以前は「魔像」などに時代劇をよく描いていた石川フミヤス、さいとうのアシスタント出身の武本サブローなどが短編を描いていた。石川フミヤスは、別に長編の青春劇画シリーズなども描いていた。
そして、さいとう・たかを自身は、「ボーイズライフ」の『007シリーズ』を描くかたわら、『台風五郎』シリーズなどのヒット作品を描きつづけていた。
佐藤まさあきが一貫して描きつづけていたのが『影男シリーズ』だ。また、三洋社(後の青林堂)から出ていた短編集「ハードボイルド・マガジン」の責任編集などもやっていたこともある。佐藤は、この三洋社から『黒い傷痕のブルース』というハードボイルド系の作品も出している。
佐藤まさあきのアシスタントからは、後年、松森正が「COM」からデビューすることになるが、面白いのは、これら劇画家たちのアシスタントの多くが、貸本屋向け単行本の読者欄に設けられた似顔絵投稿欄の常連だったことだ。
松森正(熊本県)も投稿欄の常連だったし、後に南波健二のアシスタントになる永安{ながやす}巧(熊本県)や安達{あだち}勉・充の兄弟(群馬県伊勢崎市)も、毎月のように貸本劇画の投書欄をにぎわせていた。
安達兄弟はメチャクチャに絵がうまく、静岡の片田舎で貸本劇画の読書欄をながめていたぼくは、彼らのことを「群馬の天才兄弟」と呼んでいた。
とりわけ弟の安達充は、名前が同じで、しかも同年齢ということもあって、妙に気になる存在でもあった。
兄の安達勉は、その後、赤塚不二夫のアシスタントになり、あだち勉としてデビューする(二〇〇四年に亡くなった)。
弟の安達充は高校生のときに「COM」の新人賞に佳作入選した後、石井いさみのアシスタントを経て、マンガ家として独立する。ペンネームは、あだち充だった。
(一九八三年に、あだち充氏と一緒に小学館漫画賞を受賞したぼくは、控え室で初対面となったのだが、憧れの人に会ったような気分になってドギマギしてしまい、まともに言葉も交わすことができなかった)
昭和四十年代に入ると廃業する貸本屋も増えはじめ、貸本劇画業界全体が、急坂を転がり落ちるような勢いで滅びへの道を突き進んでいく。
そんななかにあって、貸本の最後の残り火のように輝いて見えたのが、東京トップ社という貸本劇画の出版社だった。
短編集では「刑事」があった。昭和四十四(一九六九)年頃まで出版され、通巻は四十六号くらいまで行っていたはずだ。
ここには、巨匠のさいとう・たかをや、影丸譲也、永島慎二たちが作品を寄せていた。
永島慎二の代表作のひとつ『漫画家残酷物語』も「刑事」に発表されたシリーズだった。『貧乏なマルタン』『漫画家とその弟子』など、アクション劇画誌には似つかわしくない作品を描いていたが、中学生のぼくには、まだ、ピンときていなかった。ピンと来て、あらためてシビレるのは高校に入ってからである。
長編では、ありかわ栄一改め園田光慶が、ひとり飛び抜けてきれいな絵を描いていた。
絵がきれいな分だけ雑誌への登場も早かった。「少年キング」に連載した柔道ものの『車大助』や、「少年画報」に連載した探偵マンガの『ホームラン探偵局』など、貸本劇画出身者とは思えない清潔感のある絵とシャープな描線が、マニア(ぼくのことだ)をうならせていた。
園田は、貸本劇画家だった時代に、「座頭市」の現代版ともいえる盲目の殺し屋を主人公にした『完全紳士』でヒットを飛ばしていた。コートをめくると、そこに殺しの武器がズラリと納められていて、実にカッコいい劇画だった。
『ホームラン探偵局』の雑誌連載と同時期(一九六四年頃)、東京トップ社から出したのが『アイアンマッスル』のシリーズである。園田は、『アイアンマッスル』を発表することで、まさに劇画界の革命児となった。
ラフなタッチの絵が多かった貸本劇画の世界に、かっちりとしたきれいな線を持ち込んだだけでなく、アクションシーンの人物にも、アメコミの影響によるものとおぼしき極端な遠近処理をほどこしていた。構図に奥行きをもたらし、同時に、定規の線で人物の顔や身体に影を加えることにより、さらなる立体感を出していた。
格闘シーンでは、雲形定規を使ったかのようなきれいに揃った曲線を多用し、動きのスピード感と激しさを表現した。
主人公に殴られる悪党たちは、顔を変形させながら血しぶきを噴出させていた。その表情があまりにも痛そうで、殴られる悪人にちょっぴり同情したこともある。
貸本劇画を読みはじめていたぼくも、すぐさま『アイアンマッスル』の絵柄をマネしてみたが、デッサン力の問題で、すぐに断念した。
園田が開発した技法をマネたのは、ぼくのようなアマチュアだけではなかった。多くの同業者が、次々と園田の構図やペンタッチを採り入れていったのだ。川崎のぼると南波健二のふたりが、もっとも影響を受けていたのではなかろうか。
貸本劇画家のなかで、いちはやく雑誌進出を果たした園田だったが、『あかつき戦闘隊』の頃には、多くの追随者を生んだ貸本劇画時代の絵柄を捨て去っていた。『あかつき戦闘隊』は、それまでの園田の絵を知っている者にとっては、まるで別人の作品に見えたものだ。
園田は、『あかつき戦闘隊』のあとに手がけた『ターゲット』になると、さらに絵柄が変わっていた。
天才肌の半面、飽きっぽい一面もあったのか、園田は、「少年キング」連載の『赤き血のイレブン』(梶原一騎・原作)を途中で投げ出すと、『三国史』などの歴史劇画でカムバックするまで、しばらく沈黙してしまう。
園田の影響を受けた劇画家のなかでは、川崎のぼるが最初に雑誌の世界で活躍を開始した。「少年ブック」の『大平原児』や『スカイヤーズ5』、「少年サンデー」の『アタック拳』や『タイガー66』からはじまり、後の『アニマル1』や『巨人の星』に至るまで、メジャー路線を歩みつづけていく。だが、『スカイヤーズ5』や『タイガー66』の頃の川崎の絵は、あきらかに園田の絵柄の面影を残している。
南波健二は、テレビの『コンバット』に影響された戦争劇画が得意だった。彼も、園田光慶に影響されたのか、絵が洗練されていき、やがて、少年誌に登場するようになる。
東京トップ社で異色の存在だったのが旭丘光志だった。『渡り鳥シリーズ』というギターを背負った青年が主人公の作品(どこから見ても小林旭の「渡り鳥シリーズ」だった)と、「社会派劇画シリーズ」と呼ばれる実際の冤罪事件などをモデルにした実録性の強い作品を交互に描いていた。後者のタイプは、のちに「少年マガジン」などで社会派劇画として話題になる作品群の原点でもあった。
のちに編集プロに勤務し、旭丘光志氏の社会派劇画が特集された「少年マガジン」増刊号の編集を担当したとき、東武東上線沿線にお住まいだった旭丘氏のお宅まで、原稿を受け取りにいったことがある。
そのとき、生意気にも、旭丘氏に、こんな質問をした。
「東京トップ社では、社会派劇画と『渡り鳥』シリーズを交互に描いてらっしゃいましたが、どうしてなんですか?」
旭丘氏の作品は、高校生のときに、ほぼ読んでいたが、東京トップ社から刊行された作品のなかでは、どうみても社会派劇画のほうに力が入っていると思えたからである。
「社会派の方は売れ行きが悪くてね、『渡り鳥』を描かないと出させてもらえなかったんだよ」
旭丘氏は、あっさりと予想どおりの回答をしてくださったものだ。
ジリ貧になりつつも残っていた貸本向け単行本も、「ビッグコミック」(小学館)、「ヤングコミック」(少年画報社)をはじめとする青年コミック誌の登場で、その存在価値を失い、バタバタと消えていく。昭和四十三~四十四(一九六九~七〇)年頃のことだ。
お得意さんになっていた貸本屋の一軒が廃業するときは、お店のオバサンが、「これまでのお礼に、一冊好きな本をあげるよ」と言い出した。毎日のように通い詰め、仕入れの相談にも乗るようになっていたせいだ。ぼくは考えあぐねたすえに、白土三平の『シートン動物記・灰色熊の伝記』をゆずってもらうことにした。一九六三年に『サスケ』とともに講談社児童漫画賞を受賞した作品で、動物や自然の描写が、どのコマも一幅の絵になりそうなほどの素晴らしい作品だ。ぼくは『シートン動物記』を自分のマンガの教科書にするつもりだった(画力の問題で、マネをするのは断念したが……)。
白土三平は、貸本向けマンガ家の一方の雄でもあったが、ぼくが中学二年生の頃に創刊された「ガロ」を除けば、メジャー少年誌が活動の中心で、書き下ろしの貸本店向け作品は読めなくなっていた。
ぼくは、貸本系の作品では、どちらかというと都会派のアクション劇画が好きだった。泥臭い感じのする作風のマンガや劇画は、どうしても好きになれなかったのだ。
そのなかで別格だったのが水木しげるだった。
ぼくの分類では、泥臭い絵のマンガ家に入っていたのだが、水木の作品には、幼い頃に好きだった杉浦茂や前谷惟光の作品に似た雰囲気があった。怪奇マンガが多かったが、ホワンホワンとしたノンキなムードが漂っていて、ページを開くと、つい引き込まれてしまうのだ。
とりわけ好きだったのが『墓場の鬼太郎』シリーズである。最初に一冊だけ読んでみたら、あまりにもおもしろくて、『鬼太郎』シリーズの原点でもある『鬼太郎夜話』までさかのぼって読んでしまったほどだった。
コマのなかに描かれた電柱に、「どっちつかずの民社党」と書かれた張り紙が描かれていたのも『鬼太郎夜話』だったのではないか。困ったことにこのコマが、ぼくの柔軟な脳細胞に民社党のイメージを刷り込ませてしまったのだ。それから四十年が過ぎたいまでも、街で民社党の流れを組む民主党のポスターを見かけるたび、自然に「どっちつかずの民社党」というフレーズが浮かんでくる。マンガの影響というのは実に恐ろしいものである。
白土三平の『カムイ伝』や水木しげるの短篇が載っていた月刊雑誌「ガロ」(青林堂)は、発行部数が少なかったのだろう、田舎の書店では売られておらず、現物にお目にかかるのは、中学三年生になってからだった。
ぼくの生まれた静岡県富士市という街は、製紙の街として有名で、市内には多数の製紙会社があった。本州製紙(現・王子製紙)や大昭和製紙といった大工場の敷地には、国鉄東海道本線から分岐線が引き込まれ、貨車で古雑誌や古本が運び込まれていた。いずれも再生紙の原料となる古紙としてだった。
広大な工場の敷地内には、ゴムの防水シートをかけられた古紙の山がつらなっていた。二階建ての家よりも高く、学校の校舎よりも長い古紙の山が、はるか彼方までつづいているのだ。その山のなかに、「ガロ」をはじめとする珍しい雑誌が埋もれているのを教えてくれたのは、父親が製紙工場に勤めている金森俊昭というマンガ好きの同級生だった。
ぼくと金森は、日曜日の人が少ない時間を見計らって製紙工場の鉄丈網を破り、工場の敷地内に侵入した。
手には軍手、背中にはナップザックという泥棒スタイルである。目標は、もちろん古雑誌と古本の山だった。
雨よけの黒いゴムシートをはがしては、なかの古紙の山から、目ぼしい雑誌や古書を引っ張り出すのだ。「ガロ」や「鉄腕アトムクラブ」など、地元の書店では手に入らない雑誌も発見し、ぼくたちは狂喜した。
獲物は背中のナップザックに詰め込んで脱出したのだが、ときには警備員に見つかってしまうこともあった。
何度も見つかるうちに、そんなにマンガが好きならと、警備員のおじさんが正門から入れてくれるようになった。もちろん相棒の金森の父親が、その工場に勤務しているのを知ってのうえのことだ。学校の校庭が十も二十も入りそうなほどに広い敷地いっぱいに、古雑誌や古書が積まれているため、警備員のおじさんも、ナップザック一杯くらいならかまわないと思ったのだろう。
「ガロ」はユニークな雑誌だった。白土三平の「カムイ伝」が連載されたのは、途中の号からだったが、それまで貸本でお馴染みだった水木しげるや諏訪栄(小島剛夕)が読み切りマンガを描いていた。新人の作品が多いのも特徴だった。
初期の新人には星川てっぷがいる。セントラル出版の「街」でデビューした当初はシリアスなマンガを描いていたが、「ガロ」ではナンセンスマンガを描いていた。星川てっぷのペンネームを使うようになったのも「ガロ」になってからだ。
その後、つりたくにこ、という名の変わったギャグマンガを描く女性が新人賞に入選し(最初は確かSFマンガだった)、やがて同誌で活躍するようになる。絵は雑だったが、ふしぎなおかしさが漂う作品だった。「少女フレンド」にも名前を変えて作品を発表していたはずだ。
つげ義春の「沼」という作品が出てきたのは、ぼくが中学三年生頃ではなかったか。
「ガロ」には、マニア心をくすぐるような作品も多かったが、その泥臭さと暗さが、あまり好きにはなれなかった。自分でマンガを描くようになった後も、お手本は、松本あきら(零士)、手塚治虫、久松文雄、小沢さとる、石森章太郎といった〈きれいな絵〉を描く人たちだったからだ。
貸本劇画に影響されて、劇画風の絵も練習したが、こちらのお手本は、さいとう・たかをであり、園田光慶だった。どちらもバタ臭さが売り物の劇画だった。
白土三平の作品も、少年雑誌に掲載されるきれいな線で描かれたものは好きだったが、荒々しいタッチで描かれる『忍者武芸帳』や『カムイ伝』には、いまひとつ食指が伸びなかった。のちに多くのマンガ評論家が絶賛する「ガロ」の思想性も、中学生のぼくにとっては、大した意味をもっていなかったのだ。
ちなみに「劇画」という呼称を「ガロ」系のマンガ家の作品にも与えたのは、美術評論家だった石子順造氏であった。一九六〇年代末のことである。
「ガロ」系のマンガ家たちは、みずからの作品を「劇画」と呼んだことなどなかったのに、評論家が、自分の都合で勝手に劇画にしてしまったのだ。貸本屋に通って「劇画工房」出身の〈自称劇画家〉たちの作品を愛読していたぼくは、劇画家を自称していないマンガ家まで劇画家にしてしまった評論家の文章を読んで、悲憤慷慨したものだった。
投稿者 msugaya : 21:55 | コメント (0) | トラックバック
2005年07月05日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(11)
●「マンガ家入門」ショック--
 |
 |
マンガを描いていたぼくに、一大転機が訪れるのは、昭和四十(一九六五)年八月のことである。
中学生最後の夏休みも終わりに近づいた頃、ぼくは、突然高熱を発し、激しい嘔吐と下痢で寝込むことになった。
小学生の頃までのぼくは、学年が変わるたび、四〇度ちかい高熱を発し、嘔吐と下痢を繰り返しては学校を休んでいた。
子供の頃からかかりつけだった医院の医師は、精神的なものが原因だと診断した。母親が神経質なほどにきれい好きで、整理整頓にも口やかましく、それが親や教師の顔色を窺っては気をつかう性格にさせてしまったのだという。熱を出したり嘔吐したりするのも、神経を過敏にしているのが原因だというのだ。
「息子を殺したくなかったら、うるさくいうのはやめなさい」
医師は、母にこうアドバイスしたという。
そこで母は、自分の性格をおさえて、ガミガミいうのをやめることにした。
それまできちんと整理されていた机のまわりや本箱は、根がズボラだったせいなのだろう、たちまち散らかり放題になった。ところが不思議なもので、それ以来、年度替わりに担任教師が替わっても、熱を出さなくなってしまったのだ。医師の診断はまちがっていなかったことになる。
高熱と嘔吐の症状が、突然、再発したのは、一九六五年の八月、中学三年の夏休みが終わろうとしている頃だった。
この頃のぼくは、家の経済的事情も考え、高校に行くこともあきらめていた。母は必死に働いていたが、過労が原因で寝込むことも多くなっていた。
わが家の経済状況を知っている近所の人たちが、ぼくの就職先の心配をしてくれるようになったのも、この頃からだった。定時制の高校に通わせてくれるシステムがあるからと、東芝の工場や電電公社(現NTT)の電話局に口をきいてくれるという人もいた。中卒での就職は、すでに皆無にちかくなっていた頃でもあった。
ぼくは、高校に行くことをあきらめてはいたのだが、どこかに忸怩{じくじ}たる思いもあった。困ったことに、成績だけはトップクラスを維持していたからだ。宿題も家でやったことがなく、登校後、休み時間にすませていた。中間、期末の試験勉強もしたことがなかったのに、なぜか、いつも上位の成績を取っていた。
トップクラスの成績を維持できたのは、おそらく父親ゆずりの記憶力があったからだろう。
ぼくの父は、飲んだくれだったくせに、いちど電話をかけた先の電話番号は、メモも取らずに記憶した。母と夫婦喧嘩したときも、二十年も前の母の言動を引き合いにして、文句をいっていた。それも昭和○年○月○日の午後×時×分頃――といった具合に、日時まで特定するのだ。もちろん母は、二十年も前のことなど忘れ去っている。そんな昔のことを蒸し返されても困ってしまうのだが、父は、そんな些末なことまで夫婦喧嘩のネタにする嫌なヤツだった。
父親が、自分の記憶力をもとに、昔の母の失敗をなじる光景を見ては、あんな大人の男にはなりたくない――と思っていたのだが、ハッと気づけば、このぼくも、いちど電話をかけるだけで、指が番号を記憶してしまうようになっていた。そんなところだけは父の遺伝子を受け継いでしまったらしく、数字やデータ類を記憶する力だけは、バツグンに良かったのだ。落語の寿限夢だけでなく、東海道本線・山陽本線の全駅名も、小学生の頃には暗唱できたほどだった。中学生になってからは、テレビ映画『逃亡者』のナレーションまで暗記した。
当時のテストは、科挙の登用試験のように、暗記力が勝負の分かれ目となる問題が多かった。当然、記憶力が成績向上にもつながることになる。塾にもいかず宿題もやらず、もちろん試験勉強もしないのに、それでも上位の成績を維持できたのは、父親ゆずりの暗記力、記憶力のおかげだったのだ。
高校進学は断念していたつもりでも、周囲の誰もが目の色を変えて、高校受験のための勉強に取り組みはじめたのを見ているうちに、なぜ俺だけが高校に行けないんだ――というみじめな思いに取りつかれるようにもなっていた。
そして、その思いは、父に対する怨嗟にもなった。
――この父さえいなければ、ぼくと母は、もっと楽な暮らしができたはずなのだ。
そう思い込むようになってしまったのだ。
父は、身体が不自由なのに、夜になると酒を飲みに出かけては、酔っぱらって帰ることが多くなっていた。深夜、遠くから聞こえてくる怒鳴り声を聞くと、反射的に殺意を抱いたものだった。
父に何かいわれるたび、「うるさい!」と怒鳴り返し、「お前なんか死んじまえ!」と喚くようにもなっていた。遅ればせの反抗期にも入っていたらしい。
とりわけ夏休みは、家にいる時間が長くなる。父親と接する時間も多くなる分、当たり散らす回数も増えることになってしまうのだ。そのくせ、半身不随の父親を怒鳴りつける自分が情けなくなり、自己嫌悪におちいる日々がつづいていた。
四〇度の高熱を発し、激しい嘔吐と下痢で寝込んでしまったのは、あと十日ほどで夏休みが終わろうとしている頃だった。二学期がはじまって学校に行けば、毎日、高校受験の話題にさらされる。そのことが気になって、また身体がパニックを起こしてしまったのかもしれない。いまなら、登校拒否とか自閉症など呼ばれる症状の一歩手前だったのだろう。しかし、そんな気のきいた病名など、まだ聞いたこともない時代だった。
そんなとき、製紙工場がマンガ雑誌の宝の山だということを教えてくれた金森俊昭が、ぼくの家にやってきた。ぼくが寝込んで三日目くらいのときのことだ。
「おい、いま本屋にいったら、石森章太郎の『マンガ家入門』という本があったぞ」
金森が、いきなり早口でまくしたてた。
「えっ、ど、どんな本?」
ぼくは、布団の上に起きあがって訊いた。もちろんパジャマ姿のままだ。
「パラパラめくっただけだから、よくわからないけど、一ページごとにコマ割りのしかたなんかが説明してあってさ。『マンガのかきかた』よりも、ずっと詳しく説明されているんだ」
「いくらだった?」
「三百二十円。早く買いにいかないと、誰かに買われちまうぞ。じゃあな」
金森は、そういって玄関から出ていった。
ぼくは、もう、いても立ってもいられなくなっていた。なんとか布団から抜け出すと、ふらつく足で家の外に出た。洗濯物を干していた母に、お金を貸してほしいと頼むためだ。
「なんの本?」
母が訊いた。
「マンガの参考書」
「学校の参考書なんかまちがっても買うわけがないものね」
母は、アハハハと笑って財布から五百円札を出してくれた。
パジャマ姿だったぼくは、なんとか着替えをすると、家の外に置いてあったオンボロ自転車にまたがった。この数日、重湯{おもゆ}だけしか口にしていなかったので、自転車のペダルを漕ぐ足にも力が入らない。まるで雲の上を走っているような感じだった。
夏の太陽が頭のてっぺんから照りつけて、ぼんやりしている頭をよけいにクラクラさせる。商店街のアーケードの柱に自転車を立てかけて、夏の日差しのなかから薄暗い本屋の店内に飛び込むと、突然、目の前が真っ暗になった。明るい屋外から暗い店内に、あわてて飛び込んだせいだ。
目が慣れるまでにしばらく時間がかかり、ようやく本棚が見えるようになってきた。店のなかには、店員がひとりいるだけだった。
田舎の町では、真夏の昼下がりに本屋にやってくるような物好きはいない。もちろん、この頃の本屋には、冷房などという気のきいたものも入ってはいなかった。店内には、熱気と湿気が籠もっていた。
ぼくは、金森に教えられていた児童書の書棚にふらつく足を向けた。
『マンガ家入門』は、すぐに見つかった。
箱入りの豪華本だ。用心しながら箱からセロファンのかかった本体を出し、そっとページを開いてみる。
最初に見たのは奥付の部分だった。初版の発行は一九六五年八月十五日になっていた。定価は三百二十円。発行所は「マンガのかきかた」と同じ秋田書店だ。正式タイトルは、『少年のためのマンガ家入門』となっていた。
ぼくは『マンガ家入門』を買うと、急いで家にもどった。
家に着くと、包装紙を開くのももどかしく本を取り出し、胸をドキドキさせながら、石森章太郎作品のキャラクターが描かれた表紙をめくった。
見返しには、石森章太郎作品のキャラクターがちりばめられていた。サイボーグ009がいる。ミュータント・サブがいる。となりのタマゲ太くんもいる。そして、かつて熱中して読んだ『怪傑ハリマオ』や『少年同盟』の主人公たちもいた。
扉の絵は、二色で描かれたマンガ家の机の上の絵だ。ペンがあり墨汁があり、鉛筆とホワイトがある。カラスグチもあった。筆立てには、彩色用の筆といっしょに羽根ぼうきも入っていた。
カラー口絵は、本文の中でテクニックが解説されている『龍神沼』の絵だ。その下には、四色オフセット印刷と、三色印刷の色の塗り方の解説がされていた。
四色オフセット--こんな言葉を目にするのもはじめてだった。
■まえがき
第1部 入門編
■第一章 おさらい
●一、道具
●二、かき方
●三、発表方法
■第二章 自己紹介(マンガ家への道)
●マンガファン
●投稿時代
●デビュー
●マンガ家生活
●スランプ
●現在
第2部 テクニック編
■第一章 ギャグマンガ
●どろんこ作戦
■第二章 ストーリーマンガ
●龍神沼
■第三章 その他のマンガ
(1)幼年マンガ・絵本
(2)一コマ・カット
(3)4コマ
(4)パノラマ
(5)その他のその他
第3部 総集編
●マンガ家きのう・きょう・あす
●マンガ家と健康
●マンガ賞
●児童マンガ家になるための10の条件
■あとがき
これが「マンガ家入門」の目次である。
ぼくは、外が暗くなったのも気づかずに、『マンガ家入門』をむさぼり読んでいた。
なかでも夢中になって読んだのは、石森章太郎の半自叙伝ともいえる第2章の「自己紹介(マンガ家への道)」だった。
そこには、中学生時代から投稿をはじめ、高校生時代には手塚治虫にもアシスタントを依頼され、そのうえにマンガ家としてもデビューしたという石森章太郎の経歴が書かれていた。
上京した後の貧乏物語、トキワ荘の生活など、マンガを描くのが好きな田舎の少年の琴線をかき鳴らすには充分な内容が、これでもかというくらいに書きつらねられていたのだ。
『マンガ家入門』は、マンガ入門書であると同時に、石森章太郎というマンガ家ができるまでの〈青春物語〉でもあったのだ。
――マンガ家になりたい……!
『マンガ家入門』を読み終わったときには、ぼくの心の奥底に、ほのかな希望の光が生まれていた。
この頃、同じことを考えていたのは、ぼくだけではなかった。『マンガ家入門』を読んだ日本中のマンガ少年、マンガ少女が、やはりマンガ家になる夢で、胸をはち切れんばかりにふくらませていたのだ。
全国のマンガ少年、マンガ少女にとって、『マンガ家入門』は、『資本論』や『毛沢東語録』よりも熱い〈魂の書〉でもあったのだ。
投稿者 msugaya : 18:25 | コメント (3) | トラックバック
2005年07月25日
■『仮面ライダー青春譜』第2章 紙の街に生まれて(12)
●マンガ家になりたい!
『マンガ家入門』を読んで、再びマンガに取り組むことになったのだが、以前ほどにはスラスラと描けなくなっていた。本文で解説されていたテクニックの数々に翻弄され、消化しきれずにいたからだ。
中学最後の夏休みは、あっというまに終わり、誰もが高校受験のことで頭がいっぱいになる二学期になった。
教室では志望校やすべり止めに受ける私立高校の話題が飛び交っていたが、ぼくは、ひとりマンガのアイデアを練り、コマ割りを進めていた。
――二学期中にマンガを描き上げ、石森章太郎「先生」のところに送るのだ。「弟子かアシスタントにしてください」という手紙を添えて……。
どうせ、高校にいけないのなら、好きなことを職業にしたかった。マンガを描いて石森章太郎先生のところに送れば、きっと道はひらけるはずだ。ぼくは大まじめに、そう考えていた。
石森先生のところに中途半端な作品を送ったら失礼になる。きちんとストーリーを完結させたものを送るのだ。そのためには、最後までコンテを作ってから作画にとりかかる必要があった。
そんなことよりも、石森先生の弟子になることが最優先の課題だった。高校受験も、すべり止めでしかなくなっていた。
同級生たちが受験勉強にはげんでいる間も、必死にマンガを描きつづけたほくは、冬休みに入ってラストスパートをかけ、年明け早々に、ようやく原稿を完成させた。三二ページのSFマンガだった。
ぼくは完成した原稿と弟子入り志願の手紙、そして、母に書いてもらった弟子入りの同意書を大判の封筒に入れ、祈るような気持ちで近所の郵便局から発送した。
宛先の住所は、東京都新宿区弁天町四十三。宛名は、もちろん石森章太郎先生だ。
毎日、毎日、首を長くして返事を待った。しかし、二週間たっても三週間たっても返事はない。
「やっぱりだめだったんだよ」
一ヶ月ほどが過ぎたとき、母が無情にいった。現実を思い知らせようとしたのにちがいない。
「しかたないから、高校にいくんだね。いまどき、マンガ家だって、高校くらい出てないと、誰も相手にしてくれないよ」
こうして、いやいやながらも高校を受験することになったのだが、担任教師に頼み込んで、近隣の高校のなかで一番近い〈普通高校〉のF高校に志望校を変えてもらうことにした。願書提出締切日の前日のことだった。実は、この時点では、普通高校の〈普通〉が、何を意味するものか知らずにいたのだった。
高校の入試は、何の準備もしていなかったのに、スンナリと合格した。合格したのはいいが、マンガ家への道のりが長くなるような気もして、複雑な気分だった。
そして、ぼくの高校合格は、わが家にとっての一大事にもなっていた。上に五人いる腹ちがいの兄と姉のうち、男三人は父親に反抗して、中学も卒業しないうちに家を飛び出していた。父親の暴力に耐えかねてのことだった。
二十歳以上も年の離れた長兄は、ぼくの学校貯金までおろして博打につぎ込み、母の着物や家財道具もすべて質屋に叩き込んでいた。
それなのにこの長兄は、ぼくの高校の合格発表の日になると、早朝からF高校に出かけ、「この野郎、門を開けろ! 開けねえと、ぶっからすぞ(静岡弁で、ぶんなぐるぞの意味)」
と用務員を大声で脅し、まだ閉じていた門を開けさせたのだという(本人談)。合格発表の掲示板にぼくの名前があるのを確認した長兄は、自転車でわが家まで走ってきて、母に高校合格を報告すると、そのままどこかに走り去っていった。
走っていったのは、近所の商店街だった。長兄は、酒屋のシャッターを叩いて店を開けさせ、「俺の弟がF高校に合格した祝いだから」と、店の前を通る通勤途上の人たちに、ふるまい酒をしたのだという。わが家にとっては、身内から高校に入る者が出ることだけでも、一世一代の大イベントだったのだ。
そして、ぼくは高校生になった。昭和四十一(一九六六)年四月のことである。
投稿者 msugaya : 15:29 | コメント (1) | トラックバック
2005年08月18日
■『仮面ライダー青春譜』第3章 マンガ家めざして東京へ(2)
●マンガ同人誌「墨汁三滴」と出会う--
高校最初の夏休みは、あっというまに終わり、すぐに二学期になった。
少年雑誌「ボーイズライフ」の読者欄に、「マンガ同人誌の会員募集」のお知らせが掲載されたのは、この頃のことだ。
〈マンガ研究会ミュータントプロでは、石森章太郎先生を顧問に、伝統あるマンガ同人誌「墨汁一滴」の流れを継いだ「墨汁三滴」をはじめます。あなたも参加しませんか?〉
こんな告知内容で、応募に当たっては、自作のカットを二点同封して送れという。
「ミュータント・プロ」という研究会の名称は、おそらく石森章太郎のヒットマンガ『ミュータント・サブ』からきたものだろう。何よりも、石森章太郎が名誉会長というのが魅力だった。それまで遠く憧れているだけだったマンガ家の世界との距離が、急に縮まるような気がして、ぼくは大あわてで、指定されたサイズのカットを描いた。
二枚のうちの一枚は、長いあいだ描いてきて多少は自信があった飛行機の絵に決めた。旧日本海軍戦闘機の雷電である。そしてもう一枚は、人物の絵を描いた。二枚とも、市役所で使われた使い古しのペン先で描いたものだった。
「マンガを描くのには使い古しのペン先がいいらしい」と近所に住む市役所勤務の人に話したら、山のように持ってきてくれたのだ。当時、市役所に提出する住民票や戸籍謄本などの申請書類は、すべて、ペンとインクで書かれていた。そのため市役所では、使い古しのペン先が大量に出て、処分に困っていたのだという。ぼくは、この使い古しのペン先を、ヤスリや砥石で研いでは使っていた。
「ミュータント・プロ」は、東京都三鷹市に住む菅野誠という同じ年の高校生が会長をつとめていた。そこにカットを送り、同封した返信用の封筒で返事がくるのを首を長くして待った。
返事がもどってきたのは、一カ月ほど後のことだった。
結果は、不合格。送り返されてきた絵には、「レタリングが下手。テクニックがなっていない。線が汚い」と書かれたメモが同封されていた。
ショックだった。自分では自信を持っていただけに、なおさらだった。
田舎で、雑誌や貸本劇画だけをテキストにマンガを描いていたので、実際のマンガ家の原稿が、どんな線で描かれているのかなんて、わかるはずもない。ただ「テクニックがなっていない」といわれても、どんなテクニックが必要なのかも理解できていなかった。
「マンガ家入門」によれば、「マンガのテクニック」とは、マンガのストーリーをより効果的に読ませるため、見せるための技術であり、それは、クライマックスの盛り上げ方や、主人公の心理状態を的確に読者に知らしめる技術のはずだった。
つまりぼくは、マンガのテクニックとは、絵の技術ではなく、構成の技術のことを指すのだと思っていたのだ。だから、一枚や二枚のカットでテクニックの有無を判断されるのは納得がいかなかった。
「同じ年のくせして、生意気な奴だなぁ」
そんなことを考えながら、ぼくは、ほかの方法を模索しはじめた。
「少年サンデー」誌上に柔道マンガを連載していた貝塚ひろし氏が「まんがマニア」というマンガ家志望者のための雑誌を始めたことを知ったのは、「ミュータント・プロ」から不合格を告げられた直後のことだった。さっそくぼくは、このA5版の薄っぺらな雑誌の購読を開始した。
ここにも、マンガ同人誌ブームの先駆けとなったマンガ研究会がいくつも紹介されていた。マンガ研究会と同人誌が増えたのは、「マンガ家入門」の影響にちがいない。
この「まんがマニア」には、一駒マンガを何点か送り、そのたびに掲載された。しかし、掲載されるマンガの大半は、プロの水準には、ほど遠いものばかり。そこで掲載されても、あまりうれしくはなかった。
ぼくの田舎は気候が温暖で、五月はじめから十月のはじめくらいまで、プールで泳ぐことができた。水泳部員として、毎日、一万メートルくらい泳いでは、家に帰って深夜までマンガを描きつづけていたのだが、そんなことをつづけているうちに、朝起きるのがつらくなってきた。
最初は徒歩で通学していたのに、距離が近いために禁止されていた自転車で通うようになり、ついには、それでも遅刻しそうになって、毎日バスで通うようになったのだ。
毎日、睡眠不足のまま、水泳の練習を続け、深夜までマンガを描いていたせいか、夜になると身体がだるくなり、眠れない日々がつづくようになった。あまりにも体調が悪いので、病院で精密検査を受けたこともある。しかし、どこにも異常はなし。過労から貧血症になっているとの診断で、太いブドウ糖の注射を打たれておしまいだった。
水泳とマンガに明け暮れた高校一年生の二学期が終わろうとする頃、一枚のハガキが舞い込んできた。
ハガキの主は、ミュータント・プロの菅野誠だった。ミュータント・プロの下部組織として、ミュータント・プロ・ジュニアというマンガ研究会を作ることになったのだという。
肉筆回覧誌用の原稿サイズまで、きちんと決められていて、作品を描き上げて送れば、自動的に同人誌に掲載されるらしい。しかも腕が上がれば、「墨汁三滴」の方に昇格できるかもしれないというのだ。
憧れのマンガ家である石森章太郎先生に、自作のマンガを見てもらえるかもしれないチャンスでもあった。高校入試の受験勉強もさぼって描いたマンガを送っても、何の返事もなかった石森章太郎先生に、本当に、作品を見てもらえるようになるかもしれないのだ。ぼくは、冬休みに入ると同時に、ミュータント・プロ・ジュニア用の作品に取り組んだ。
冬休みには郵便局のアルバイトもしていたが、ノルマの配達が終わると、家に飛んで帰ってマンガを描いた。翌年の年明け早々が、締切になっていたからだ。
描いていたのは、『シークレット・エイジエントマン』という二〇ページの読み切りスパイマンガだった。
年が明け、冬休みが終わろうとする頃、なんとか二〇ページのマンガを描き上げ、菅野誠のところに発送した。
今度は、半月も経たないうちに返事がきた。しかも、送った原稿が同封されていた。送られた原稿を見た結果、ぼくを「墨汁三滴」のメンバーにすることに決めたという。ついては、「墨汁三滴」の方は、原稿のサイズが違うので、別の作品を描いて送れというのだ。原稿が返送されてきたことよりも、ファームから一軍に上がれることの方がうれしくて、ぼくは、すぐに新しい作品を描き出した。
締切は、春休みになっていた。ぼくは、冬で水泳の練習もないことをいいことに、高校一年の三学期を、マンガを描くために費やした。
突然、二軍だったぼくが一軍に引き上げられた原因は、「ミュータント・プロ・ジュニア」の方に、実際にマンガの作品を描いて送ってきたのが、ぼくと、もうひとり、都内に住む中学三年生の女子しかいなかったためだった。たった二人の作品では、同人誌も作りようがなかったのだ。
「マンガは下手だけど、せっかく作品を送ってきたのに、入会を断るのはかわいそうだよ」
同じ中学出身の四人の高校生がはじめたミュータント・プロの幹部会議で、ぼくと女子中学生に対する同情が集まり、ふたりして一軍に引き上げられたものらしい。
もちろん当時は、そんなことなど知るはずもなく、ぼくは、ただ必死に次の作品を描き、東京の菅野誠とのあいだで文通をかさねて、できあがった作品を東京に持参することになったのだ。
菅野は、ぼくが上京すれば、石森先生に会わせてくれるだけでなく、作品の批評も受けられるようにしてくれるというのだ。これで張り切らないほうがおかしいというものだ。ぼくは、最後の頃は、睡眠時間を二、三時間に切り詰め、なんとか完成させたマンガの原稿を持って、東海道本線の鈍行に乗り込んだ。静岡県の富士駅から東京駅までは片道五百三十円、三時間半の旅だった。
江東区亀戸にある叔父の家に一泊し、翌日の朝、総武線、地下鉄丸の内線、西武池袋線を乗り継いで、練馬区の桜台駅に向かった。
ミュータント・プロ会長の菅野誠とは、この駅の改札口で待ち合わせることになっていた。
第1章の内容は、この長い一日に起きたことである。
投稿者 msugaya : 08:23 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月20日
■『仮面ライダー青春譜』第3章 マンガ家めざして東京へ(3)
●長編アニメ『ホルスの大冒険』
東京にいき、マンガの仲間と会い、マンガ家の先生がたに原稿を見てもらったおかげで、ぼくはすっかり〈その気〉になっていた。
〈その気〉とは、もちろんマンガ家になることだ。高校二年から三年にかけて、ぼくは、何度も上京しては、マンガ仲間と一緒にマンガ家のお宅を訪問したり、当時のマンガ少年のバイブルとなっていた「COM」というマンガ専門誌を出していた池袋の虫プロ商事にも出かけていた。
たびたび上京するための資金を稼ぎ出すために、夏休みや冬休みには、アルバイトに精を出した。鳶職の手伝いや、東名高速道路の工事など、身体を使うアルバイトが、一番の稼ぎになった。入墨をした鳶職人、気の荒い出稼ぎの漁師のあいだに混じって、ツルハシをふるい、スコップを握った。東名高速道路のインターチェンジの工事では、中学時代の同級生を集めて、金網を張る仕事を土建会社から請け負ったりもした。
高校二年のとき、竹内さんという一年生の女子生徒と知り合った。ぼくがマンガを描いているという噂を聞いて、彼女のほうから話かけてきたのだ。新聞部に所属し、安保問題などで議論をする才女タイプの女の子だった。
その頃のぼくは、安保といったら、国連の安全保障条約のことだと思っていたほどの政治オンチ、社会オンチだった。安保が日米安全保障条約のことだと教えてくれたのも、情けないことに、下級生の竹内さんだったのだ。
竹内さんが、マンガを描くぼくに興味を持ったのは、彼女のお父さんが東映動画のアニメーターだったかららしい。お父さんの名は、竹内留吉さんといい、マンガ家の白土三平氏のお父さんに絵を習った方だという。
白土氏のお父上である岡本唐貴氏は、「松川の人々」などの作品で知られるプロレタリアート画家だった――というようなことは雑誌の記事で知っていたが、その頃は、プロレタリアートの意味もわかっていなかった。
しかし、彼女と知り合ったおかげで、高校二年の夏休みには、東映動画のスタジオを見学させてもらえることになり、いそいそと東京に出かけていった。
西武池袋線大泉学園駅から徒歩15分ほどのところにある東映動画のスタジオでは、『太陽の王子ホルスの大冒険』を作っているところだった。そう、あの東映最後のオリジナル長編アニメといわれる名作である。いまにして思えば、演出・高畑勲、作画監督・大塚康生、美術設計・宮崎駿という豪華スタッフの方々と対面していたはずなのだが、その頃は、アニメ界の事情も知らず、ただポ~ッとしながらスタジオを案内してもらっただけだった。
見学の途中、動画のセクションで、アニメーターの方が、原画が動くところを見せてくれた。数十枚もある動画用紙の束をバラバラッとめくっていくと、紙に描かれたホルスが氷河を滑ってくる。奥行きのある絵でスピード感もあり、紙の上からホルスが目の前に飛び出してくるかのようだった。
とんでもない迫力の絵に、ぼくは、ただただあきれ、呆然としたまま原画の動きをながめていた。
竹内留吉さんは、東映動画の組合紛争に関わっていたとかで、その関係から家族だけ、お母さんの実家のある静岡に別居していたらしい。その問題が解決したのか、娘さんのほうは、翌年、東京の高校に転校していった。
その後、竹内留吉さんのお名前は、『アタックNo.1』をはじめとする他社のアニメ作品で拝見したが、その後も『DRAGON BALL Z』や『ONE PIECE』などの作画監督として活躍されていたらしい。そして、二〇〇一年五月に亡くなられていたことは、つい最近になってからネットの情報で知った。合掌。
投稿者 msugaya : 04:19 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月22日
■『仮面ライダー青春譜』第3章 マンガ家めざして東京へ(4)
●肉筆回覧誌のつくり方
マンガ研究会ミュータント・プロが発行していた同人誌「墨汁三滴」は、石森章太郎先生が発行していた「墨汁一滴」を踏襲した肉筆回覧誌だった。
肉筆回覧誌とは、マンガのナマ原稿を糸で綴じて製本し、会員のあいだを郵便小包で回覧する方式の同人誌のことをいう。
いま、コミケで売られているようなオフセット印刷による同人誌はもちろん、コピーでさえも、設計用の青焼きしかないような時代だった。マンガ同人誌といえば肉筆回覧誌――というのが当たり前だったのだ。
「墨汁三滴」は、隔月――つまり二ヶ月に一回のペースで発行されていた。決められた大きさの原稿用紙にマンガを描き、その原稿を編集担当者に送ると、そこで編集と製本の作業がおこなわれ、一丁あがりとなる。
とはいっても、編集は、そんなに簡単な作業ではない。届いた原稿の裏面に接着剤をつけて貼り合わせ、これを束ねた上で、糸を通すための穴をハンドドリルで開けるのだ。
厚さは最低でも五センチにはなった。穴を開けるだけでも一苦労で、ひとりで編集するのは無理だった。
そこで「墨汁三滴」を編集するときは、同人誌仲間が手伝うことになっていた。
表紙は黒一色のクロス布で、「墨汁三滴」という誌名と号数が、白い糸で刺繍されていた。千葉県東金市に住む小川まり子(のちの河あきら)が、毎号、刺繍を担当してくれた。
「墨汁三滴」が完成すると、東京に住む会員が、石森章太郎先生をはじめ、松本零士、久松文雄、斎藤ゆずる、江波じょうじ、そして後には宮谷一彦といったマンガ家、劇画家の先生がたのお宅を訪問し、批評のコメントを書いてもらっていた。
それから会員のあいだを巡回するのだが、ひとりの会員が所有できるのは、四十八時間まで。その間に、すべての掲載作品を読み、各作品の感想や批評を書いた上で、次の人に郵便小包で送るシステムである。いまのような宅配便もない時代のことだ。郵便小包だけしか配送の手段はなく、毎号、あわてて荷造りしては、郵便局に駆け込んだものだった。
東京で会の仲間と会ってからは、「墨汁三滴」の編集を手伝いに出かけるようにもなった。手伝いにいけば、完成したばかりの「墨汁三滴」掲載作品の批評を持って、マンガ家の先生方の家を訪ねることもできる。それが楽しみで、ぼくは、二ヶ月に一度くらいのペースで上京するようになった。
高三の夏休みには、三鷹市のメンバーの家に泊まり込み、ここでぼくが編集担当となった「墨汁三滴」を完成させた。
このときも、完成したての「墨汁三滴」を持って、石森章太郎先生はじめ数人のマンガ家、劇画家の仕事場を訪問した。もちろん批評してもらうためである。
マンガ家や劇画家の仕事場で、プロの仕事を間近に見るたび、いつか、その仕事場の一角で、ベタ塗りをしたり背景を描く自分の姿を想い描くようになっていた。
こんな状態では、高校の授業などに身が入るはずもない。いちおう高校に通ってはいたが、いつも、心ここにあらず――の状態だった。頭のなかは、すっかり東京に飛んでしまっていた。
投稿者 msugaya : 03:00 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月23日
■『仮面ライダー青春譜』第3章 マンガ家めざして東京へ(5)
●就職先は劇画家アシスタント
ぼくが通っていた高校は受験校だったせいで、三年生になると、国公立、私立理系、私立文系にコースが分かれることになっていた。
それぞれの受験科目に応じた授業に重点が置かれるのだが、大学に進学するつもりがなかったぼくは、授業がいちばん楽そうな私立文科のコースを選ぶことにした。
三年生になると、進学相談や父兄面談が行なわれるのだが、大学にいかないと宣言していたため、その行事も省略されることになった。
「ほかの生徒の邪魔にならなければ、卒業させてやるからな」と、担任が保証してくれたので、ぼくは気分が乗らないと、一日の大半を図書室で過ごすようになった。マンガのストーリーを考えるか、本を読んで、ひたすら時間をつぶすのが日課となったのだ。
読んだのは、井伏鱒二や三島由紀夫の全集からモーパッサンの全集まで。講談社の「われらの文学」も読めば、純文学雑誌の「文学界」や「群像」まで読んでは、ひたすら同級生の授業が終わる時間を待った。
教室での授業中は、誰かが持ってきた「平凡パンチ」を読んでいた。五木寛之の『青年は荒野をめざす』を読んではシベリア鉄道に夢を馳せ、北原武夫の『ミモザ夫人』という官能小説に妄想をかけめぐらせた。
マンガ同人誌「墨汁三滴」の仲間は、次々とアシスタントの口を見つけ、就職先を決めていった。会長の菅野誠は、通っていた工業専門学校を三年で中退し、石森先生のアシスタントになるという。しかも、夏休みには、近所に住む宮谷一彦さんのところにも手伝いに出かけていた。
宮谷さんは、ぼくたちのような「COM」世代にとっては、キラキラと太陽のように輝く新進劇画家だった。そんな劇画家から手伝わないかと声をかけられたのだ。それだけで菅野の腕前が想像できようというものである。もちろん、うらやましくてたまらなかった。
ほかの同学年の仲間も、夏休み前には、アシスタントになることが決まっていた。細井雄二は、江波じょうじ先生、近藤雅人と田村仁のふたりは、斎藤ゆずる先生のアシスタントになるという。その結果、同学年の同人仲間のなかで、高卒後の動向が決まっていないのは、千葉県に住む小川まり子とぼくのふたりだけになっていた。小川まり子は、線が少しラフだったが、少年マンガのような骨太のストーリーマンガが得意な女子高生だった。
そんなぼくにもアシスタントになれそうなチャンスがめぐってきた。夏休みに上京したときに、先に江波じょうじ先生のアシスタントになることが決まっていた細井の紹介で、ぼくも高卒後に、江波先生のアシスタントにしてもらえることになったのだ。
家にもどって就職口が決まったことを母に告げると、さすがに母は泣き崩れていた。大学なんて言葉は、わが家の辞書にはなかったが、やはり、99パーセントの生徒が大学に進学する高校に進んだ息子が、そのまま就職することについては、忸怩たる思いがあったらしい。
その頃、母が勤めていた料亭には、ぼくが通っていた高校の先生方が、宴会のために、しばしば訪れていた。受験校でありながら、陸上競技だけは全国に名を知られた高校だったが、その陸上部顧問の体育教師が、宴会にやってくるたびに調理場に足を運んできては、「息子を大学にいかせてやってくれ」と、母を説得したのだという。その教師も、父親がいない貧しい家に育ったそうで、お母さんが行商をしながら息子の大学への入学金をこしらえてくれたらしい。
「これからは、大学くらい出ていないと、世の中に通用しない」というのが、その教師の決まり文句で、奨学金の資料まで持ってきてくれていたという。
少し前までは、頭の片隅のどこかに、大学に行けない悔しさも残っていた。大学には行かないつもりだったのに、どの程度の大学に入れるのかを確認しておきたくて、旺文社や学研の大学入試模擬試験も毎回受けていたほどだったのだ。もちろん受験勉強なんてしたことがないから、理系の国公立大学は全滅。東京六大学の一校の二部ならば、なんとか入れそうな成績だった。
アシスタントになることが決まったあとも、模擬試験は受けつづけたが、たぶん、自分のアイデンティティのようなものを確認しておきたかったのだろう。
母には、四年間だけ時間をくれ――と頼み込んだ。四年というのは、もちろん、同級生が大学に行く期間である。
四年後、大学を卒業し、就職した同級生の初任給よりも収入が少なかったら、マンガ家になるのをあきらめて郷里に帰り、母と同じ調理師になることを約束した。
もしもマンガ家になれなかったら、手に職をつけるしかない、と考えてはいたが、まだ上京もしていないこの時点では、マンガをあきらめて田舎に帰ることなど考えてもいなかった。とりあえず母を納得させるためには、ウソも方便だったのだ。
すでに東京のマンガ仲間の実力を知り、「COM」などを通じて、同じ年でありながら、はるかに腕の立つマンガ家志望者がいることも知っていた。そんな腕っこきのマンガ家志望者と競わなくてはならないのだ。
そこで考えたのは、マンガ家としてデビューする前に、せめてアシスタントの仕事だけでも生活できるようにしておこう――ということだった。
ぼくは、劇画からストーリーマンガ、そして、ギャグマンガと、ペンを変え、絵柄を変えて、いろいろな絵柄に挑戦した。どんなマンガ家のところでも手伝いができるようにするためだ。この訓練が、後で生活を助けることになろうとは、この時点では夢にも思っていなかった。
この頃のアシスタント志望者は、誰もが斜線の掛け合わせを習う必要があった。宮谷一彦が導入した斜線のテクニックが、あっというまに劇画、マンガの世界を席巻し、細かい斜線を掛け合わせる技術が、アシスタントになるための必須条件となりつつあったからである。
もちろんぼくも、シャシャカ、カリカリ……と、斜線を掛け合わせる練習にいそしんだ。その練習のおかげか、ペンの線は、急速にきれいになっていった。
やがて、高校三年の二学期が終了した。三学期は、受験のために、授業もほとんどなくなる。実質上、この二学期が、最後の高校生活となった。
冬休みに入る直前、就職がきまっていた江波じょうじ先生から電話がかかってきた。年末進行で仕事が厳しくなっているため、手伝いにきてほしいというのだ。ぼくは冬休みになるのを待ちかねて、マンガの道具と着替えを抱えて上京した。一九六八年の暮れ、東京の府中で三億円事件が起きた直後のことだった。
細井雄二とふたりで先生の家に泊まり込み、アシスタントの仕事をした。同級生たちは、みんな受験勉強でヒイヒイしているはずだった。そんなとき、ぼくは、いちはやく「大人の世界」に飛び込んだような気になっていた。
参考:小学生から高校生までの自作マンガの変遷
投稿者 msugaya : 00:19 | コメント (0) | トラックバック
2005年08月25日
■『仮面ライダー青春譜』第3章 マンガ家めざして東京へ(6)
●六〇年代末のマンガ事情
一九六〇年代後半のマンガ家志望者のヒーローといえば、なんといっても宮谷一彦だった。
「COM」の月例新人賞に『眠りにつくとき』という作品で入選した宮谷は、独自に開発した緻密な絵柄で劇画家志望者を魅了し、さらに先発のプロの劇画家たちにまで、大きな影響を与えていった。
ぼくたちも、劇画家のアシスタントになると決まったときから、宮谷が劇画の世界に持ち込んだ複雑な斜線の掛け合わせを真似ていた。曲線を掛け合わせたり、直線を掛け合わせながら渦を巻かせるといった細かい作業がどれだけできるかで、アシスタントとしての優劣が決っていた時代でもあったのだ。
スクリーントーンの二重貼り。スクリーントーンをホワイトでぼかして写真のようなグラデーションの効果を出す。そんな工夫も、皆、宮谷が開拓したものだった。
宮谷一彦は劇画のテクニック――とりわけ作画技法を大きく変革した革命家だったといってもいいだろう。
だが、彼の功績は、そのテクニック面だけではない。それまで劇画、マンガといえば、時間つぶしの娯楽だと思われていた世界に、思春期の少年の悩みや、作者自身のことを描いたと思える私小説ともいえる内容の作品を連発してきたのだ。
マンガ・劇画の文学化は、たとえば永島慎二の『漫画家残酷物語』や石森章太郎の『ジュン』などでも試みられていたが、宮谷の作品は、もっと「身近」だった。
また、同じ文学的傾向を持つ作品でも、「ガロ」の作家たちの描き出す四畳半・下町・ドブ川的なものとも一線を画す実に都会的なセンスにあふれていた。
「身近」に感じられたのは、そこに描かれた高校生の世界が「リアル」だったからだろう。リアルの要因は、「本物」を描いたことにあった。
それまで「リアル」を売り物にしてきた貸本系劇画は、実は表現を激しく描く「激画」であり、リアルやシリアスとは、ちょっとちがっていた。
たとえば少年が煙草の吸い殻を投げ込むのは、コカコーラの瓶である。路上を走るスポーツカーや乗用車も、どこのメーカーの何という車種かまでがわかった。エレキギターはリッケンバッカーだったりと、「ブランドがわかる」のが宮谷作品の特徴でもあった。固有名詞という点では大藪春彦のアクション小説が有名だが、その大藪小説と共通する匂いを放っていた。宮谷は、大藪春彦小説の劇画化も多数手がけているが、これ以上の適任者はいなかった(固有名詞のカタログ小説『なんとなくクリスタル』が出てくるのは十年以上後のことである)。
私小説的な作品としては、自らを主人公にした『ライク・ア・ローリング・ストーン』。思春期の少年を主人公にした作品では、『少年サンデー』に2回連続読み切りとして登場した『75セントのブルース』、『闇に流れる歌』などがあった。『75セントのブルース』はジャズ・ミュージシャンを目指す少年とトランペッターの出会い、『闇に流れる歌』は、当時、人気の絶頂にあったラジオの深夜放送を舞台にしたパーソナリティと視聴者の少年の交流を描いたものである。さらには、『COM』の別冊付録に掲載された『セブンティーン』が、初めて劇画の中で高校生の妊娠中絶を扱ったということで、話題を呼んでいた。
授業中に『平凡パンチ』連載で連載されたいた五木寛之の『青年は荒野をめざす』を隠れて読み、図書室で大江健三郎の『セブンティーン』や『死者の奢り』を読んでいたぼくは、すぐに宮谷一彦の作品にかぶれ、彼の作品が掲載された雑誌は、すべて買い込み、丁寧にスクラップしていった。もちろん、細密なペンつかいのテクニックを盗むのも目的だった。そのスクラップが、後に光文社の下請けで『女性自身』の編集を手伝ったときに、五木寛之氏の『海を見ていたジョニー』劇画化の企画が出たときに役立つことにもなった。
投稿者 msugaya : 02:55 | コメント (6) | トラックバック
2005年08月29日
■『仮面ライダー青春譜』第3章 マンガ家めざして東京へ(7)
●上京
一九六八年の年末を東京でアシスタントの仕事をして過ごしたぼくは、年が明けた一九六九年の新年早々から、アマチュア無線の講習会に通い出した。高校生活最後の冬休みを有効に使うためである。
高校では、合間を見つけては物理部の部室に出入りし、グループサウンズ・ブームに影響された同級生たちのバンドのために、真空管でアンプを作ってあげていた。
部室に置いてあるアマチュア無線機を使い、学校のクラブ局に認められた以外の周波数で交信したために、郵政省の東海電波管理局から学校にお叱りのハガキが舞い込んだこともあった。
ぼくの心の片隅には、まだ、エレクトロニクスで身を立てたいという気分が残っていた。
とっくに就職先は決めてあったのに、旺文社や学研の模擬試験も、理科系の大学を志望校にして受けつづけていたのも、ラジオの世界に対する未練からである。アマチュア無線も、やはり、やりのこした未練のひとつだったのだ。
中学一年生のときに一度だけ、アマチュア無線の国家試験に挑戦したことがあったが、その頃の試験は、すべて筆記だった。無線工学や電波法規の問題が、答えはわかっているのに、漢字が書けなくて敗退してしまっていた。「平衡」「逓倍」といった漢字が書けなくて、それを思いだそうとしているうちに時間が過ぎてしまったのだ(手書きでは、いまでも辞書を引かないと書けないのだが、日本語ワープロのおかげで、こうして書けるようになった。コンピューター様さまである)。
この頃は、ハムの国家試験は春と秋の年二回だけ。それ以外には、夏休みや冬休みに開催される講習会に通って講義を受け、終了試験にパスするしか免許取得の方法はなかった。
同級生たちの中で、推薦入学などで大学が決ってしまった者は、自動車の運転免許を取りに通っていた。しかし、ぼくは、いましかハムの資格を取るチャンスはなくなってしまうだろうと、電車に乗って、静岡市の高校で開かれた講習会に通い、なんとか終了試験にもパスして、アマチュア無線の従事者免許を手にすることができた。
一日だけ講習会を休んだが、それは『墨汁三滴』の会合に出席するため、東京に出かけたからである。
その会合は、マンガ同人誌ブームを取り上げる『アサヒグラフ』の取材を受けるためのものだった。
三鷹駅での待ち合わせシーン、仲間の家での編集会議の様子などが、プロのカメラマンの手で撮影されていった。
東京から戻ると、すぐに三学期がはじまった。
各地の大学受験に出かける者が多くなり、教室には空席が目だつようになっていた。授業も自習になることが多かったのではないか。
「すがや、お前、マンガ描いているのか?」
自習になった英文法の時間に、英語の教師が突然ぼくに訊ねてきた。
「え?」
その教師は、ぼくがマンガを描いていることなど知らないはずだった。
「図書室に届いた『アサヒグラフ』に出てたぞ」
教師がニヤリと笑って教えてくれた。
ぼくは、授業が終わると、あわてて図書室に走った。雑誌を並べた棚に、その『アサヒグラフ』が置かれ、ページをめくると、ぼくたち『墨汁三滴』の仲間が飛び出してきた。
担任や、上京のたびに学割の証明書をもらいにいった教頭など、一部の教師しか、ぼくがマンガを描いていることは知らないはずだったのに、「アサヒグラフ」のおかげで、すっかり有名になってしまったのだ。
高校三年の三学期は、受験のため一月で授業は終わりになる。その一月の中旬過ぎ、全共闘の学生が占拠していた東大の安田講堂に機動隊が突入した。ぼくは学校をさぼって、その光景をテレビでながめていたが、大学闘争なんてものは、ブラウン管の枠の中に切り取られた、遠い世界の光景でしかなくなっていた。
同級生の中には何人か、東大を受験する者がいる。彼らは、あの荒れた大学にいくのだろうか……?
そんなことがチラリと頭の中をかすめたりもしたが、その東大の入学試験も、翌々日には中止が発表された。
二月五日の早朝--ぼくは、布団と電気ゴタツと着替えを荷台に詰め込んだ叔父のライトバンに乗って東京に向かった。従兄弟がひとり、引っ越しの手伝いについてきてくれた。
雪で箱根を通る国道1号線が不通になり、国道246号線を迂回したために、目的の練馬区大泉学園にある四畳半一間のアパートに着いたのは、午後六時過ぎになっていた。六時間の予定が、十二時間もかかったことになる。東名高速道路は、まだ一部が開通していただけだった。
先生の家に挨拶し、叔父たちが帰ると、しんしんと冷えるアパートの部屋の中で、電気ゴタツにスイッチを入れると、ぼくは、さっそくペンと墨汁を引っ張り出した。
一人暮らしの第一夜だったが、不思議と寂しさや恐ろしさはなかった。明日から本格的に始まるプロのマンガ家のもとでのアシスタント生活を考えると、身体が熱くなって眠れなくなっていた。
投稿者 msugaya : 04:16 | コメント (1) | トラックバック
2005年09月08日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(1)
●アシスタント生活がはじまった
 朝--。
朝--。
うるさいほどの鳥のさえずりで目がさめた。
すでに外は明るくなっている。カーテンもまだ取り付けていなかったアパートの部屋の窓をひらくと、狭い道路をはさんだ向い側には大きなお屋敷があり、塀の内側が雑木林になっていた。その林の中で、鳥たちがさえずっていたのだ。
「ここがホントに東京?」
練馬のはずれ、西武池袋線の大泉学園駅から歩いて七、八分の場所にある農家が建てたアパートだ。周囲には、まだまだ武蔵野の面影が残っていた。
アパートの建つ敷地内にも竹薮がある。地方の工場都市の中心地からやってきたぼくの目には、ひどい田舎に見えたものだった。
仕事は午後からだ。まだたっぷりと時間がある。ぼくは、散歩がてらに食事の買い出しに出かけた。
先生のところでは、仕事の途中の食事は、自分でとることになっていた。
しかし、初任給は二万円。七千円の部屋代は、先生が払ってくれることになっているが、将来の独立にそなえ、毎月五千円ずつ貯金しようと決めていた。
残りは一万五千円。一日五百円ずつつかえるが、外食では、ラーメンが百円前後、定食が百三十円から百五十円くらい。食費以外にも生活費はかかるので、とても外食なんかしていられない。
そこで食事は自炊にし、仕事場にも弁当を作って持っていくことにした。
小さな電気釜でご飯を炊いて、マーケットで買ってきた薄いトンカツをタマネギと一緒に煮込み、その上に溶きタマゴを流す。これでおかずの出来上りだ。半分を朝食に、半分を家から持ってきた弁当箱に、ご飯と一緒に詰める。
そして、いま、煮込みカツを作ったばかりの鍋を洗って、残ったタマネギを具に味噌汁を作る。これで朝食の出来上りだった。
一ヶ月後に、同人誌『墨汁三滴』の仲間の細井雄二がアシスタントとして同じ部屋に住むようになると、そのまま、ぼくは、彼の食事も作るようになった。母が仕事でほとんど家にいなかったこともあり、また旅館で調理師をする母の手伝いなどもしていたこともあって、自炊はお手のものだった。
昼過ぎに歩いて三分ほどの江波先生の家に出かけると、先生も起きてきたばかりのところだった。そこに電話がかかってきた。やはり同じ『墨汁三滴』の仲間で、千葉に住む小川まり子という同い年の女の子からだった。ぼくと細井、そして彼女の三人が、週刊誌のスタートで忙しくなっていた江波先生のアシスタントになることが決まっていた。そのなかでぼくだけが、卒業式も待たずにアシスタントを始めることにしたのだった。
電話の内容は、彼女が『別冊マーガレット』の月例新人賞を受賞したというものだった。高校生活の記念にと描き上げて送った原稿が、みごと新人賞に選ばれたのだ。
男まさりの大胆な絵を描いていたが、ストーリー作りが抜群にうまく、いつも舌を巻いてばかりだった。そんな彼女が新人賞を受賞したといっても、そんなに驚くことではなかった。『墨汁三滴』の仲間のなかで、いちばん先にプロのマンガ家になるのは彼女だろう――とひそかに思っていたからだ。
彼女からの電話は、アシスタントになるのを断わりたいというものだった。編集部でめんどうを見るから上京するようにと言われたらしい。
その話に、ほっとしたのは、ぼくと、先生の奥さんだった。ぼくも、なんとなく女の子が一緒では、やりにくいなと思っていたし、奥さんは奥さんで、先生が女の子と同じ部屋で仕事をするのを心よく思っていなかったからである。
彼女の入選作は、まもなく『別冊マーガレット』に掲載された。一六ページの短篇で、題名は『サチコの仔犬』。作者の名前は〈河あきら〉となっていた。
投稿者 msugaya : 06:43 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月12日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(2)
●最初の仕事は怪奇マンガ
いよいよ仕事がはじまった。
最初の仕事は怪奇マンガだった。当時、楳図かずお氏が巻き起こした少女向け怪奇マンガがブームになっていた。楳図氏は、すでに少年誌に移行していたが、古賀新一などの手で、あいかわらず少女怪奇マンガの量産はつづいていた。その少女怪奇マンガを、江波先生も連載することになったのだ。
掲載誌は講談社の「少女フレンド」。恋人に裏切られ、殺された女性の長い髪が、死体から離れ、恋人に復讐するストーリーだった(と思う)。
江波先生は、わら半紙にネームを入れていた。そのネームを原稿用紙に写していくのだが、ぼくに最初に割り当てられた仕事は、その原稿用紙づくりだった。
劇画家の多くは、ペンタッチを活かすために、ペン先の引っかかりやすい画用紙を好んで使っていた。江波先生のところも同じで、薄手の画用紙を原稿用紙に使っていた。
マンガの原稿用紙は、模造紙や画用紙の上に基準となる型紙を重ねて載せ、千枚通しなどで穴を開けたものを使うのが一般的だった。
定規を使って穴と穴を鉛筆で結び、枠線の基準となる線を引いたものが原稿用紙になるのだが、江波先生のところでは、もっと合理的な方法が使われていた。厚紙の内側をカッターで切り抜いた型紙があり、この内側を鉛筆でなぞるだけで、基準の枠線が引けてしまうのだ。
この型紙を使った原稿用紙づくりが、ぼくの最初の仕事だった。
この原稿用紙に、先生がネームを写し取っていく。もちろんコマ割りしながらだ。ネームは、二つ折りにしたワラ半紙に書かれていた。
ぼくはネームとコマ割りが入った原稿用紙を受け取ると、まずカラス口で枠線を引いていく。枠線が乾いた原稿用紙に、先生が人物の下絵、ペン入れをしていく手順になっていた。
この時点でアシスタントは、ぼくひとりだけ。人物のペン入れが終わった原稿用紙に背景を描いていくのだが、情けないくらいに絵が描けない。ガチガチに緊張していたからだ。
それでも数日が過ぎると、少しづつ要領も覚えてきた。次第に背景をまかされるところが増えていき、仕事に通うのが楽しくなっていった。
投稿者 msugaya : 05:12 | コメント (2) | トラックバック
2005年09月13日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(3)
●大人への階段
初めての休みの日、ぼくは、従兄弟が住む中野坂上のマンションに遊びにいった。この従兄弟は母の姉のひとり息子で、芸能プロで俳優のマネージャーをやっていた。
「みっつるちゃーん、はじめましてーっ!」
中野坂上にある従兄弟のマンションに着き、ドアの呼び鈴を鳴らすと、まるまると太った若い男性がドアを開け、にこやかな笑顔で声をかけてきた。三枚目をめざす役者さんだという。年齢はぼくより六歳上だった。
芸名は、畠山麦{はたけやま・ばく}。TBSテレビ系で放映された『柔道一直線』(六九年六月~七一年四月放映)に、主人公の一条直也の先輩役で登場してくるのは、この少し後のこと。『秘密戦隊ゴレンジャー』に、カレーの好きなキレンジャーの役で出演するのは、さらに数年を経てからになる。
その日は、従兄弟のマンションでぼくの歓迎会が催され、ビールとウィスキーをたらふく飲まされた。
父をはじめ、周囲には酒飲みばかりがいたせいで、ぼくはずっと酒飲みを憎んでいた。そのため上京するまで一滴の酒も飲んだことがない。
高3の夏休み、アシスタントになることが決まったとき、同級生たちが就職祝いを開いてくれたことがあった。夜、水泳部の部室に、柔道場の畳を剥がして持ち込み、ここで酒盛りを始めたのだ。安いウィスキーをコークハイにして飲んだおかげで、ぼくを除いた全員が酔っぱらい、夜のプールに飛び込んでいた。そんな状態でも、主賓のぼくは、コーラを飲んだだけだった。
しかし、社会人になったんだから、酒くらい飲めなければダメだと従兄弟に説教され、その挙げ句に、従兄弟夫妻と麦さんから、次から次にビールとウィスキーを注ぎ足され、とうとう酔いつぶれてしまったのだ。
畠山麦さんとは、この日の出会いをきっかけに、その後、暇さえあれば一緒に遊ぶようになる。酒を飲み、深夜の代々木公園にアベック(死語?)を冷やかしにいき、山や川にも遊びにいった。麦さんたちと遊ぶのが便利なように、アパートも近くに引っ越したほどだった。
その夜、従兄弟のマンションに泊まったぼくは、翌朝、電車を乗り継いで大泉学園のアパートに帰ったが、二日酔いの気配などカケラもない。もともと呑ん兵衛の家系に育っていたせいで、肝臓が頑丈だったのかもしれない。
途中、西武池袋線の車窓から、「古田体制打倒」「安保反対」などと書かれた大きな立て看板が見えたが、そこが江古田の日大芸術学部だということを知ったのは、しばらくたってからのことだった。
投稿者 msugaya : 00:48 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月14日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(4)
●アシスタントも楽じゃない
アシスタント稼業を始めてから一ヶ月半が過ぎた頃、ぼくは高校の卒業式のために家にもどることになった。
ところが、この日は、ちょうど「少女フレンド」の締切だった。朝まで原稿を描いても終わらないため、そこで仕事を一区切りつけさせてもらい、ぼくは一睡もしないまま、朝一番の東海道新幹線で帰郷した。
家に寄って学生服に着替え、母校に向かう。
卒業式といっても、ぼくはもう、アシスタントとして仕事をはじめていた。一足先に社会人のはしくれにつらなったという意識もあって、進学が決まった大学の話をする同級生たちが、少し子供っぽく見えたりしたものだった。
卒業式は、半数くらいの生徒しか出席していなかった。各地の大学を受験するために、留守にしている生徒が多かったのだ。
卒業式が終わると、一年生の女の子が花束をくれた。連絡先を教えてほしいといわれたが、あいまいな返事をしてごまかした。マンガ家のアシスタントになったのはいいが、この仕事がいつまでつづくのか、まるで自信がなかったからである。アシスタントをクビになって、こっそりと郷里に舞いもどることだってありえるのだ。そんなことを考えると、とても東京の住所など教えられなかった。
家にもどったぼくは、母が用意してくれてあった赤飯をかきこむと、すぐに駅に向かった。東京では先生が、ひとり徹夜で原稿を描いている。その手伝いをしなくては……と思うと、つい早足になった。
駅に着くと、跨線橋の階段の下で、二年生の女の子がひとり、ぼくを待っていた。ぼくが読書好きだというのを知っていて、在学中も、ときどき純文学の本などを貸してくれていた。
「これ電車の中で読んでいってください。卒業のお祝いのかわりです」
手わたされたのは、北杜夫の本だった。
東海道本線と東海道新幹線を乗り継いで東京にもどり、先生の家に駆けつけると、先生は休んでいた。奥さんが、ぼくにも、少し寝てきたらという。結局その日の仕事は夜からになった。
高校を卒業しても、卒業したという実感が湧かなかった。もちろん感激などもない。それも、在学中からずっと、気持ちが東京に向いていたせいだろう。やっと肩の荷がおりた、というのが正直な気持ちだった。
まもなく、やはり高校を卒業した細井雄二が、江波先生のところにやってきた。
彼の自宅は三鷹にあるが、ふだんは、ぼくと同居することになった。
四畳半のアパートに男がふたりで寝泊まりするのだから、むさ苦しいことこのうえない。
仕事は、「少女フレンド」の連載が終わったと思ったら、すぐに「少年サンデー」で新連載がスタートした。あの『ちかいの魔球』と同じ福本和也氏原作の野球マンガだった。
週刊誌の連載のほかに何本かの月刊誌の連載も加わって、ぼくたちは、アパートの部屋には、ただ眠るだけのために帰るような状態になった。
たまの休みの日には、細井は三鷹の実家へ洗濯物を抱えて帰っていく。ぼくの方は、部屋の外にあった流し場で洗濯だ。ため込んだ衣類を洗うだけで、あっというまに一日は過ぎていった。
三ヶ月ほどが過ぎたとき、細井がアシスタントをやめたいと言い出した。
細井は、もともと、あすなひろし氏の絵が好きで、あすな風の繊細なタッチのマンガを描いていた。先生が「少女フレンド」で怪奇マンガを描いているときだと、出番も多くあったのだが、劇画タッチの野球マンガでは、その繊細な線が裏目に出ることもあった。
ぼくの方は、アシスタントでも食いっぱぐれがないようにと、劇画からギャグマンガまで、いろいろなマンガ家の絵柄をまねていた。いまさら田舎には帰れない……という思いが強かったからである。おかげで、迫力ある劇画を描く先生にも、少しは気に入られるような絵を描けるようになりつつあるところだった。
「うーん……でも、いまやめたら、迷惑がかかるしさ……」
「しかたないよ。かわりに言ってやるからさ」
ぼくは、渋る細井をせきたてて、先生の家にいき、事情を説明した。
先生も、すぐに納得してくれて、細井は退職することになった。
「困ったことがあったら、連絡しろよな。うちには、ひとりくらいだったら寝るとこもあるしさ」
「うん」
そうは答えたものの、そんな気があるわけがない。先生のところで腕を磨いて編集者に認められ、一日も早くデビューを果たすのだ--ぼくは本気でそう考えていた。
しかし、その決意も、短期間でぐらつくことになった。先生が「少年サンデー」で連載していた野球マンガのアンケート結果が思わしくなく、十回で連載が終了することになってしまったのだ。
しかも他の連載までバタバタと終わり、残るは月刊誌が一誌だけとなった。こうなると、仕事は月のうちに三日か四日だけ。マンガ家の野球大会やボーリング大会のほうが忙しくなっていった。
先生が所属するマンガ家の野球チームで欠員が出ると、そのたびに穴埋めに駆り出された。セカンドを守っているときに、猛然と盗塁を敢行してきたちばてつや氏に、手をスパイクされたこともあった。
ベテランの貝塚ひろし氏が、仕事があまりにも忙しくなったせいでノイローゼ状態になり、失踪してしまうという事件が発生したのも、この頃のことだ。
創刊してから間もない「少年ジャンプ」でも貝塚氏は連載作品を持っていた。このままでは貝塚氏のページが白紙になってしまうことになる。あわてた編集部が、急いでピンチヒッターに立てたのが本宮ひろ志さんだった。本宮さんは、ぼくが入る直前まで、江波先生のところでアルバイトとして仕事を手伝っていた。
本宮さんは、地下鉄工事をして金を貯めては、その金がつづくあいだはマンガを描き、持込みを繰り返していたが、さっぱり売れずに腐っていたらしい。
そこにピンチヒッターの仕事が飛び込み、張り切って描いた作品が『男一匹ガキ大将』だった。
代役のはずだった『男一匹ガキ大将』は、予想外の人気を集め、あっというまに巻頭カラーを飾るほどのヒット作となった。
そのせいか、やはり野球にきていた本宮さんは、ニコニコと顔をほころばせていた。
「活版でもカラーでも、原稿料は、ずっと一ページ千円だったんスけどね、編集者に値上げしてくれって言ったら、一気に七千円にしてくれたんスよ」
ぼくは、そんな言葉を脇で聞きながら、やはりマンガ家はチャンスの職業なんだと確信した。
しかし、チャンスもあれば、それを失うこともある。そんな厳しい現実を知るのは、この直後のことだった。
ぼくがアシスタントをしていた江波先生は、仕事が減りはじめていた割には、野球にボーリングにとノンキだった。しかし、先生はノンキでも、家計を預かる奥さんが、次第にカリカリしはじめたのだ。
すぐに夏がきた。
仕事がある日なのに、先生の家に出かけても、今日はまだネームが入っていないからと言われ、トボトボとアパートに帰る日がほとんどだった。
ボンヤリしていてもしかたがないので、やはりアシスタントをしている「墨汁三滴」の仲間のところに遊びにいくことにした。
菅野誠がアシスタントをしている石森章太郎先生の仕事場にいくと、週刊誌が五本、月刊誌数本の仕事のために、アシスタントたちは青ざめた顔で机にへばりついていた。
「ヒマでいいよな」
シャカシャカと『リュウの道』の原稿にペンを走らせながら、菅野が言う。
「おれなんか、この見開きのバック、昨日、徹夜で描いたのに、先生に直しを出されてさ。切り貼りして描き直してるんだぜ」
「忙しい方がいいよ。こっちなんか、することがないんだから」
ぼくたちが喋っていると、仕事場で、やはり徹夜で原稿を待っている編集者たちが、じろっと睨みつけてきた。
齊藤ゆずる氏のアシスタントになった田村仁、近藤雅人という同人誌仲間のところにも遊びにいった。齊藤先生は、そんなに仕事は多くなかったが、人のめんどうを見るのが好きで、自分のアシスタント以外にも、友人のマンガ家に仕事場の机を貸していた。しかも、居候のマンガ家の方が、仕事が忙しいのだという。居候のマンガ家は、壁に「一秒が金儲け」という標語を書いた紙を張りつけていた。
マンガ仲間のところで話すことは、やはり業界の噂話になる。
--『巨人の星』や『男の条件』といった連載で徹夜の連続の川崎のぼるさんのところでは、編集者が差入れしたスタミナドリンクの箱が山積みになっていて、アシスタントは、それをジュース代わりに飲んでいる……。
--川崎さん自身も、編集者が見張っているために眠る時間もなく、すっかり胃をこわし、机の脇に置いた洗面器にゲーゲーと吐きながら、マンガを描いている……。
--原稿が落ちそうになった川崎さんの窮状を救うため、永島慎二さんがアシスタントを連れて応援に駆けつけ、原稿を間に合わせた……。
そんな「忙しいマンガ家」の話ばかり聞いていると、次第に、みじめになってきた。
「やめさせてもらえないでしょうか?」
思いきって先生に伝えたのは、一九六九年七月二十日のことだった。
なんで日付まで憶えているかというと、アポロ11号の月面着陸が、この日だったからである。
アパートにテレビもなかったため、ぼくは近所のラーメン屋に出かけて冷やし中華をすすりながら、月面から送られてくる映像を見た。その足で先生の家に向かい、退職の話を切り出したのだ。
「そう言ってくれると、助かるのよね」
先に返事したのは、横に立っていた奥さんだった。
「おいおい、それじゃ、菅谷くんの立つ瀬がないじゃないか」
「だって、しかたないでしょ。仕事がないんだから」
そう言われては、先生も、返す言葉がない。
先生ほどの腕を持っていて、仕事がこないはずはなかった。しかし、ただ腕があるだけでは、仕事が来ないのもわかるようになっていた。人気のあるなしだけでなく、マンガ家にも企画力や営業力が必要なのだ。石森先生や、ちばてつや氏のところでは、出版社との交渉や、仕事のスケジュールを管理し、テレビ化の企画なども進めるマネージャーがいた。当然、プロダクションも会社組織になっている。
マンガの世界も、職人肌では通用しなくなりつつあった。マンガというメディア自体が、職人主導から、ビジネス主導の世界に変わる転換期でもあったのだ。
退職はOKになったものの、その後のあてがあったわけではない。郵便局で毎月五千円ずつ貯金していたが、仕事がない分だけお金を使う機会も多くなっていた。本当なら半年で三万円貯まっていなければいけないのに、実際の貯金は、二万円ちょっとに減っていた。
これではアパートも借りられない。いまのアパートは、先生が借りてくれたもので、アシスタントをやめたら、出ていかなければならないのだ。
だからといって、あてはない。もちろん田舎に帰るのもくやしかった。
ぼくは、考えあぐねた末に、ワラをもつかむ気持ちで、細井雄二の家に電話をかけた。
投稿者 msugaya : 04:40 | コメント (5) | トラックバック
2005年09月16日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(5)
●居候生活
わずか六ヶ月でアシスタントをやめたぼくは、一緒にアシスタントをしていた同人誌仲間の細井雄二の家に居候させてもらうことになった。
お菓子屋さんを営んでいたお母さんが、店を手伝いながらマンガを描いたらいい――と言ってくれたのだ。
店に出かけるのも、午後からでかまわないという。これならば、店が終わった後、夜中までマンガを描くことができる。
このお母さんは、昔から人の面倒を見るのが趣味のような人で、困った人がいると、すぐに面倒をみたり、居候させたりしていたのだという。ぼくが居候をはじめたときも、ほかにひとり、居候状態の中年男性がいた。
細井雄二も、子供の頃から、そんな生活に慣れっこになっていたらしい。「困ったら電話しろ」と言ってくれたのも、こんなアテがあってのことだったのだ。
細井のお母さんが営むお菓子屋さんは、三鷹市と調布市の境界ちかくにある小さなマーケットの中にあった。ちかくに高級住宅が多いせいか、コーラをケースで購入する顧客も多く、ぼくは自転車での配達も担当した。
自転車の荷台にコーラのケースをくくりつけて、配達してまわった先には、クレージーキャッツの谷敬氏や落語家の林家木久蔵師匠の家があった。
店番をし、買物にくる主婦や子供と軽口をたたきながらお菓子やケーキを売る。その様子が水に合っているように見えたのか、細井のお母さんからは、「マンガなんかやめて、お菓子屋になったら? そっちのほうが向いてそうよ」と、冗談まじりに言われていた。
ぼくはぼくで、まったく家族の一員として扱ってくれる細井家の居心地がよくて(おそらく、生まれてからこのかた、家族の団らんといったもの縁のないままに育ったせいだろう)、つい、その好意に甘んじてしまおうか、と思ったこともあった。
しかし、仲間のうちで、アシスタントもしないで、プロのマンガ家の世界から遠ざかってしまったのは、ぼくと細井の二人だけだという焦りもあった。石森先生のところでは、菅野誠がバリバリと緻密な背景を描き、小川まり子は、阿佐ヶ谷の喫茶店でウェイトレスのアルバイトをしながら、すでに担当者がついて、『別冊マーガレット』で読み切り作品を発表するようになっていた。
自分のマンガを描こうと思っても、つい、夜中は、細井と二人で、話をして遊んでしまう。細井のお母さんからもらった給料代わりの小遣いもあるせいで、深夜に喫茶店に出かけたり、ボーリングにいったり。それはそれで楽しくはあったのだが、いつも、どこかに焦りと苛立ちを感じていた。
投稿者 msugaya : 01:24 | コメント (0) | トラックバック
2005年09月17日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(6)
●編集プロダクションに就職
十月に入ってすぐ、細井の家に、マンガ家の清つねおさんから電話がかかってきた。
清さんは、ぼくの出身地、静岡県富士市に隣接する富士宮市の出身で、地元の高校を卒業したあと上京し、石森章太郎、森田拳次両先生のアシスタントを経て独立したギャグマンガ家だった。
『少年サンデー』や『まんが王』などに作品を発表する恵まれたデビューを飾ったが、すぐに身体をこわしてしまい、郷里の病院に入院することになった。マンガ家志望だったぼくを、入院中の清さんに会わせてくれたのは、清さんの家の近所に住むひとつ年上の女子高生だった。
その後、退院して再上京した清さんは、鈴木プロというマンガ専門の編集プロに所属し、マンガやカットの仕事を手伝っていた。
鈴木プロは、「少年キング」や「COM」の編集者としてマンガ界で知られていた名物編集者の鈴木清澄さんが、虫プロ商事を退職して設立した〈日本初のマンガ専門編集プロダクション〉だった。
鈴木さんには、「墨汁三滴」の仲間といっしょに「COM」の編集部を訪ねたときに会っていた。一年ちょっと前、高三の夏休みのことだ。
鈴木さんは、「墨汁三滴」に描かれたぼくのマンガを見て、「若さがないなあ……」といった。ぼくのマンガが、ロケットやらロボットが出てくる〈娯楽作品〉だったせいである。
「COM」や「ガロ」には、若い新人による多数の実験作が掲載されていたし、同人誌にも、やはり既成のマンガ作品とは一線を画すような前衛的な作品が収録されていた。
商業誌に掲載されている娯楽作品のできそこないのようなマンガを描くぼくは、こころざしが低いと思われたのにちがいない。もっともぼくは、それでもかまわなかった。ぼくにとってマンガとは、生活するため、稼ぐための手段だったからだ。
まだ設立されて日の浅い鈴木プロは、劇画ブームやコミックス・ブームの追い風を受け、猫の手も借りたいほどに忙しくなっていた。そこで猫の手……いや、人手さがしを頼まれた清さんが、ぼくに声をかけてくれたのだ。清さんは、ぼくの家に電話をかけて、母から細井家のやっかいになっていることを聞いたとのことだった。
ぼくは、清さんの誘いを受けることにした。細井の家にいつまでも居候しているのも心苦しかったし、編集の仕事ではあるが、マンガ業界の片隅で働くことに魅力があったからだ。
とりあえず池袋にあった鈴木プロの事務所に出かけ、鈴木社長の面接を受けた。
社長は、「菅ちゃん(菅野誠)の仲間で、ロボットのマンガを描いてたね、確か」と、ぼくのことを憶えていてくれた。
「あんなマンガじゃプロにはなれないから、うちで編集の勉強をして、編集で身を立てるといい」
社長にいわれて、ぼくは、はあ……と力のない返事をした。反発したい気持ちはあったが、それよりも生計を得るのが先立った。
月給は2万5000円。残業代はなし。保険も年金もないとのことだったが、それが何を意味しているのかもわからなかった。
その条件でかまわないというと、すぐに社長から就職のOKが出た。
三鷹の細井の家からでは、池袋まで通うのは大変なので、近くにアパートを探すことにした。
新しく借りたアパートは、西武池袋線で池袋から2駅目の東長崎。住所は豊島区千早町で、横山光輝先生のお宅から歩いて5分ほどのところだった。
引っ越し荷物は、細井の兄さんがライトバンで運んでくれ、また、ひとり暮らしがはじまることになったのだ。
荷物は布団一組に、衣類の入ったベビーダンスとコタツ、そしてアルミスチールの本棚がひとつずつ。細井の兄さんに手伝ってもらって部屋に荷物を運び込みにいくと、部屋の畳がない。押し入れを開けると、押し入れの床板もない。
大家に事情を聞くと、前に住んでいた夫婦が、だらしのない使い方をしていて、畳と押し入れの床が腐ってしまっていたのだという。畳表だけ替えればいいと思っていたら、畳を新しく入れ替えなくてはいけなくなり、押し入れの床も修理することにしたという。
これでは寝ることもできず、その日の夜は、従兄弟のところに泊めてもらうことにしたが、なんだか、先が思いやられるような出来事ではあった。
投稿者 msugaya : 00:56 | コメント (1) | トラックバック
2005年09月19日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(7)
●初仕事は『ワイルド7』と『アモン』
鈴木プロは、池袋東口の繁華街の一角にあった。
隣にあるのは古い映画を100円で見せてくれる文芸座。事務所の入っている雑居ビルは、地下にサウナ風呂、1階と2階には当時の呼称でトルコ風呂(現在のソープランド)が入っていた。
雑居ビルの3階から5階までが貸事務所になっていて、鈴木プロは4階の1室を使っていた。
3階から上の階へは、ビルの裏手にある鉄製の外階段を昇っていく。
この階段は、2階にあるソープランドの非常口にもなっていたが、営業前の時間は、掃除のためか、いつもドアが開けっぱなしになっていた。
廊下の両側に並ぶ個室のドアも開いたままで、頭にタオルを巻いたソープ嬢が、ドアにもたれて煙草をふかしていることもあった。
カンカンと靴音が響く階段を昇り、4階のドアを開けると細長い廊下があり、その両側に貸事務所のドアが並んでいた。会計事務所もあったが、なんだかわからない怪しげな事務所が多かった。
怪しさでは鈴木プロも負けてはいない。そもそも事務所内の構造が異常だった。
事務所は横に細長い部屋で、窓に向けてスチールデスクと椅子が5つずつ。背後の壁にはスチールの書棚が置かれ、大量のマンガや書籍が並んでいた。
窓の外は狭いベランダで、そこにはプレハブの小部屋が建てられていた。
この小部屋が社長室だった。事務所の窓を開いて出入りする構造である。窓の両側には、小さな踏み台が置かれていた。
鈴木プロでの初仕事は、コミックスの写植貼りだった。写植が使われるのは、もちろんマンガのネーム――つまりセリフやナレーションの部分である。
ぼくに写植の貼り方を教えてくれたのは、少年画報社を退職し、鈴木プロの契約社員として働いていたTさんだった。
Tさんは、まず、椅子に座る姿勢から教えてくれた。
まず机にまっすぐに向かって椅子に腰をおろし、身体を机と正対させる。
次に原稿の底辺を机の縁にきっちりと当てる。身体がまっすぐ原稿に向かうようにするためだ。
つづいて原稿用紙の吹き出しの中に、ハサミやカッターで切った写植をのせていく。位置が確定したら、写植の裏に写真用セメダインを塗り、あらためて吹き出しの中に貼りつけていく。
ぼくがはじめて写植貼りをしたマンガは、少年画報社から新書判コミックスとして発売予定の『ワイルド7』だった。
新書判コミックスが誕生してから、まだ5年も経っていなかった。
コダマプレスが、マンガの新書判コミックスを発売したのは1965年のことだ。手塚治虫の『ロストワールド』、石森章太郎の『ミュータント・サブ』といった中高生あたりをターゲットにした作品を中心にしてスタートした新書判コミックスの市場に、やがて、朝日ソノラマ、秋田書店なども参入し、マーケットの規模を拡大した。
自社の雑誌に連載された作品が、他社からコミックスになる状況をこころよく思わなかったのか、講談社、小学館、少年画報社といった少年週刊誌の発売元も、自社ブランドの新書判コミックスを立ち上げつつあった頃である。
「少年キング」連載の人気マンガ『ワイルド7』も、そのような流れのなかでコミックス化が決まった作品だった。少年画報社にとっては初の新書判コミックスでもあったはずだ。
この当時、マンガのネームには、写植(写真植字)が使われるのが当たり前になっていた。江波先生のところでアシスタントをしていたときも、原稿が遅れると、ネームを印字した写植とハサミと写真用セメダインを持参した編集者が、完成した原稿の吹き出しの中に、小さく切った写植を貼りつけていた。
だが、不思議なことに、『ワイルド7』の原稿には写植が貼られていなかった。吹き出しの中には、青インクの万年筆でネームが書かれているだけなのだ。
この当時、マンガを印刷するには、次のような手順を踏んでいた。
(1)マンガの原稿を写真製版し、亜鉛凸版にする。
(2)凸版の吹き出しの位置に穴を開け、ネームを組んだ活字を穴の裏側から突き出し、固定する。
(3)片面16ページ分の亜鉛凸版を並べ、紙を押しつけて紙型をつくる。
(4)この紙型に溶けた亜鉛を流し、16ページ分の亜鉛凸版をつくる。
(5)この凸版を印刷機のドラムにかけ、用紙に印刷する。片面16ページずつ、表裏で2回印刷し、一折(両面32ページ)ができあがる。
この用紙を4回折りたたんだあと、ノド側を針金などで綴じ合わせ、残る3辺を断裁したものが、本や雑誌となって出荷されるのだ。
週刊誌の時代になり、マンガ家も多忙になってきたことから、マンガのネームは、写植を切って原稿に貼りつける方法が一般的になっていた。
原稿に写植が貼りつけられていれば、原稿をカメラで撮影する写真製版の際、カメラの一発撮りで作業が終了する。前記(2)の作業が省略できるのだ。その分だけ入稿から印刷までの時間が短縮されることになる。写植は、入稿時間を短縮できる秘密兵器のようなものでもあったのだ。
ところが便利な写植にも欠点があった。当時は、まだ写植の料金が高かったのだ。そのため急ぎの原稿以外での写植の使用は敬遠する出版社も多かった。少年画報社も同様で、締切が早いマンガ家の原稿のネームは、写植を使わずに、活字を組む方法をとっているとのことだった。
 『ワイルド7』作者の望月三起也氏は、人気マンガ家でありながら、締切が早いマンガ家でもあった。決められた締切の数日前には、原稿が上がるのが当たり前らしい。『ワイルド7』の原稿には、いっさい写植が使われていないのは、ここに理由があった。
『ワイルド7』作者の望月三起也氏は、人気マンガ家でありながら、締切が早いマンガ家でもあった。決められた締切の数日前には、原稿が上がるのが当たり前らしい。『ワイルド7』の原稿には、いっさい写植が使われていないのは、ここに理由があった。
ところがコミックスは、すべて、オフセットという方式で印刷されている。平版印刷ともいわれるオフセットは、活字を使うことができず、すべて写植を使う必要があった。そのため『ワイルド7』の原稿に、新たに写植を貼る必要が生じたのだ。
『ワイルド7』では、写植の貼り直し以外にも、めんどうな作業があった。
コミックスの本文ページは、基本的にモノクロである。雑誌連載時はカラーだったページも、当然、モノクロになる。
ところが、当時の色分解技術では、4色原稿をモノクロにすることはできたが、フィルター技術の関係で、2色原稿の色分解が苦手だった。そのため、2色原稿をそのまま製版すると、赤色の部分までスミベタになり、画面が真っ黒けになってしまうのだ。
これでは何が描かれているのか、わからなくなってしまう。そこで2色原稿をモノクロ印刷するときは、原稿を新たに描き直すか、あるいは、原稿か雑誌のページをトレスして、新たな原稿にする方法がとられていた。
ちなみに2色原稿とは、通常、スミと赤(朱色に近い)のインクだけが使われる。この2色だけで、赤ベタ、スミベタ、ピンク(赤アミ)、灰色(スミアミ)のほかに茶色(赤アミ+スミアミ)を出すことができた。
トレスとは、トレペ(トレーシングペーパー)を原稿や印刷された雑誌のページに重ね、ペンでタッチを似せながら、そっくりに描き写していく作業のことをいう。
『ワイルド7』でも、2色ページではトレスした原稿が使われることになり、アシスタント経験のあるぼくが、作業を担当することになった。
雑誌から切り抜いた2色ページにトレペを重ね、てセロハンテープで固定し、墨汁をつけたペンで線をなぞっていくのだが、これがけっこうむずかしい。トレペは、手の脂がつけば、すぐに墨をはじいてしまうし、紙質の関係で、ペンの線もブルブルと震えがちになってしまうのだ。
それでもなんとかトレスをすませ、これが原稿として使われたのだが、その後、版をかさねた『ワイルド7』のコミックスを見たら、絵が替わっていた。どうやらオリジナルの原稿が使われたものらしい。フィルター技術の進歩で、2色の色分解が可能になったからだろうと推測しているのだが、作者の望月氏が「あんな汚い線の絵では困る」と抗議した可能性もなきにしもあらずである。
鈴木プロでは、『ワイルド7』の写植貼りと並行して、同じ少年画報社の青年コミックス第1弾の編集もおこなわれていた。「ヤングコミック」に連載されていた上村一夫氏の作品で、題名は『アモン』。上村氏にとっても自作の単行本化は初めてだったはずだ。
上村氏の雑誌に印刷されたマンガは、いかにもイラストレーター出身者らしい繊細で華麗な線で描かれていた。
ところが原稿に引かれた上村氏のペンの線は、劇画家アシスタントを経験した目から見ると、そんなにきれいでもない。
きれいに見える原因は、原稿の拡大率にあった。一般的にマンガの原稿は、実寸の一・二倍から一・三倍ほどの大きさで描かれる。これを縮小して印刷すると、画面がしまって見えるからだ。当然、線も細くきれいになる。
作画に時間のかかるマンガ家の中には、少しで描く面積を小さくしたいということから、一割拡大(一・一倍)のサイズで描く人もいた。『タイガーマスク』の辻なおき氏や、怪奇マンガで人気を集めた楳図かずお氏が、一・一倍派だった。
圧倒的多数のマンガ家が一・二倍で描いていたが、石森章太郎先生は一・三倍で描いていた。荘司としお氏が、デビュー当時に一・五倍の拡大率で描いていたことがあるらしい。
ぼくは後年、自分がマンガ家になってから、上村氏の原稿を見たときのことを思い出して、一・五倍の拡大率で描くようになった作品がある。一ページに入る情報量を増やしたい――つまり、絵の密度を高めたい――という理由からだった。
最初に一・五倍の拡大率で描いた作品は、『ゲームセンターあらし』である。掲載誌の「コロコロコミック」が、ふつうのマンガ誌より小さなA5判だったために考えついたことだった。
投稿者 msugaya : 23:04 | コメント (2) | トラックバック
2005年09月23日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(8)
●長谷川法世さんに紹介される
入社して数日目の夜。
出版社へ原稿を届けて帰社すると、ひょろりとした眼鏡の神経質そうな男の人が、椅子に座り、社長と一緒に湯呑み茶碗で日本酒を飲んでいた。
「長谷川法世さんだ。知ってるだろ?」
社長が紹介してくれた。
もちろん知らないわけがない。長谷川法世さんは、「COM」の常連投稿家で、何度かの佳作入選を繰り返した後、『正午に教会へ』という西部劇のマンガで月例新人賞に入選したマンガ家だ。とはいえ、まだマンガだけで生活するのは厳しい状態で、鈴木プロに籍を置き、読み切りマンガやカットの仕事をしているときだった。
「ども……」
毛糸の帽子をかぶった法世さんは、照れくさそうに微笑んで、ぴょこんと頭を下げた。
法世さんは、お酒を飲みながら、ポツリポツリと自分のアルバイト体験を話してくれた。
その話によると法世さんは、鈴木プロに所属する前、ソープランドでボーイをしていたのだという。ソープランドでは、個室でソープ嬢が使ったゴム製品が発見されると、売春防止法で営業停止になってしまうのだとか。そのため各個室から下水パイプを通り、汚水タンクに流れ込んできたゴム製品を、竹竿の先で水中に押し込む係が必要だった。汚水タンクを覗かれたとき、証拠物件が浮かんでいないようにするためである。法世さんは、そのゴム製品の押し込み係も担当していたとのことだった。
「けっこう情けない仕事でね……」
法世さんは自嘲気味に笑ったが、ぼくは「そんな仕事もあるのか……」と感心しながら話を聞き、同時に、階下にあるソープランドのことを想像した。
長谷川法世さんは、その翌年、「月刊ぼくら」が週刊誌化された「ぼくらマガジン」のカット、イラストを一手に引き受けて、猛烈に忙しくなる。住まいも四畳半のアパートから賃貸マンションに変わり、高校の後輩だというアシスタントを雇うまでになった。
ところが、まもなく「ぼくらマガジン」が休刊してしまい、仕事の基盤を一挙に失うことになった。法世さんは、いちど郷里の九州にもどり、沖仲仕やライブハウスで働きながら、捲土重来を期すことにした。
再チャレンジしたのは「漫画サンデー」の新人賞だった。ここで新人賞を受賞した法世さんは、同誌で『痴連』という作品の連載が決まって再上京。以前所属していた鈴木プロの部屋の隅に、金属パイプでできたボンボンベッドを持ち込み、そこで寝泊まりしながらマンガを描くようになった。
法世さんは、「ヤングコミック」などの青年劇画誌を中心に、ハード劇画風の作品ばかり何本も連載を抱え、アシスタントを何人も使うようになるが、その合間に、自分で描きたかったジャンルの作品を描きためていた。
「こんなのを描きたいと思ってさ、暇を見つけては描いてるんだ」
池袋に借りた仕事場に遊びにいったぼくに、その原稿を見せてくれた。
すでに連載を何本を持ち、数人のアシスタントを抱え、事務所もかまえるようになっていたプロのマンガ家が、掲載のあてのないマンガも描いてるのだ。ぼくもマンガだけで生活できるようになっていたが、目先の締切をこなすだけで精いっぱいの毎日を送っていたからだ。
法世さんのマンガは、ソープランドでアルバイトをする青年の苦悩をコミカルに描いた読み切り作品だった。かつて自分がアルバイトで体験したことをマンガにしていたのだ。しかも、その頃たくさん描いていたハード劇画風の作品とは、まったく違った傾向のものだった。
その作品がやっと雑誌に載ったのは、半年以上もたってからのことだった。
「漫画アクション」の増刊号に掲載され、好評だったその作品は、三回ほどのシリーズになった。
そして、この作品が母胎となったような青春マンガがスタートする。法世さん自身の思春期をモデルにした作品で、掲載誌は「漫画アクション」。作品には『博多っ子純情』というタイトルがつけられていた。
投稿者 msugaya : 01:10 | コメント (12) | トラックバック
2005年09月24日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(9)
●ちばてつや氏は、マンガも野球も全力投球
ぼくが入社した鈴木プロは、いまでは当り前になっている編集の下請けプロダクションの走りだった。ここでは、各社のいろいろな雑誌や単行本の編集を請け負っていた。
『ワイルド7』のコミックスの編集と平行して手伝ったのが、『増刊・少年マガジン』の編集だった。当時、大人気だった『あしたのジョー』『巨人の星』などの総集編をまとめる仕事である。
下請けの、さらに見習いの編集者とはいえ、『あしたのジョー』や『巨人の星』のナマ原稿を目にすることができるのだ。それだけでも、マンガ家になりたいぼくにとっては、アシスタントをする以上の価値があった。
もちろんマンガ家の先生のお宅にも、原稿取りなどで、しばしばお邪魔することになる。それはそれで、また楽しい体験だった。
総集編をまとめるときに困るのは、雑誌掲載時の広告スペースや見開き処理の問題だった。雑誌掲載時に広告用に割かれた1ページの縦3分の1、あるいは横2分の1のスペースが、ぽっかりと空白として開いてしまっているのだ。総集編では、このスペースを埋めてもらわなければならない。
さらに、連載時のページ数も、偶数ページだったり奇数ページだったりと一定していない。そのため扉をはずして総集編にまとめると、空白のページができてしまうことがよくあった。この空白ページも埋めてもらう必要があった。
しかし、忙しい先生方に原稿を依頼しても、どうしても目先の連載原稿が優先されるため、描き足しの原稿が遅れることがよくあった。そのため先生がたの仕事場でアシスタントを監視し、原稿のできあがるのを待たないといけないこともあった。もちろん徹夜になることもある。
だが、それも苦にはならなかった。マンガの技術を知る機会も多かったからだ。
たとえば川崎のぼる氏のところでは、アシスタントが、アルミのかぶらペンを裏返しにして細い線を引いていることを知った。てっきり丸ペンを使っていると思ったのだが、こんな方法で掛け合わせの斜線などを引いていたのだ。高価な丸ペンを使うのに比べ、安あがりな方法だった。
ちばてつや氏は、完全主義者だった。たとえば縦1/3の広告スペースを埋める作業でも、縦長の駒をアシスタントの描く背景で埋めておしまい、などということはしなかった。ぶ厚い原稿用紙(画用紙)のコマの両脇を、断面が斜めになるようにカッターでカットする。縦長になった紙の両側に、やはり断面が斜めになるようにカットした紙を貼り合わせ、もとの原稿用紙と同じサイズにしてしまうのだ。
そのうえで、背景を描き足していくと、そこに広告スペースがあったこともわからない画面になった。
 縦1/3の広告スペースは、背景だけのコマで埋めるマンガ家さんが多かった。どうしても時間のとれないマンガ家さんの場合は、隅にカットを配置するだけですませるのも珍しくはない。しかし、ちばてつや氏は、そのような妥協が許せないようで、面倒な手間とヒマをかけ、広告スペースを消してしまうのだ。
縦1/3の広告スペースは、背景だけのコマで埋めるマンガ家さんが多かった。どうしても時間のとれないマンガ家さんの場合は、隅にカットを配置するだけですませるのも珍しくはない。しかし、ちばてつや氏は、そのような妥協が許せないようで、面倒な手間とヒマをかけ、広告スペースを消してしまうのだ。
ちば氏は、カラーの表紙の試し刷りが出たときなども、きちんとご自身の目で確認した。「この色をもう少し強く」とか「ここは、もう少し弱く」と、見習い編集者の前で、みずからチェックしてくれるのである。ぼくは緊張しながら指示を聞き取り、会社に帰ると社長に伝えた。
ちばてつや氏は、そのマンガのイメージどおりに、誠実の固まりのような方だった。
この少し前、アシスタントをしていたときに、マンガ家の野球チーム同士の試合に、人数が足りないからと助っ人として参加したことがあった。助っ人として参加したのはマンモスというチームで、対戦相手が、ちば氏ひきいるホワイターズだった。
場所は石神井公園に隣接する野球場。この試合で、ライト前にクリーンヒットを放ったちば氏が、セカンドを守るぼくのところに突っ込んできたことがある。ぼくは、ライトからの返球を捕球し、タッチに行こうとしたのだが、ちば氏は、そこに猛然とスライディングしてきたのだ。それもスパイクを履いた足を前にして。
スパイクを履いた野球の経験などなかったぼくは、タッチにいったグラブを弾き飛ばされ、ボールも落としていた。もちろん判定はセーフ。
そのときグラブをしていた左手が痛むのに気づき、目をやると、左手の甲から血が流れているではないか。ちば氏にスパイクされた部分から出血していたのだ。
結局、セカンドの守りは別の人に交代してもらい、ぼくは敵軍のベンチで手の治療を受けることになった。ちばてつや氏の家族やアシスタントが応援に駆けつけていて、救急箱まで用意されていたからだ。
ぼくの手をオキシドールで消毒し、赤チンを塗ったあと、包帯を巻いてくれたのは、ちばあきお氏の奥様と、当時、ちばてつや氏のアシスタントで、まもなく「なかよし」でデビューし、『でっかいちゃんと集まれ』などで人気を博す、あべりつこ氏であった。
話が横道にそれたが、このエピソードでもわかるように、野球でも全力疾走なら、仕事でも手を抜かないのが、ちばてつや氏であった。マンガ家生活は長いが、そのわりに作品数が多くない理由はここにある。1本の作品の連載期間が長いせいでもあるが、あのような誠実なマンガづくりをしていたら、とても大量生産などできそうにない。
投稿者 msugaya : 14:00 | コメント (3) | トラックバック
2005年09月26日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(10)
●ジョージ秋山氏と差し向かいでマンガを描く
『増刊・少年マガジン』では、人気ギャグマンガの『ほらふきドンドン』(ジョージ秋山)や『キッカイくん』(永井豪)の総集編も担当することになった。
最初に原稿取りに伺ったのは、ジョージ秋山氏の仕事場だった。西武池袋線・椎名町駅から徒歩5分ほどのところにあるマンションの一室が、秋山氏の仕事場になっていた。
見開き処理の関係で、何ページか描き足してもらう必要が生じ、その原稿取りに出かけたのだ。
「おう、よく来たな」
チャイムを鳴らすと鉄のドアが開き、秋山氏が顔を出した。
顔には薄い茶色のサングラスをかけ、着るものは黒ずくめ。マンガに出てくるのと同じスタイルの秋山氏が、そこにいた。しかも畳敷きの部屋の中を下駄履きで歩いている。
ぼくが玄関で靴を脱ぐべきなのかどうか戸惑っていると、
「そのまま上がってきな」
と、秋山氏が声をかけてくれた。
おそるおそる土足のまま部屋に上がり、畳の部屋を通り抜けていく。もう長いこと土足で歩いているせいなのか、畳表はゴルフ場の芝生のように毛羽立ち、逆立っていた。
アシスタントたちは、別のアパートの一室で仕事をしているとのことだった。このマンションは、秋山氏と、このときは不在だったが、若くて可愛らしいアイドルのタマゴのような女性秘書がいるだけだった。
奥のベランダに面した部屋が、秋山氏の仕事部屋になっていて、机がひとつだけ置かれていた。
秋山氏は、自分の机の正面に、椅子をひとつ持ってくると、「そこに座れ」という。
「あの……原稿は……?」
ぼくは、椅子に腰をおろして、おずおずと訊いた。
「おめえ、アシスタントしてたんだってな。ベタくらい塗れるだろ?」
唐突に秋山氏がいった。
「は?」
「おめえんとこの社長がいってたぞ。これから原稿取りにいく若いのは、ちょっと前までアシスタントをしていたから、ベタ塗りくらいなら手伝わせてかまわねえってな」
薄い色のサングラスの奥の目が、ぼくを見てニヤリと笑っていた。
秋山氏のアシスタントは、別のアパートにある仕事場で連載の原稿に追われていて、こちらの仕事に割く時間もないらしい。でも入稿の時間は迫っている。
「だったら、原稿をとりにいくうちの若いのが、マンガも描けるから手伝わせたらどうだ」
と、うちの社長が電話でもちかけた結果、秋山氏が了承したということのようだ。
秋山氏は、自分の机の上に原稿用紙をひろげると、
「おれがこっちからペン入れしてくから、おめえは、そっち側からベタを塗れ」
といって、ぼくの前に墨汁と筆を置いた。
秋山氏は、ささっとシャープペンシルで下絵を入れると、シャカシャカと、すごい勢いでペンを走らせていく。いや、走らせる、というよりも、たたきつけるといった方がいい。『ほらふきドンドン』のキャラクターと背景が、一気に描かれていくのだ。
ぼくは、その迫力に気押されしながら、秋山氏がペンを入れる原稿用紙に、向かい側からベタを塗っていった。1枚の原稿に2人が向かい合わせになって、同時にペン入れとベタ塗りをする経験など、もちろん生まれて初めてのことだ。いや、その後、自分がマンガ家になってからも、このような経験は一度としてなかった。
時間がないので、ホワイトも使わないですむように、慎重にベタを塗っていった。同じ紙の上に、一方ではペン入れがされているのだから、当然、紙も動く。ベタを塗りにくいったらありゃしなかったが、秋山氏は鼻歌まじりでペンを入れていく。ぼくの背後の壁にはレコードプレーヤーが置かれ、古今亭志ん生の落語がかかっていた。
ベタ塗りが終わった原稿をヘアドライヤーで乾かすと、ぼくは、その原稿を持って、大急ぎで事務所にもどった。入稿の時間が、もうギリギリになっていたからだ。
秋山氏のところに原稿を取りにいったのは、このとき1回こっきりだったが、翌年、また再会を果たす。鈴木プロをやめたあと、臨時のアシスタントを頼まれ、毎週、秋山氏の仕事場に通うようになるからだ。
そして、あの「『アシュラ』騒動」が起きたとき、ぼくもチョッピリ巻き込まれることになる。そんな運命(?)が待ち受けていようとは、原稿取りをしているときにわかるはずもない。1969年の終わり、ぼくは、まだまだヒヨッコの見習い編集者だった。
投稿者 msugaya : 00:25 | コメント (3) | トラックバック
2005年09月30日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(11)
●ライター見習い
鈴木プロでは、マンガの雑誌や単行本の編集だけでなく、マンガに関連したことなら、どんな仕事でも請け負っていた。
「ちょっと、すがやクン。キミも手伝ってくれないか」
ある日、突然、社長から命令されたのは、電話インタビューの仕事だった。「週刊女性自身」から依頼されたもので、その頃ちょうど話題になっていた永井豪さんの『ハレンチ学園』に対する識者の声を集めるものだった。そう、あの「スカートめくり」が、子どもたちの教育上よろしくない、ということで大問題になっていたことから、エライ先生方の声を集めることになったものだ。
ぼくが担当したのは、『フイチンさん』で知られる上田としこ氏や、永井さんのマンガの擁護者でもあったカバゴンこと教育評論家の阿部進氏。いずれも『ハレンチ学園』の「スカートめくり」には否定的なコメントではなかった。そのほかにも数人の識者に電話でインタビューし、そのコメントの要点を200字詰め原稿用紙にまとめていった。
社長も電話でコメントを取っていたのだが、ぼくがまとめた原稿を見せると、
「はじめてなのに手際がいいじゃないか。だったら、こっちの分もやってくれ」
といわれ、社長が担当するはずだった人たちへのコメント取りまでやることになった。
といわれ、社長が担当するはずだった人たちへのコメント取りまでやることになった。
まとめたコメントの原稿は、池袋駅から都電に乗って、音羽の光文社の近くにあった同社の別館に届けにいった(まだ都電が走っていた)。ホテルのような建物で、指定された和室には、テーブルに資料と原稿用紙、そして、ちびた4Bの鉛筆を山のように並べた中年の男性がいた。
この人が記事の最終原稿をまとめる人で、週刊誌の業界ではアンカーと呼ばれていた。案内してくれた「女性自身」の編集者の話によれば、このアンカー氏は、作家志望で、歴史小説の大家・海音寺潮五郎氏の弟子とのことだった。
「よろしく、お願いします」
座布団にすわり、こちらに背中を向けているアンカー氏の脇に、ぼくは部屋の上がりかまちから、おそるおそる原稿の束を差し出した。
さっと原稿の束を取ったアンカー氏は、ぼくが書いたコメント原稿の文章を、赤鉛筆で囲っていく。どうやら本番原稿に使えそうな部分に印をつけているらしい。
「これキミが書いたの?」
アンカー氏が、背中を向けたまま訊いてきた。
「はい。初めて書いたんですが……」
「ふーん……。そのわりには、うまく書けてるじゃないか。このコメント、話し手の口調も、よく出てる。どれも、そのまま使えるよ」
どうやら褒められているようだった。電話インタビューで得たコメントも、なるべく、その方たちの口調を活かした話し言葉でまとめてあったのだが、マンガでネーム作りをしていた経験が、こんなところで役立ったものらしい。
こんなことが何度かあって、社長はぼくに、ライターの仕事もまわしてくるようになった。まだ隔週だった「少年チャンピオン」の柱の原稿(「豆知識」のようなもので、100字前後で100本以上書く。「世界の国旗100」を書いたときには、国旗の絵も必要だといわれて、「現代用語の基礎知識」にカラーで出ていたの世界の国旗を、トレペに丸ペンと墨汁でトレスした)、「COM」の「マンガ家短信」のページなどだ。
「マンガ家短信も、マンガ家の先生方に電話で近況をたずねたり、決められたテーマに沿ってインタビューした内容を文字原稿でまとめるものだった。マンガ家のデビュー作を特集する回があり、真崎守氏にデビュー作について質問したところ、『地獄狼』という青年劇画誌に掲載した作品の名前が返ってきた。
「あれ、先生のデビュー作は、セントラル書房から出ていた『街』の新人賞受賞作じゃないんですか?『雨の白い平行線』と、もう1作が同時受賞していたはずですが。その後に、東京トップ社から『燃えてスッ飛べ!』という永島慎二先生原作の作品も描いていませんでしたか……?」
と問いつめると、渋しぶ、本当のデビュー作の名前を出してもいい、ということになった。もしかすると「真崎守」名義でのデビュー作と、かつての「もりまさき」名義の作品とは、区別して考えていたのかもしれない。
投稿者 msugaya : 23:01 | コメント (0) | トラックバック
2005年10月21日
■■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(12)
●マンガ家地獄編――永井豪さん『鬼』にたたられる
「別冊少年マガジン」で、人気マンガ家の仕事場訪問を担当させられたのも、入社直後のことだった。人気マンガ家の仕事場をイラストで図解してもらい、1週間の食事のメニューを書いてもらう。その食事メニューには、その頃、人気の高かった医事評論家の石垣純二氏がコメントをつけることになっていた。
十人以上のマンガ家の方々の仕事場を訪問し、仕事場を描いたイラストと食事メニュー集めるのが、ぼくの任務である。
最初に『スパイダーマン』(平井和正原作)の池上遼一さんは、吉祥寺の薄暗いアパートで、ゴミの山の中でマンガを描いていた。
印刷された絵は、すごくきれいで、なおかつ迫力があるのに、原稿は、ほんとうに汚かった。ろくに鉛筆の線も消えておらず、強いタッチの線が、画用紙に食い込んでいた。
問題は永井豪さんだった。
ちょうど初の長編SFマンガとなった『鬼』を描いていたときで、永井さんは過労で倒れてしまっていた。
ダイナミック・プロのマネージャーT氏は、「少年マガジン」に一挙掲載予定の『鬼』の原稿が落ちそうで、とても仕事場のイラスト図解など描いている暇はないという。「どうしても仕事場のイラストが必要なら、そちらで勝手に描いてくれ」というのだ。しかたないので、ぼくがダイナミック・プロに出かけて仕事場をスケッチし、このスケッチを元に描き上げた絵が、誌面に使われることになった。
急いでいたので、あまりいい出来だとは思わなかったが、原稿の監修をお願いしたT氏は、原稿を見るなり、ぼくの顔を覗き込んできた。
「これ、きみが描いたの?」
「はい」
「うーーん、よかったら、うちにこないか?」
と、いまの言葉でいうヘッドハンティングをされたのだ。
いくらなんでも、入ったばかりの会社をやめるわけにはいかないので、丁重にお断りし、さらに高校生のときのイキサツもT氏に説明した。ひょっとしたら、ぼくは、永井豪さんの第1号のアシスタントになっていた可能性があったのだ。
高校3年のはじめ、すでに石森先生のアシスタントになる内諾を得ていた『墨汁三滴』会長の菅野誠から、ぼくのところに電話がかかってきたのだ。
「石森先生のところから独立した永井さんが、ギャグマンガを描けるアシスタントを捜しているんだけど、紹介してほしい?」と菅野は言うのだ。
ギャグマンガも描いていたぼくの絵柄なら、たぶんOKだろうという。喜んで、紹介して欲しいと頼んだのだが、菅野が話してくれたときには、すでに先約が決まっていた。ぼくたちが目標としていたマンガ同人誌のひとつ『宝島』(竹宮恵子、大和田守[夏希]さんたちも会員だった)の会長をしている小山田つとむという人が、アシスタントに決定してしまったというのだ。
そのときは永井さん自身も、こんなに忙しくなるとは夢にも思わず、アシスタントは1人で充分と思っていたらしい。
「そりゃ残念だったねぇ」
といってくれたダイナミック・プロのマネージャーT氏に連れられて、今度は永井さんの実家を訪問した。永井さんのお母さんから、最近の1週間の食事のメニューをインタビューするためだ。
しかし、家がすぐそばなのに、仕事が忙しく、家で食事をとることもないらしい。過労で倒れてしまったのも、そのあたりに原因があるようだった。
『鬼』の方は、園田光慶氏のところから独立したばかりの新進マンガ家で、直後に「週刊ぼくらマガジン」で『超人ハルク』を描く西郷虹星さんや、まもなく「別冊少年サンデー」で児童文学作家の山中恒氏作の『天文子守唄』をマンガ化する川手浩次さんたちが手伝って、なんとか完成させていた。
そうそう、永井さんの仕事場には、石森先生のところで永井さんと一緒にアシスタントをしていた野口竜さん(後に「少年サンデー」でアリステア・マクリーンの『女王陛下のユリシーズ号』をマンガ化)が手伝いにきていたし、その後、ダイナミックプロの中枢になる石川賢さんもアシスタントとして活躍中だった。
マンションの室内だというのに、高下駄を履き、竹刀を持って、後輩をしごいていたのは、後に永井作品の『マジンガーZ』を「冒険王」に連載することになる桜多吾作さんだった。
その取材の際、永井さんのお母さんが一生懸命思い出しながら、正直に教えてくれた永井さんの食事のメニューに対する石垣純二氏のコメントは、「死にたくなかったら、早く結婚しなさい」だった。
投稿者 msugaya : 22:22 | コメント (3) | トラックバック
2005年10月23日
■■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(13)
●『少年マガジン』の黄金時代と初めての原稿料
ここで中心になって登場している「少年マガジン」は、この頃が、まさに黄金時代だったといえるだろう。有名な内田徹編集長のもと、「右手にジャーナル、左手にマガジン」、「1ページに1万語」といった名コピーが、次々と登場していた頃だ。
上村一夫氏による笹沢左保原作の『見返り峠の落日』などの股旅モノなど、長編問題読み切りが、続々と掲載されていた。石森先生も、『リュウの道』を連載しながら『仮面ライダー』の前身となる『スカルマン』を発表していた頃だ。
表紙のレイアウトにイラストレーターの横尾忠則氏を起用したのも同じ頃である。
一九六九年暮れの講談社の話題は、一九七〇年の新年合併号(六九年末発売)で一挙に百五十万部を刷ることだった。
七〇年早々には、『あしたのジョー』は、天井桟敷の寺山修司氏の企画で、講談社の講堂にリングを特設し、ジョーのライバル・力石徹のお葬式が執り行われたりもした。
『巨人の星』はアニメにもなって、「父ちゃん!」という声優・古谷徹さんのセリフが流行語になっていった。
このとき「少年マガジン」は、ただのマンガ週刊誌を超え、一種の社会現象ともいえる状態になっていた。その熱気のほどは、バブルの頃、「少年ジャンプ」が数百万部を超す発行部数を誇ったところで及ぶものではなかった。
その熱気があふれる音羽の講談社に、ぼくは、池袋から走っていた都電に乗って、毎日のように通っていた。スポーツ新聞の記者に書いてもらったプロ野球やプロレス記事の原稿をリライトしたり、色原稿の入稿も怒られながら憶えたり。「少年マガジン」の編集部だけでなく、児童部や絵本部といった部署にも出入りした。豪華版のマンガ単行本やマンガを使った絵本の編集をするためだ。といっても、ぼくの仕事のほとんどは、原稿取りなどの使いっ走りだった。

「すがやくん、ちょっと四コママンガを描いてくれないか?」
いきなり社長に言われて、ぼくは、とまどった。社長からは、何度も、「きみはマンガがヘタだし、マンガでは芽が出そうにない。編集の仕事に身を埋めたほうがいい」と、繰り返し言われていたからだ。
「いやね、『COM』に連載してるマンガ家短信のページの記事が埋まらなくてさ、急きょ、そのページの穴埋めしないといけなくなったんだ」
「少年キング」を経て「COM」の編集に参加し、その後、独立してマンガ専門の編集プロダクションを作った社長は、「COM」に連載されている「マンガ家短信」のページも受け持っていた。しかし、社長を含めて総勢四人の会社である。そのうち編集経験があるのは社長も入れて二人だけ。残るは、元マンガ家アシスタントのぼくと経理の女性だけという布陣だった。
社長も営業と編集とで駆け回っているため、ときおり細かい仕事がピンチになることがあった。そのせいで、社長がみずからら担当していた「マンガ家短信」のページが落ちそうになってしまったのだ。
「マンガ家短信」は、毎号、いろんなテーマを決めては多数のマンガ家に電話をかけ、取材した内容を記事にまとめて伝えるページである。これから取材して原稿を書き、そのページを写植で組んでもらって……という手順を踏んでいたら校了に間に合わないのだという。
そこで社長が考え出したのが、二ページを四コママンガ四本で埋めることだった。マンガなら、原稿さえあれば、あとはカメラ撮りして写真製版するだけだから、入稿時間が短くなる。
ベテランマンガ家の井上のぼる氏に鈴木プロ所属の長谷川法世さん、ぼくをこの会社に引っ張りこんだ清つねおさん、そしてぼくの四人が四コママンガを一本ずつ描いて、ページを埋めることになった。
とにかくなんでもいいというので、その頃、好きで読んでいた秋竜山さんのマンガをまねたナンセンス風の四コママンガを描き上げた。そして、すぐに、近所に住む長谷川さん、井上のぼるさんのところに原稿を取りにいく。清さんは、事務所の机でささっと四コママンガを描き上げてくれた。
完成した原稿を、急いで同じ池袋にあった「COM」の編集部に運ぶ。入稿がギリギリになったせいで編集長もカンカンだ。ひたすら謝りながら原稿を渡すと、飛ぶように事務所に逃げ帰ってきた。
まもなく給料日がやって来た。給料袋の中身は、いつもより五百円多い。社長が「こないだの『COM』の四コママンガの原稿料だ」と言った。マンガも給料のうちだと思っていたので、まさか原稿料なんかもらえないと思っていたぼくは、びっくりしながらも、もちろん、ありがたく頂戴した。
その頃、毎日食事に通っていた定食屋の定食が百三十円。五百円あれば三回の食事に生卵くらいはつけられる。こうして、生まれて初めてもらったマンガの原稿料は、胃袋の中に消えていったのだった。
ちなみに、この当時、フトコロがさみしくなると出かけていたのが、池袋東口の大戸屋という定食屋だった。この店のカレーライスは五十円。当時にしても格安の料金で、非常に助かったものである。その後、吉祥寺に、同じ名前の女性も入れるおしゃれな定食レストランができたと思ったら、やがて、あちこちに拡大し、いまでは、ちょっとしたターミナル駅なら、どこでも目にすることができる。その大戸屋の発祥の地が、ここ池袋東口だったのだ。かつての発祥の地には、現在、数店の大戸屋が軒を並べている。
投稿者 msugaya : 13:26 | コメント (3) | トラックバック
2005年11月13日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(14)
●天才マンガ家・坂口尚
一九六九年の終わり--世の中は、来年の万博ブームに浮かれていた。マンガの方でも、講談社の『のらくろ』をはじめとする豪華本がブームになっていた。
『のらくろ』豪華本の成功に気をよくした講談社では、ヤナギの下のドジョウを狙って、いろいろな豪華マンガ集を出版することにした。
『巨人の星』『あしたのジョー』『サイボーグ009』などの名作をカラー版の豪華コミックスとして発売するという企画である。その編集の仕事が、ぼくが勤めていた編集プロにまわってきたのだ。しかも同時に、世界名作のマンガ化まで引き受けることになった。
『巨人の星』『あしたのジョー』などは、画用紙にモノクロで原稿を縮小印刷した主版というものをマンガ家の先生のところに持っていき、それに絵の具で着色してもらう。それも大量なので、それでなくても忙しいマンガ家のアシスタントたちには、露骨に嫌な顔をされたものだった。
しかし、それでも原稿はもらわないといけない。着色を担当するアシスタントの仕事を見ながら、「へぇ、すごいですねぇ」「わぁ、こんなふうにして色を塗るんですか」といちいち感心しては、アシスタントに気をよくしてもらい、なんとか、原稿を進めてもらっていた。
売れっ子マンガ家のアシスタントの仕事ぶりには、ただただ驚くことばかりだった。たった半年のアシスタント経験しかないぼくを比較の対象にするのはおかしいが、仕事は早いし、何よりもペンの使い方などが手慣れていて、実に絵がうまいのだ。そんな作業を見ているだけでも、将来、自分がマンガ家になったときのプラスになるような気になったものだ。
ところが鈴木プロの社長には、「すがやクンは、マンガが下手なんだから、マンガ家になるのは諦めて、編集者として骨を埋めたほうがいい」と、繰り返し言われていた。この年の暮れには、田舎に帰った清つねおさんが、鈴木プロの社長の名代としてぼくの家を訪ね、母に「マンガ家になるのは断念して、ぜひとも編集者に……」という言葉を伝えたらしい。それほどマンガ家としては期待されず、編集者のタマゴとしてだけ期待されていたのだった。
坂口尚さんという新人マンガ家を紹介されたのは、そんな頃(1969年の終わり)のことだった。
虫プロのアニメーターだった坂口さんは、マンガを描きたくて鈴木プロに所属し、ハンマー坂口というペンネームで「プレイコミック」に、軽めのアクションマンガを描いていた。
この坂口さんに、講談社の世界名作マンガのうちの一冊を依頼することになった。『トム・ソーヤの冒険』が、坂口さんの担当である。
しかし、青年誌の連載や「COM」の読み切りもあって、なかなか単行本にはかかれない。連載の原稿を間に合わせるため、ぼくが坂口さんの住んでいた上石神井のアパートに急行し、徹夜でベタ塗りを手伝うこともあった。
初めて手伝いに出かけたときは、アシスタントの経験があったので、簡単な背景くらいは手伝うつもりでいた。ところが原稿を見たとたん、絵の手伝いは、瞬間的に断念した。ふつうのマンガとは、描き方が異なっていたからである。
まず原稿に、鉛筆の下絵が入っていなかった。コマ割りをしてネームを描いた下絵用の薄い紙に、丸と線だけの人物を示す当たりが入っている。
その紙に別の紙を重ね、トレス台を使って下絵を透かせると、上に重ねた白紙に枠線を引く。そして、いきなり墨をつけたGペンで、本番の絵を描いてしまうのだ。
だから、ペン入れがすんだ原稿には、鉛筆の線がない。当然、消しゴムをかける必要もなかった。背景も、さささっと、下絵もなしに描いていく。ぼくが手伝うのは、スミベタと修正のホワイトだけだった。
それまで、編集者も経験したおかげで、多くのマンガ家の仕事場を訪問していたが、こんな描き方をするのは、坂口さんだけだった。まさにアニメの出身らしい描き方でもあった。表情も何も描かれていない鉛筆の当たり線を透かせただけで、いきなりペンを入れてしまうのだ。そんな描き方を見ていると、本当に天才としか思えなかった。
その天才ぶりは、しばらくしてからもらった『トム・ソーヤの冒険』のカバー絵にも現われていた。ふつう、マンガのカラー原稿というと、にじまない製図用の黒インクでペン入れした原稿に、さくらやペンテルの水彩絵の具で、ペンの線を殺さないように、薄く着色していくものだ。だが、坂口さんのカラー原稿は、アクリル絵の具という、それまでのマンガ家には考えられない絵の具で、まるで油絵のような塗り重ねを多用した重厚なタッチで描かれていた。
さらに、見返しと呼ばれる表紙を開いた部分の絵になると、まるで、デザイナーかイラストレーターが描いたような、しゃれたデザイン感覚に満ちあふれた絵を描いていた。
おまけに原稿には、絵の具を定着させるためのフィキサチーフというスプレーがかけられていて、テカテカに輝くと同時に、カチカチに固まっていた。
さらに原稿のサイズが大きかった。マンガの原稿は、仕上がりサイズの一・二~一・三倍の大きさで描かれるのがふつうだったが、坂口さんの原稿は、二倍ほどの大きさで描かれていた。ほかに、こんな常識はずれの大きさの原稿を見たのは、ぼくがやはり編集をした故・上村一夫氏の初の単行本『アモン』だけである。『アモン』は一・五倍の大きさで描かれていた。
坂口さんは、アニメ出身ということもあり、さらに、イラスト感覚を持ち込み、それまでの常識からは、かけはなれたマンガ家だといってよかった。
その後、坂口さんは、虫プロが製作した大人向け長編アニメ『クレオパトラ』のマンガ化を手がけ、さらに、『ぼくらマガジン』で平井和正氏原作による『ウルフガイ』を連載することになる。
『トム・ソーヤの冒険』のばかでかいカラー原稿を事務所に抱えて帰ったぼくは、あまりにも原稿が大きかったせいで、原稿の端で湯呑茶碗をひっくり返すミスをしでかした。しかも、そのお茶が原稿の一部にかかってしまったのだ。そこだけ絵の具が変色してしまい、ぼくは青ざめた。
しかし、さいわいにして被害は印刷に入らない部分だけですんでいた。おかげで本の進行も遅らせずにすみ、ほっと一息つくことができたのだった。
……と思っていたのだが、つい最近になって『トムソーヤーの冒険』を見たら、カラー口絵の端に、シミのようなもの……。これは、もしかして、ぼくがこぼしたお茶の跡かもしれない……。
追記:そういえば、今日(2005年11月13日)、竹熊健太郎さんのBlog「たけくまメモ」に書かれていた大阪万博の「太陽の塔」についての文章を読んでいて思い出したのだが、坂口さんとは、講談社の子ども向け公式大阪万博ガイドブックの仕事も一緒にしたことがあった。講談社の別館に住み込み状態のカンヅメになり、和室の座卓に坂口さんとぼくがならび、ぼくが書く文章の原稿を見ながら、坂口さんがカットを描いていく仕事である。坂口さんは、シーラカンスでも何でも、下絵などなしに、いきなりペンで描いてしまうのだ。しかも、その早いこと早いこと。やはり、ここでも坂口さんは天才だった。
投稿者 msugaya : 21:28 | コメント (21) | トラックバック
2005年11月16日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(15)
●もう一人の天才――ダディ・グース
 この頃は、坂口さんをはじめ、個性的なマンガ家がたくさん登場していた。マンガ界にとって、最も熱気にあふれた時代でもあったのだ。
この頃は、坂口さんをはじめ、個性的なマンガ家がたくさん登場していた。マンガ界にとって、最も熱気にあふれた時代でもあったのだ。
なかでもユニークなマンガ家を輩出していたのが双葉社の『漫画アクション』だった。同社の『漫画ストーリー』に登場したモンキー・パンチ、バロン吉元といった人たちが、それまでにないアメリカンナイズされたユニークな絵柄と構成で『漫画アクション』に新作を描き、人気を集め始めていた。
『ルパン3世』のモンキー・パンチ氏は、兄弟ふたりの合作のペンネームだった。兄弟のどちらかが、時代マンガで第1回講談社新人賞を受賞していたはずだ。
バロン吉元氏は、セントラル出版という名古屋の貸本劇画専門出版社から出ていた『街』という短篇劇画誌の新人賞受賞者だった。その後、横山まさみち氏の横山プロダクションに入り、吉元正の名前で『鉄火場シリーズ』などのヤクザものを手がけていたが、『漫画アクション』に出てきたときは、絵柄も名前も変わり、西部劇や『賭博師たち』(傑作!)といった作品を手がけるようになっていた。『柔侠伝』という大ヒットが生まれるのは、この少し後のことだ。
『漫画アクション』には、ほかにもユニークなマンガ作品が登場していたが、なかでも気になったのは、アメリカのパロディ雑誌『マッド』に掲載される似顔絵マンガに似たバタ臭いマンガで、作者の名前はダディ・グースといった。
『平凡パンチ』に紹介されたプロフィールによれば、東大付属駒場高校で学園闘争をし、そのままドロップアウトしてマンガ家になったということだった(※東大付属ではなく東京教育大付属だったかもしれない。ダディ・グース氏の叔父さんだったかが、「平凡パンチ」の編集者だったと、宮谷一彦氏から聞いたことがある)。
絵柄は確かに『マッド』のマンガを下敷きにしていたが、アメリカの似顔マンガをまねるには、デッサン力が必要になる。デッサンの素養のないぼくには、逆立ちしても真似のできない絵柄だった。そのむずかしい絵柄で、オリジナルのパロディマンガを描いていたのがダディ・グースだったのだ。
「ダディー・グースは天才だ!」
ぼくは心底そう思い、マンガ仲間にも触れてまわったのだが、誰も同意してくれなかった。当時のアシスタントは、劇画系の細密な描写をするマンガ家を好む傾向が強く、パロディマンガに関心を持つ人は皆無に近かった。
それは、一般のマンガ雑誌の読者にとっても同じだったらしい。たぶん人気アンケートのせいだとは思うのだが、ダディ・グースのマンガは『漫画アクション』でも、一九七四年あたりを最後に見かけなくなっていく。
その後、ダディ・グースの名前を見つけたのは、早川書房の『ミステリマガジン』誌上だった。そこで彼はレイモンド・チャンドラーの『長いお別れ』をマンガ化していたが、主人公であるフィリップ・マーロウの顔は、どう見ても、テレビ映画『逃亡者』で主人公のリチャード・キンブルを演じたデビッド・ジャンセンだった。
その連載と平行してだったろうか、終了後だったろうか、同じ『ミステリマガジン』に、バタ臭い感覚の横須賀の刑事を主人公にした国産ハードボイルドが掲載された。作者の名前は矢作俊彦といった。この作者の初の書き下ろし長編『マイク・ハマーへ伝言』が、光文社から出版されるのは一九七八年のことだが、その直後、『リンゴキッドの休日』も早川書房からハードカバーで出版された。
このハードボイルド作家・矢作俊彦氏こそが、マンガ家ダディ・グースの変身した姿だったのだ。矢作氏は、その後、古巣の『漫画アクション』で大友克洋氏とコンビを組み、『気分はもう戦争』の原作を手がけることになる。
 『少年レボリューション』(ダディ・グース/飛鳥新社/2003年四月刊/2,625円)
『少年レボリューション』(ダディ・グース/飛鳥新社/2003年四月刊/2,625円)
※冒頭の写真は、矢作俊彦氏の作品(『リンゴキッドの休日』と『夏のエンジン』。後者は装丁がダディ・グース名義。大判の本は、2003年に復刻されたダディ・グース氏の作品集『少年レボリューション』。懐かしさにかられて、つい買ってしまいました。
投稿者 msugaya : 23:16 | コメント (10) | トラックバック
2005年11月30日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(16)
●『燃えろ南十字星』に原画で再会
昭和45年……この頃から、一般週刊誌にもマンガや劇画が連載されるようになってきた。ぼくがときおり取材を手伝っていた『女性自身』でも、劇画の連載を始めることになった。
『女性自身』での劇画連載第1作は、五木寛之氏の小説だった。北欧シリーズの一篇で(「霧のカレリア」だったかな? 記憶がさだかでなくてすみません)、松本零士氏が作画を担当した。そして、このページの編集を鈴木プロが請け負うことになり、ぼくが担当編集者に指名されたのだ。
この劇画(この頃は、ストーリーマンガだったら、なんでもかんでも劇画にされていた)は、毎週8ページという短いものだったが、松本氏の筆が遅く、毎回、泊り込みをしないと原稿がもらえなかった。
締め切り時間が過ぎても原稿ができず、とりあえず、ネームだけとりにいく。ネームとは、もちろんマンガのセリフのこと。これを写真植字(写植)に打ち出してもらっているあいだに原稿を進めてもらい、完成した原稿に、その場で写植を貼りつけるのが毎回の恒例になって。
しかし、ネームだけ入った原稿用紙--それもスケッチブックを切り離した厚い画用紙だ--の上にトレーシングペーパーを重ね、セリフを書き写していくのだが、その字が独特の崩れた字で、さっぱり読めないのだ。松本氏は、ネームだけ入れると、どこかに出かけてしまうため、夫人の牧美也子氏に、読めない文字を教えてもらいながらネームを書き写すことが多かった。
この連載の担当をしているときに、ぼくは、松本氏の家の応接間で、思わぬものに遭遇した。応接間にあった暖炉のなかに古いマンガの原稿が押し込められているのを見つけたのだが、そこには、なんと、あの「燃えろ南十字星」の原稿があったのだ。そう、小学生のとき、ぼくがマンガを描きはじめるきっかけになった作品だ。
ぼくは、原稿の完成を待つあいだ、このナマ原稿に読みふけった。零戦が、グラマンが画面の上で躍る『燃えろ南十字星』の原稿は、八年か九年前に描かれたものだったが、このときでも充分に面白く、徹夜の原稿待ちもすっかり忘れさせてくれたものだった。
――本当は、マンガを描くために東京に出てきたんじゃなかったのか? それが、マンガの編集をする立場になってしまっている。本当に、これでいいのか……?
『燃えろ南十字星』の原稿を読んでいると、そんな言葉が脳裡に浮かんでは消えた。
会社では、あいかわらず社長から、「すがやくんは、マンガよりも編集の仕事の方が向いている」といわれつづけていた。あまり何度もいわれると、反抗したくなるのも人情だ。
ぼくは、毎夜アパートに帰ると、また、こっそりとマンガを描くようになった。
投稿者 msugaya : 15:37 | コメント (2) | トラックバック
2005年12月05日
■『仮面ライダー青春譜』第4章 アシスタントから編集者へ(17)
●『赤頭巾ちゃん気をつけて』
「女性自身」に連載された五木寛之・原作、松本零士・作画の「劇画」連載は、予定どおり8回で終了することになった。しかし、劇画の連載企画そのものが終了したわけではなく、「女性自身」の編集部では、さらに話題性のある文芸作品の劇画化を目論んでいた。
「女性自身」が次の連載劇画の原作として白羽の矢を立てたのは、芥川賞を授賞し、映画化が発表されたばかりの『赤頭巾ちゃん気をつけて』だった。
作者は庄司薫氏。「劇画」化は、矢代まさ子さんが担当することになった。
(矢代まさ子氏の作品を「劇画」と呼ぶのは抵抗があるので、ここからは「マンガ」に統一する)
マンガの原稿に取りかかる前に、まず庄司氏に挨拶しようということで、矢代さん、「女性自身」の担当編集者、そして、ぼくの3人で、指定された銀座のウエストという名曲喫茶に出かけることになった。
この頃の庄司氏は、超多忙で、行方をくらましてばかりいた。編集者と会うのも、月に何日かだけ。庄司氏と会いたい編集者は、あらかじめ指定された時刻に、指定された場所に出かけるしか会う方法がないという話だった。
そのせいか、ウエストに着くと、あちこちのテーブルに編集者らしき男女がすわり、入口の方にギョロリと目を光らせていた。
高校を卒業するときに母が買ってくれた一張羅のスーツに身を包んだぼくは、矢代さんと編集者と一緒にテーブルについた。メニューを渡されたが、よく知らない名前の飲物ばかりが並んでいる。てっきりソーセージがついてくると思って頼んだウィンナコーヒーの飲み方がわからず、「女性自身」の編集者に教えてもらっていると、よそのテーブルにいた他社の編集者らしき人が、ぼくたちのテーブルに歩み寄ってきた。
その編集者は、ぼくの顔を覗き込むと、いきなりこういったのだ。
「あの庄司先生ですか?」
「はあ……?」
ぼくがあっけにとられていると、
「ちがう、ちがう。彼は、うちの編集のお手伝いさんだよ」
と、横から「女性自身」の編集者が助け舟を出してくれた。
他社の編集者は、ぼくを庄司薫氏とまちがえたらしい。
「どうも、写真と雰囲気が似てたもんで……」
といって、その編集者は去っていった。その編集者も、庄司氏には、まだ会ったことがなかったらしい。
「芥川賞作家と間違えられるなんて、光栄だね」
「女性自身」の編集者と矢代さんが、けらけらと笑った。
庄司薫氏が店内に姿を見せたのは、十五分ほど過ぎてからのことだ。白のスーツに身を包んだ庄司氏は、さっそうとテーブルからテーブルを飛び歩き、待たせていた編集者たちと打ち合せをかさねていく。その姿は、まさにマスコミの寵児という形容がぴったりだった。
やがて庄司氏が、ぼくたちが待つテーブルにやってきた。
庄司氏は、『赤頭巾ちゃん気をつけて』のマンガ化に関連して、いくつかの条件を出してきた。そのなかの最重要案件は、マンガの原稿を掲載前にチェックしたいというものだった。映画化が進められている折りでもあり、映画に悪い影響が出るのが心配だというのだ。
ぼくは内心、少しムッとしていた。『ようこシリーズ』をはじめとする矢代作品を貸本時代からたっぷりと読んでいて、矢代さんが、いかに優れた作品を描くマンガ家であるかを知っていたからだ。
――ひょっとするとマンガが小説を凌ぐかもしれない……。
そんなことまで、ひそかに期待していたほどだったのだ。
もちろん、原作者の前で、そんなことを口に出せるはずもない。おそらく、矢代さんも悔しい思いをしたはずだが、やはり沈黙を守っていた。
それから二週間ほどが過ぎ、第一回目の原稿の締め切りがやってきた。
マンガ家で締め切り日に原稿を仕上げてくれる人は、まずいない。矢代さんも、その例に漏れなかった。
しかし今回は、原作者サイドの事前チェックがあるので、その分、締切を前倒しにする必要があった。そのため、原稿の締切は、実際の入稿日よりも、かなり早めに設定されていた。
締切日の早朝、国分寺にあった矢代さんのお宅に伺うと、まだ原稿が終わっていなかった。あわてたぼくは、女性のアシスタントと一緒になって、仕上げを手伝うことにした。
スクリーントーン貼りを手伝おうとしたら、カッターの数が足りないという。しかたがないので、ボンナイフという小学生が鉛筆削りに使う折りたたみカミソリを借り、これでトーンを切って原稿に貼りつけた。
おかげで締切時刻に間に合ったが、もちろん締切とは、原作者に原稿を見せる約束の時刻のことである。庄司氏に原稿を見せる役目は、光文社の編集者が担当した。
「あのマンガの連載が、延期になった」
突然「女性自身」の担当者から連絡があったのは、二、三日後のことだった。編集者は、矢代さんの描いた原稿を、庄司薫氏本人と、映画の監督を担当していた森谷司朗監督に見せて、掲載の了解をとりつけようとした。ところが、結果はノー。編集者は、掲載を延期してほしいと要求されてしまったのだ。
映画化に当たって一年がかりで改訂をかさね、ようやく決定稿に漕ぎつけたばかりのシナリオのファースト・シーンと、矢代さんが描いたマンガのファースト・シーンが、まったく同じだったという。矢代さんのマンガのファーストシーンは、原作にはない矢代さんが独自に考えたものだった。もちろん映画のシナリオなど読むチャンスもない。主人公の薫クンが、広い川の河川敷のようなところを歩くシーンだったが、似たのは、まったくの偶然だ。
映画が公開される前にマンガが出ると、映画がマンガを真似したと思われかねない――というのが、ノーの理由だった。映画の公開後だったら、いつ掲載してもかまわないというのだが、マンガ化に当たっての条件に、このチェックが含まれていたため、これは呑むしかなかった。
「女性自身」の編集部は、頭をかかえた。すでに連載劇画のページ枠を取ってあるのだ。八ページというストーリーマンガにしては短いページ数だったが、女性週刊誌にしては、大盤振る舞いのページ数だった。
すでに締切が迫っていたため、他のマンガ家に連載を依頼する時間もなく、一回は、穴埋めの企画でページが埋められることになった。
だが、次の週には「劇画」の連載をスタートさせたいという。そこで再び白羽の矢が立ったのが、五木寛之氏の小説だった。
「女性自身」では、数ある五木氏の傑作短編小説のなかから『海を見ていたジョニー』を第一候補に選ぶと、五木氏に劇画化の許可を求めにいった。
ところが五木氏は、『海を見ていたジョニー』の劇画化に当たり、事前に担当する劇画家の絵を見せてほしいといってきたらしい。前回、五木氏の作品を劇画化した松本零士氏の絵が、あまりお目にめさなかったらしいのだ。担当していたぼくは、まるで違和感を感じていなかったのだが、五木氏は、もっと劇画劇画した絵柄が望みだったらしい。
『海を見ていたジョニー』は、ぼくも読んでいた。青春小説の傑作である。この作品を劇画化できるとしたら、それは、ひとりしかいない。しかも五木氏も絶対に気に入るはずだという確信があった。
「女性自身」の編集者と鈴木プロの社長が、候補となるマンガ家の名前をあげているところに、ぼくは生意気にも口を挟んだ。
「『海を見ているジョニー』を劇画化できるのは、宮谷さんしかいないと思います」
宮谷さんとは、もちろん宮谷一彦さんのことだ。
鈴木社長は、目玉をギョロリと回してぼくを見た。
「うん、いい、彼ならピッタリだ!」
元「COM」の編集者で、宮谷氏のデビューにも立ち会っている社長は、何度も首を縦に振った。
「誰、それ?」
「女性自身」の編集者は、宮谷さんを知らなかった。もちろん五木氏も知らないだろう。そこで、ぼくが持っている宮谷さんの作品の切り抜きを「女性自身」の編集者に渡し、それを五木氏に見てもらうことになった。
ぼくは、宮谷さんのほぼ全作品をスクラップしてあった。このスクラップを「女性自身」の編集者に預けたのだ。
スクラップの表紙には、この直前に公開されて大ヒットした映画『イージーライダー』の中で使われていたステッペン・ウルフの歌、『ワイルドで行こう(Born to be Wild)』の歌詞を英語で書き連ねてあった。いまにして思えば実に恥ずかしい行為だが、当時は、そういう時代でもあったのだ。

|

|

|

|
投稿者 msugaya : 00:57 | コメント (3) | トラックバック
2006年08月22日
■同級生からの手紙:貸本屋のオバサン、健在なり

先月、高校の同級生(女性)から手紙が届いたのですが、先週、やっと手紙の主と連絡がついて、Blogへの転載許可をもらいました。以下に、その内容を紹介させていただきます。
ご無沙汰していますが、お元気ですか?
先月、富士に帰って父方の伯母に会ったのですが、その時、菅谷くんの話が出ました。
伯母は昔、中島(註:地名)で「S文庫」という貸本屋をやっていたのですが、そこに菅谷くんがマンガを借りに来ていたと言っています。ご記憶にありますでしょうか?
自分の店でマンガを借りていた菅谷くんが東京へ行ってマンガ家になったと、とてもうれしそうに話していました。
それはいいのですが、なぜか伯母は、菅谷くんが「やくみつる」のペンネームでマンガを描いていると思っていて、私が、やくみつるは別人だと言ってもなかなか信じません。
そこでお願いなのですが、「すがやみつる」の名前が入ったマンガの作品(雑誌の連載マンガのコピーでもかまいません)があったら、それにサインして送っていただけないでしょうか。
ついでに菅谷くんの最近の写真も送っていただければ、テレビに出演している「やくみつる」とは別人だと分ると思います。
伯母は少々呆けてきましたが、相変わらず元気で口うるさいおばさんです。息子が10年前に亡くなったので、今は息子の奥さんと暮しています。
勝手なお願いで申し訳ありませんが、菅谷くんの作品を見たら、きっと伯母も喜ぶと思うので、よろしくお願いします。
それではまた。
菅谷様
2006/7/4
(署名)
この貸本屋さん、よおおぉぉぉぉく憶えています。この貸本屋は、わが家と高校との中間地点にあって、毎日のように通っていました。仕入れの相談にまで乗っていましたが、だんだん客足が途絶えるようになり、仕入れる本も少なくなってきたため、ぼくは貸本劇画の出版社から、直接、購入するようにもなりました(直接買うと、原画がオマケにもらえた)。
いつも白い割烹前掛けをつけて、眼鏡をかけた目が、絶えずニコニコしていたおばさんでしたが、名前を憶えられていたのは、貸本の貸し出し帳に名前を書いていたからかもしれません。確かに、いいお得意さんだったはずです。高校卒業後は、この貸本店に行ったことはありませんが、ぼくがマンガ家になったことは、近所の人にでも聞いたのかもしれませんね。この店は、ぼくが上京した後、貸本屋を畳んだ、という話だけは聞いていました。
でも、高校生時代に通い詰めた、この貸本屋が、ぼくのマンガ家への夢を育んだ「環境」のひとつであったことは間違いありません。
はいはい、すぐに著作と写真を送ることにします。高校時代の写真も複写して送れば、顔も思い出してくれるかな?
それにしても当時通っていた高校の同級生の伯母さんだったとは、思いもしませんでした。
ちなみに、ぼくの貸本体験については、以下に記載しています。





